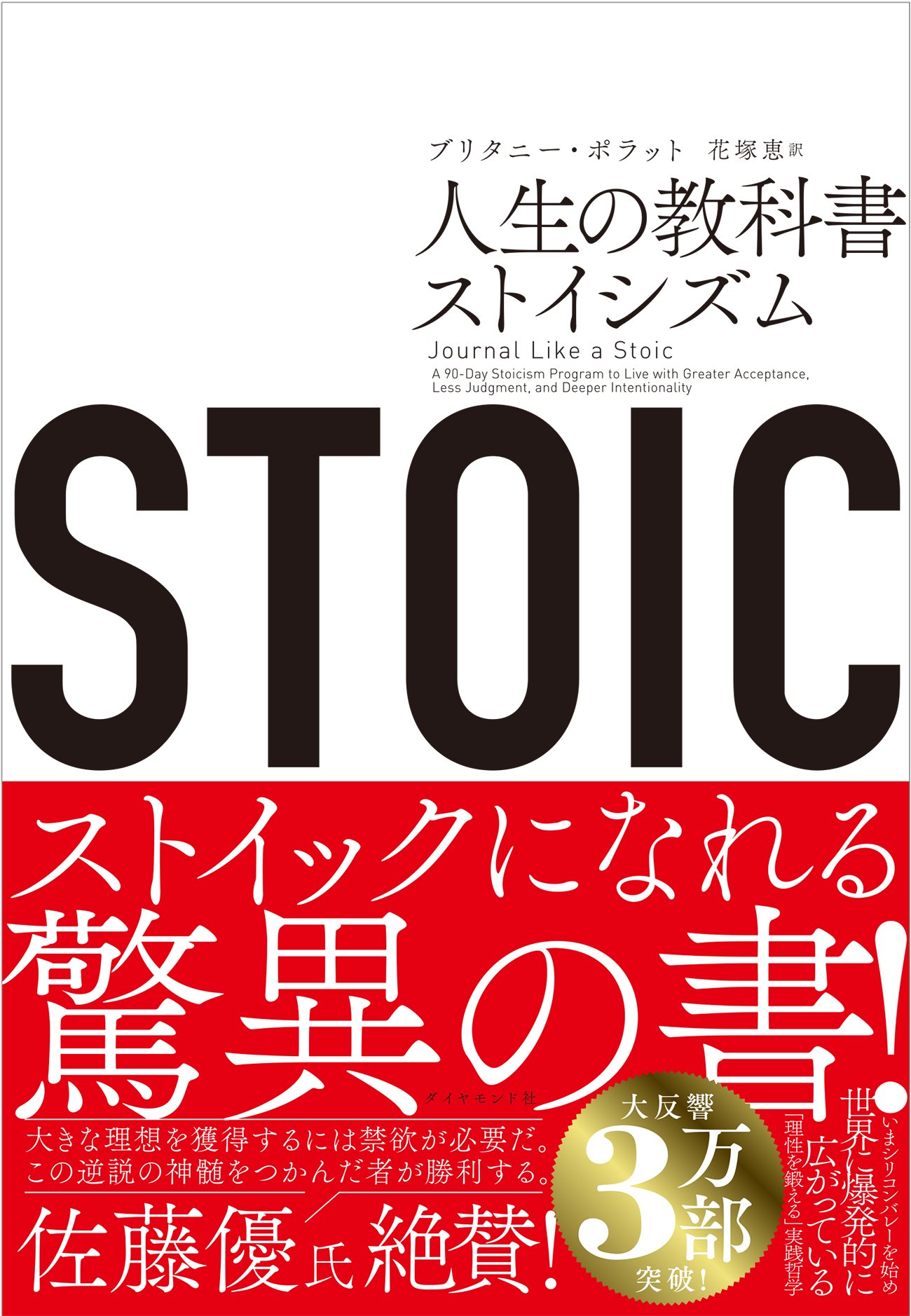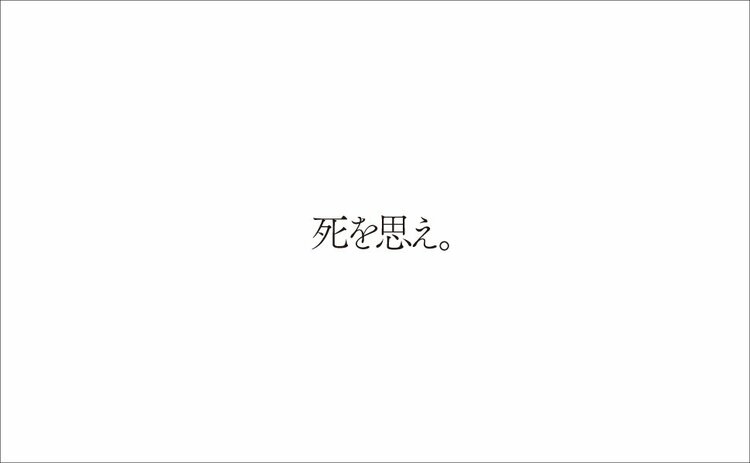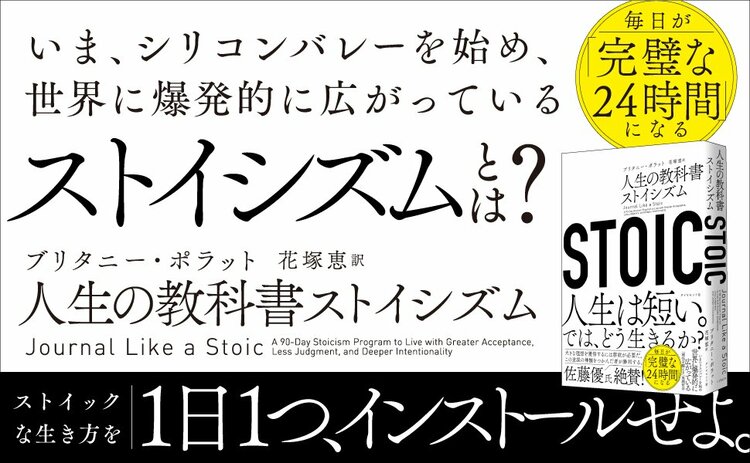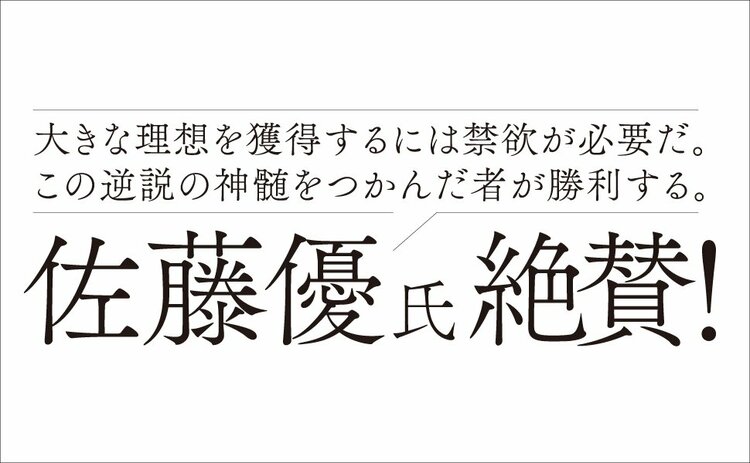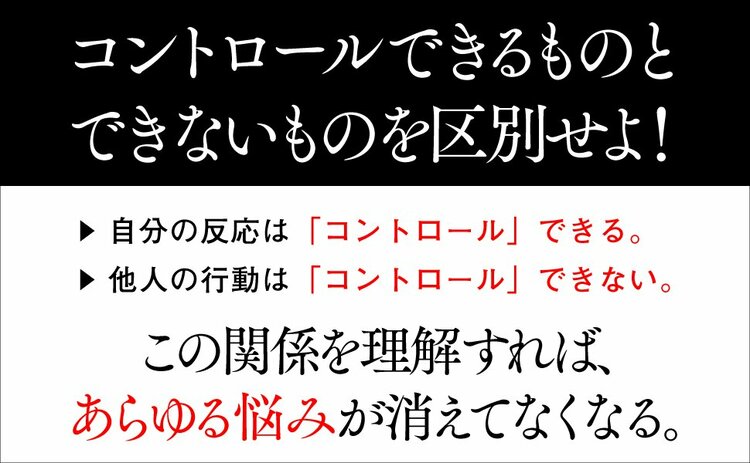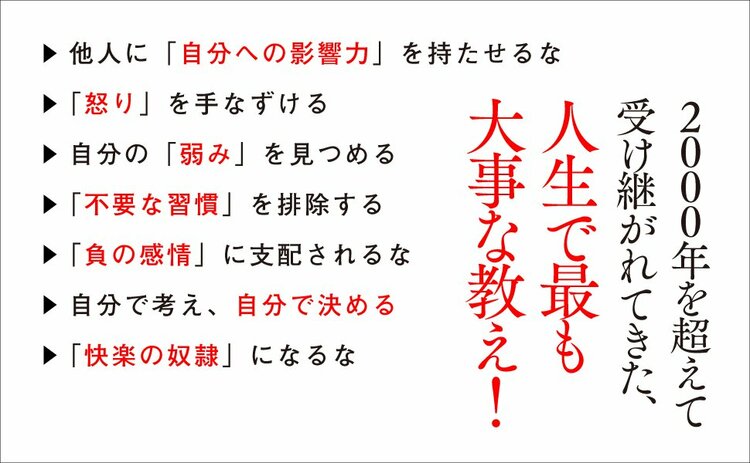いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
イライラしては反省する
息子にはちょっとした肌のトラブルがあり、小さい頃から悩まされてきた。病院に行って薬を処方してもらいつつも、根本的に直すにはどうしたらいいのか、私はさまざまな本を読んで勉強した。
息子の性格や体質も含めて照らし合わせると、一番しっくりくる改善法は砂糖や油を控えることだ。体質的に消化しきれないのに摂りすぎているため、皮膚に症状が出てしまうと考えられた。
食事やおやつに気を遣うようになってから、息子の肌トラブルは相当改善した。薬も必要なくなり、本人も忘れて過ごせるようになった。
ところが先日、夫の実家でケーキやシュークリームを食べ、てきめんにひどい状態になってしまった。私なら絶対そんなに食べさせないのにと、つい腹が立ちそうになる。
そのうえ、息子はその翌日、油たっぷりの駄菓子を勝手に買ってきて食べていた。小言を言おうとしたら、
「お母さんには怒られると思ったから、小さいヤツにした」
私は反省した。「そんなもの食べたらつらい目に遭うよ」なんて言われて、嬉しいわけがないのだ。そのうち、私に隠れて食べるようになるだろう。それでは何のために努力しているのかわからない。
ストア哲学者でローマ皇帝であったマルクス・アウレリウスは、「自分の思考」「宇宙」「自分を取り巻く人たち」の3つについて日々確かめるように説いている。
自分を導くものは何か?
自分自身の理性については、正しいものにするために、宇宙の理性については、自分が何の一部であるかを再認識するために、隣人の理性については、それが無知か、知識にもとづいているものかを理解するために、そしてその理性が自分のそれと同種のものであるということを考えるために。(マルクス・アウレリウス『自省録』)
――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より
ストイシズム(ストア哲学)では、論理学、自然学、倫理学という3つの分野を理解することが大事だとされている。
論理にもとづいて真実を判断しようとすること(論理学)、自然界や宇宙について畏怖や驚嘆、感謝をもって考えること(自然学)、相手の態度に関係なく、周囲の人に対して忍耐、思いやり、寛容を示すこと(倫理学)で、よい人生を送れるようになると考えられている。
3つの視点で考える
「子どものおやつ」という些細なことに関しても、論理学、自然学、倫理学の視点で考えることができる。
「何を食べるべきか、何を控えるべきか」は、情報や経験から論理的に判断すべきことだ。
また、食べ物が身体にどのように作用するかを考えると、自然の摂理や人間の身体のしくみの精巧さに気づかされる。こうした驚きや感謝の感情は、自然学の視点にあたる。
難しいのは倫理学の視点だ。
息子の考えや行動は、何にもとづいているのか? 冷静に見なければならない。私から見て間違った行動をとっていたとしても、それはわざと間違えているわけではない。夫の行動もそうだ。感情的にならず、思いやりをもって理解しようとすれば自分の行動もまた変わってくる。
どんな物事に対しても、ただ論理的に考えるだけでなく、「宇宙」や「他者」とのつながりを意識することで、人間らしい考え方ができるのだ。
常日頃からメンタルが安定している人は、どんなときも感情的に反応せずに、いったん立ち止まって、物事を多面的に考えることができている。
さまざまな角度から世界を理解しようとすることこそがストイシズムの実践であり、こうした思考の積み重ねがよりよい行動につながっていくのだと思う。
(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)