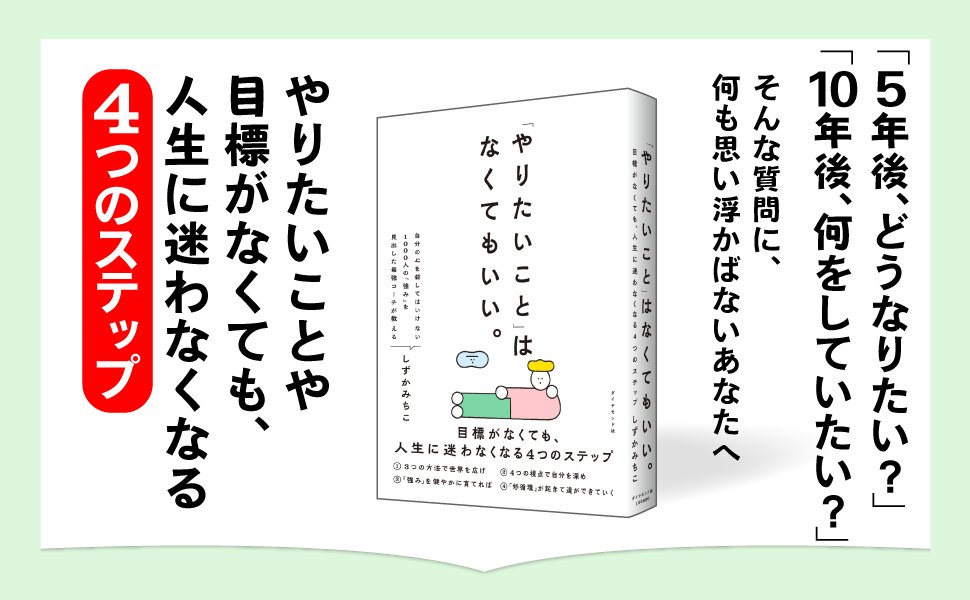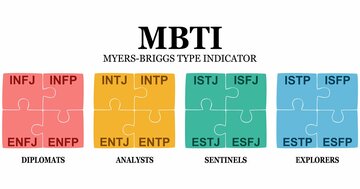社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。
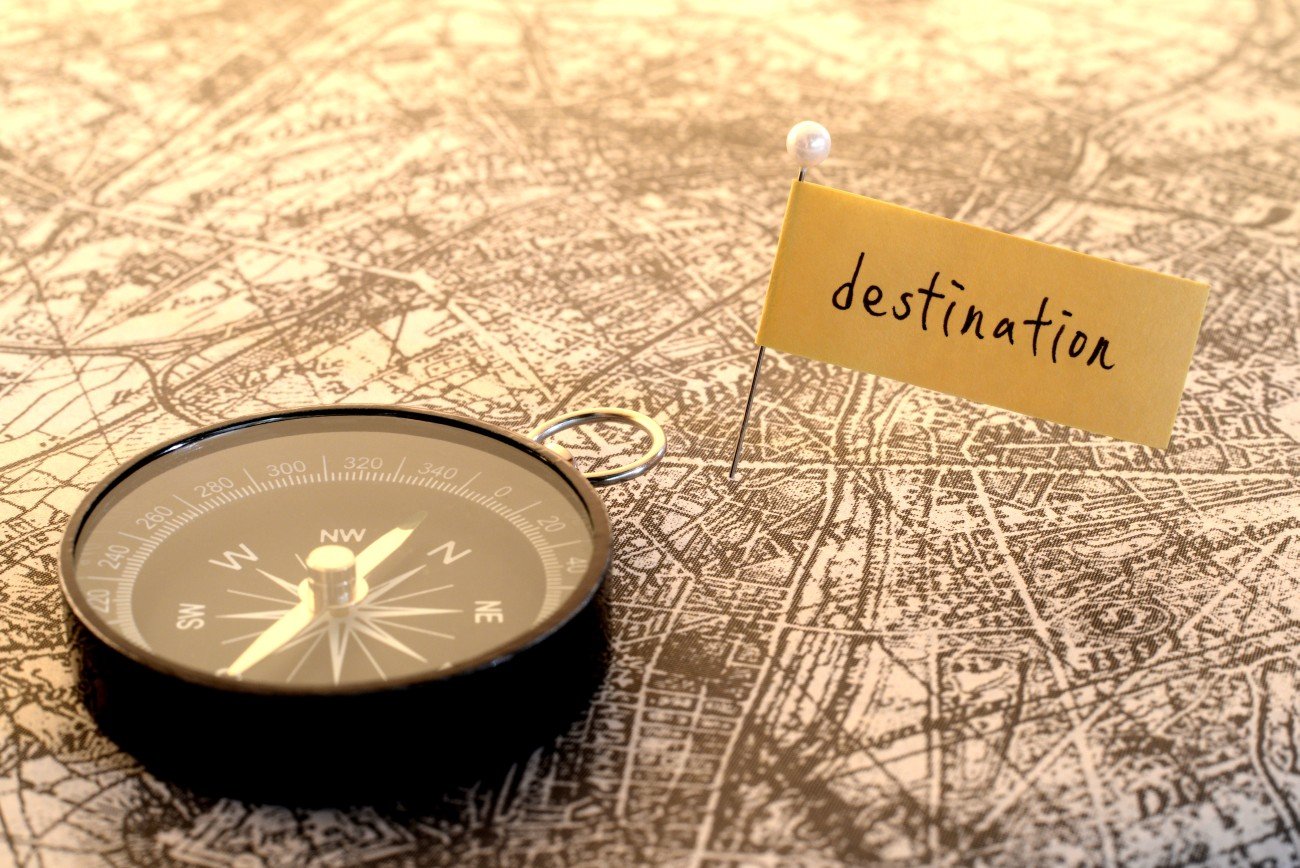 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
目標が立てられないのは悪いこと?
「やりたいことが見つからない私って、ダメな人間ですよね。何が原因でしょうか」という質問をされることが多いのですが、本当にそうでしょうか?
私の思い出話をします。私の仕事は厳密にはコーチングとは違うのですが、近い部分はあるので、折に触れてコーチングについて学んでおり、そのときの話です。
コーチングは、狭義の意味では「目標達成に向けて対象者の能力や気力を引き出し自発的な行動を促す対話手法」を指すので、「目標」や「やりたいこと」と親和性が高く、受講者も目標を立てることを求められる場合が多いです。
コーチングの場では、目標が立てられない人は、何か原因があるとされ、その原因さえ取り除けば、目標が立てられるようになると思われることがあります。
「目標が立てられない原因」としてよく言われるのは次のようなことです。
① 知識や情報が不足している(目標達成に必要なものを知らず、イメージできない)
② 自分に制限をかけている(自分には無理だなど、自分の能力に上限を設けている)
③ 失敗を恐れている(目標を決めて失敗したら恥ずかしいので目標を立てない)
目標を立てるのが苦手な私は、「目標を立てられないお前は、勉強不足で新しいことに挑戦する勇気がない人間だ!」と言われている気がして、しょんぼりしてしまいました。この原因さえ取り除けば、目標を立てられる人間になれるのでしょうか。
その答えに気づいたのも、私がコーチング講座を受けている最中でした。
え!? 目的地がないと旅行に行けないの!?
「なぜ目標を持つのが大切なのか」という授業の中で、講師はこう言ったのです。
「旅行に行くとき、目的地が決まらないと、どこにも行けませんよね? だから、人生にも夢や目標という目的地が必要なのです」
これを聞いて、私は心底、驚きました。
「え!? 旅行に行くとき、目的地がないとどこにも行けないの!?」
と、心の中で叫んでいました。
私は、目的地や帰る日付が決まっていない旅行をしばしばします。
例えば、ある年、応援している野球チームの優勝の瞬間が見たくて、夫婦で試合のある大阪に向かいました。初日は大阪が目的地でしたが、優勝するまでチームを追いかけられるように、その後の予定も帰る日も決めずに出発しました。
結果、見事にその日に大阪で優勝決定!
勝利の美酒を散々味わってホテルに戻った深夜、「明日はどうする?」と話し合い、ちょうど関西国際空港からソウルに行く飛行機に空きがあり、見たい韓国野球の試合もあったので、ソウルに行くことに決定(こんなことがあろうかとパスポートを持ってきていました)。帰りは、ソウル→東京の直行便よりも、福岡で乗り継ぐほうが安かったため福岡にも寄り、優勝の余韻が落ち着いた頃に東京に帰りました。
また、ある日の朝は、その日が手元にある「青春18きっぷ」(乗り放題きっぷ)の有効期限最終日であることに気づいて、慌てて最寄りのJRの駅に行きました。そのままとりあえず来た電車に乗り、午前中に行けるところまで行こうと電車に乗り続け、山梨県の甲府駅で降りました。その場で見どころを検索して駅前を散歩し、ほうとうを食べ、温泉に入って、その日のうちに東京に戻りました。
さらにまたある冬の日には、岐阜県の日帰り温泉に行く予定で家を出たのですが、岐阜は大雪だというニュースを電車内で見て挫けて名古屋で降り、駅できしめんを食べながら計画を練り直し、三重県志摩の日帰り温泉に行き先を変えました。
目的地のない旅のほうが印象に残ることも
このように目的地が決まっていないまま出かけたり、決めていてもそこに行かなかったりすることが、頻繁にあります。
もちろん目的地を決めて、予定どおり帰ってくることもありますが、印象に残るのは、行き先を決めずにふらふらと、その場の気分で動く旅です。
このような話をすると、「よく、そんな行き当たりばったりの行動ができるね。私には無理!」と言われることがあります。
では、そういう人が行き先を決めない旅行ができない原因は何だろうと考えたとき、私が出した答えは次の3つでした。
① 知識や情報が不足している(ソウルは短期間ならビザなしで行ける〈2023年当時〉、JR中央本線は毎時電車があるから駅に行けば電車は来る、といった情報を知らないから、安心して動けない?)
② 自分に制限をかけている(決めた行程通りに進まなければという思いが強くて、その場の気分で動くことを悪いことだと思っているのでは?)
③ 失敗を恐れている(予定を変えて楽しめなかったら後悔する?)
この原因はどこかで聞きましたね。
そうなのです。この3つの原因は、この章の冒頭に書いた、目標を立てられる人が目標を立てられない人に対して思う原因と、全く同じなのです。
こう見ると、目標を立てられるか立てられないかの違いは、「知識や情報」「自分への制限」「失敗への恐れ」の有無ではないようです。
目標が必要な人も目標が不要な人も全ての人が、この3つを“動けない原因”として持つ可能性があるだけなのです。
目的地=目標が必要かどうかは、価値観の差
目標を立てられるか立てられないかは、どちらが劣っているとか、どちらに原因があるかとか、そういう話ではありません。
世の中には、行きたいところに到着することを重視する人がいます。
逆に、行き当たりばったりの旅での思いがけない経験、出会い、トラブルを楽しむ人もいます。
旅先で列車が何らかの理由で運休になったときに「予定が狂った!」と怒りだす人もいますし、「よっしゃー! ここをどう切り抜けようか!」とテンションが上がる人もいます。
これは何に価値を感じるかの違いであって、良いとか悪いとかどちらが優れているかとかの話ではないのです。
目標を立てられないのは原因があるわけでも劣っているわけでもなく、そこに価値を感じるか否かの違いなのです。
*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。