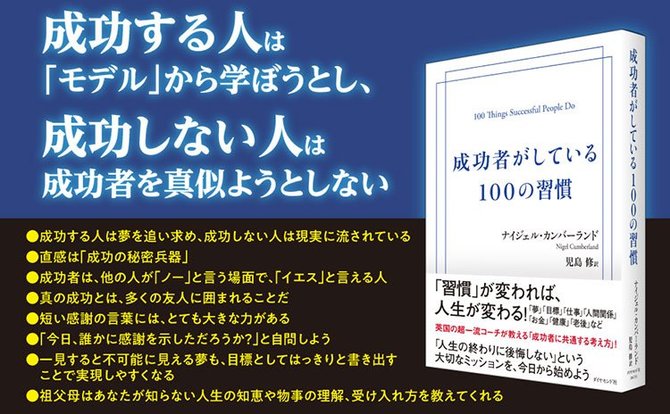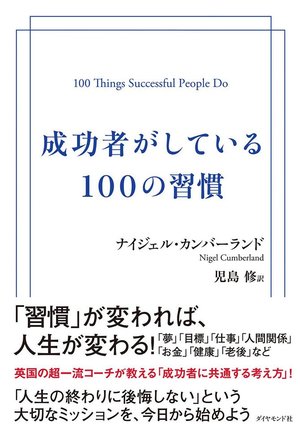15年以上にわたり、世界中の人々にコーチングをしてきたコーチは、成功する人には年齢や分野を問わず共通する習慣があることに気づく。その習慣を最重要の100個に厳選し、1冊にまとめ、ロングセラーになっているのが、『成功者がしている100の習慣』だ。著者のナイジェル・カンバーランドはイギリス人。共同経営者として起業した会社を成功させたのち、コーチになった。自らも成功した著者が見た、多くの成功者の習慣とは?
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
仕事を楽しいものにするには努力がいる
15年にわたって世界中の人々にリーダーシップ・コーチを務めてきた経験から、成功の可能性を最大限に引き出す「マインド」と「行動」について「100の習慣」としてまとめたのが、本書だ。
書籍の中で紹介されている「成功者のマインドセット」を普段から意識し、行動に結びつけている人はわずかしかいないと著者は「はじめに」で記している。
そして、そのわずかな人こそが、成功者なのだと。
著者自身、共同経営者として起業した会社を成功させ、数百万ドル規模で売却した経験を持っている。その後、コーチに転身した。
成功の要諦を記した本はたくさんあるが、本書には大きな特色がある。
それは、成功するための習慣を紹介するだけではなく、その「習慣の具体的な実践方法」が紹介されていることだ。しかも、極めて具体的に。これが、今なおロングセラーとして支持されている理由かもしれない。
成功といえば、真っ先にイメージできるのは、やはり仕事だろう。
仕事についても多くの「成功者の習慣」が紹介されているが、本書ならではのユニークなものを紹介してみたい。例えば、【成功者の習慣6「仕事を遊びに変えている」】だ。
付随する名言として投資家、ウォーレン・バフェットの「大好きな仕事をしよう。朝、心躍らせてベッドから飛び起きる毎日を過ごそう。世間体を気にして楽しくない仕事を続けていると、心は失われる」が紹介されている。
1日の時間の大半を過ごすことになるのが仕事。ならば、できるだけ楽しいものにしたい。そのためには努力が必要だというのだ。
その実践方法についても紹介されているが、誰かが仕事を楽しくしてくれるわけではない。自分で楽しくするしかないのだ。
仕事への過度の意識の傾斜は、むしろ危険
その一方で、こんな意外とも思える習慣もある。【成功者の習慣32「仕事人間になっていない」】だ。タイトルでは「成功する人は仕事を人生の一部と考え、成功しない人は仕事でしか人を評価しない」とある。
付随する名言は、アメリカの実業家、メアリー・フランシズ・ウィンターズの「私は生きるために働いているのか? それとも、働くために生きているのか?」。仕事がすべてと考えてはいけないということだ。
周りの人たちが華々しいキャリアや知名度の高い職業について話していると、子育てのために休職している人や、一度社会に出てからあらためて大学に入り直した人、失業中の人たちは居心地の悪い思いをすることがあります。(P.144-145)
たしかに、初めて会った人に、ついついまずは仕事について尋ねてしまうという人は少なくないかもしれない。当たり前のように。
しかし、職業について話すことが、その人という人間のすべてを説明することになるのかといえば必ずしもそうはならない。
人生において、仕事の重要性が大きくない人もいるのだ。いや、それがほとんどだと著者は記す。
これは人間関係、友人関係、あるいは部下へのマネジメントや上司と接する際にも、重要な示唆を与えてくれる。
自分は仕事に熱心で、仕事こそが人生を成功に導いてくれると信じていたとしても、周囲は必ずしもそうではないのである。
仕事は、人間の一面を表すに過ぎない。その人が人生をどう生きるかについて選んだ一つの答えに過ぎないのだ。
だから「習慣の実践」では、「周りからどんな人間だとみなされたいかを定義する」「成功者の形は様々」「仕事とプライベートの最適なバランスを探る」の3つのアドバイスが掲載されている。
仕事への過度の意識の傾斜は、むしろ成功にとっては危険ということである。
心の声が、外野のノイズで打ち消されてしまう
もう一つ、これもまた意外とも思える習慣かもしれない。【成功者の習慣11「直感を信じている」】だ。タイトルには「成功する人は『直感』というスパイスを活用し、成功しない人は理屈だけで動く」とある。
付随する名言は、アメリカの女優、映画プロデューサー、アンジェリーナ・ジョリーの「理屈で考え、直感に従わないと、物事がうまくいかなくなる」。
「いくつかの候補のうち、一つが特別なものに感じられる」
「何かを選んでみたが、どうにもしっくりこない」
「この人と一緒にいると、落ち着かないし、嫌な予感がする」(中略)
直感を信じることは、職場に限らず、様々な場面で私たちにメリットをもたらしてくれます。(P.55-56)
この文章を書いている私には3000人以上の取材経験がある。成功者も数多く含まれるが、インタビューでよく耳にしたのが、直感の大事さ、だった。むしろ成功者はロジックを重視する人が多いのでは、と想像していたので意外に感じた。
実際、就職先を選択するときにも、直感のようなもの、偶然のようなもので選んだという人が多かった。就活では、会社のエントランスや社員の雰囲気など、直感で感じて判断するのがいいとアドバイスしていた人もいた。
それだけに、この項目が含まれていることにとても共感を持った。だが、実際には直感を大事にするのは、難しい。心の声が、外野のノイズで打ち消されてしまうことが多いからだ。他人の意見を優先させるようなことになってしまうのである。
この「習慣の実践」では、「合理的な考えに固執しない」「静かに心の声に耳を澄ませる」の2つのアドバイスが挙げられている。
直感に従うという考えなど、ばかげていると思っている人もいると著者は記す。ただ、事実に基づいた論理的で慎重な思考をやめてしまえと言っているわけではない。
そこに直感もバランスせよとメッセージしているのだ。
いずれにしても、自分の心の声に耳を澄ませる機会は多くはないのではないだろうか。時には直感を信じてみる。やってみる価値は、十分にあると思うのである。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。