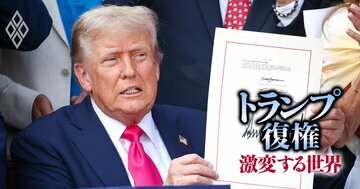ドナルド・トランプ米大統領 Photo:Andrew Harnik/gettyimages
ドナルド・トランプ米大統領 Photo:Andrew Harnik/gettyimages
FRBの金融政策は
3つの不確実性に直面
米国では、インフレ鎮静化が進み、5月のインフレ率(PCEデフレータの前年比)は+2%台半ばまで低下した。FRB(米連邦準備制度理事会)が目標とする+2%まであと一歩である。しかしながら、FRBは3つの不確実性に直面しており、金融政策の判断は困難な状況にある。
第一の不確実性は、トランプ政権による関税政策、いわゆる「トランプ関税」の行方である。各国からの輸入品に対する関税政策は、輸入品の価格上昇を通じて、インフレ動向や企業活動に大きな影響を及ぼす。
トランプ関税は、(1)合成麻薬「フェンタニル」や不法移民の流入を防止する目的の関税引き上げ策(フェンタニル関税)、(2)鉄鋼・アルミニウム製品など商品別の関税引き上げ策(商品別関税)、(3)米国と各国の貿易状況を踏まえた各国別の関税引き上げ策(相互関税)の3つに大別される。
そのうち、カナダ、メキシコ、中国向けの「フェンタニル関税」は、3月にかけて動きが激化したが、フェンタニルや不法移民の流入への有効な防止策がすぐに打ち出せるものではなく膠着状態にある。
一方、「商品別関税」については、トランプ政権は今後も引き上げる構えを崩していない。実際に、鉄鋼・アルミニウム製品向けの関税率は6月3日に25%から50%に引き上げられた。また、これまで関税賦課に向けて調査がなされてきた商品のうち、銅・関連製品には50%の追加関税が8月1日に発動される方針で、医薬品・医薬品原料にも1年間の猶予期間後に200%もの追加関税が課されるとの報道がある。その他、半導体や木材などさまざまな商品が今後の関税賦課に向けて調査されている。
さらに、「相互関税」についても予断を許さない状態が続いている。相互関税は、各国に対して発動済みの「世界共通分」10%と、国・地域ごとの「上乗せ分」で構成されている。米国は、7月9日を期限として各国との交渉を進め(対中国では例外的に8月12日まで)、交渉がまとまらなければ「上乗せ分」を発動するとしてきた。
そうした中、英国とベトナムなどごく一部の国を除き交渉がまとまらず、交渉期限は実質的に8月1日まで延期された。ただ、トランプ政権は、「上乗せ分」の税率を細かく変えつつ、交渉合意に向けた圧力を強めている。