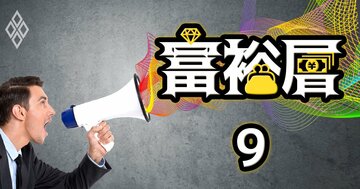写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
迅速果断な意思決定と長期志向の経営が強み
今回は、ファミリービジネス(同族企業)の強みと課題を整理し、ファミリーガバナンスが必要となる背景を確認したい。
ファミリービジネスの特筆すべき強みを三つ紹介したい。まず、「迅速果断な意思決定」が挙げられる。所有(オーナーシップ)と経営(ビジネス)が一致しているため、リーダーシップを発揮して迅速な行動が取りやすい。複合レジャー施設を手掛ける上場ファミリービジネスのラウンドワンは、2020年のコロナ禍で米国での出店を拡大する「逆張り戦略」を採ることで、コロナ後の「リベンジ消費」につなげた(注1)。不安定な環境下でも迅速果断に取り組むことができる点は、所有と経営が一致しているからこその大きな強みといえる。
次に、「長期志向」である。ファミリービジネスの経営者は在任期間が長い傾向にあり、超長期の時間軸で事業の発展に取り組むことができる。日本を代表するファミリービジネスの一つとされるサントリーは、ビール事業を実に45年もの歳月をかけて黒字化し、現在では中核事業の一つに成長させている。これは、ファミリービジネスだからこそ可能な超長期の時間軸での経営の強みが表れた事例である。
最後に、「創業精神の承継」である。創業家出身の経営者は、幼少期からファミリー内で企業経営の所作を学ぶ環境にある。具体的には、企業の社会的な役割や、地域社会や取引先、従業員といったステークホルダーとの関わり方など、アントレプレナーシップを自然と身に付けることができる環境で育つ。これは、一般の経営者とは異なる求心力につながっているのではないだろうか。
例えば、10年ごろリコール問題に揺れていたトヨタ自動車の豊田章男社長(当時)は米国公聴会で「私は創業者の孫であり、すべてのトヨタ車に私の名前が付いています。私にとって車が傷つくことは私自身が傷つくことに等しいのです」と発言した。これは、創業家出身の経営者の発言として称賛をもって注目された(注2)。
また、ユニ・チャーム創業家出身で2代目である高原豪久社長は、社長就任後約25年で売上高を5倍にし、25年度に連結売上高1兆円超を見込む。同社は、創業家の邸宅を改築し、宿泊・研修施設「令和共振館」を新設しており、そこで社員が創業者の精神を学び、企業の成長にもつなげる試みを行っている(注3)。