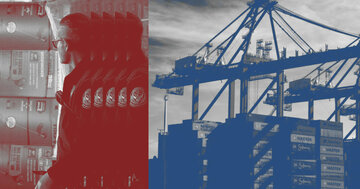Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
「株式市場は今朝早い時間帯に上昇した。その理由は誰も分からず、誰も予測できなかった」
1998年に米誌「ザ・ウイークリー・スタンダード」が掲載したウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の見事な偽物の記事の書き出しはこうだった。だが2025年のここまでの市場動向にもおおむね同様のことが当てはまる。予測できた人は非常に少なく、筋の通った説明ができる人はさらに少ない。
偽の風刺記事はこう続く。「CNBCのアナリストはアフリカ西部セネガルのマネーサプライ(通貨供給量)に関係があると自信満々に主張した。一方で、ペルー沖のマグロ不漁を示す月次漁獲量データの改定値が理由だとの指摘もあった」
「初の全く正直な株式市場の記事」と題するこの偽記事は、投資評論家の特徴を浮き彫りにしている。大抵の場合、理由など本当は存在しない。因果関係を明らかにするには、視野をかなり広げなければならない。
もちろん頭を悩ませる必要がない日もある。大手企業が業績見通しを下方修正したり、前向きな経済リポートが公表されたりして、市場が急落または急騰するときだ。だがそうした場合も、最初は一方向に動くように見えて、突如意外な展開をすることがある。
これを数カ月単位で見ると、さらに不可解さは増す。例えば、2007年と08年には住宅市場が明らかに転落し始めていたにもかかわらず、2桁の上昇率が2カ月程度続くという特筆すべき現象が起きた。
幸いにも評論家がこれらを説明するのは比較的容易だ。懸念材料が多い中で株価が高騰するのはなぜか? 「相場は不安の壁を登るのが好きだから」。企業業績が好調にもかかわらず、方向感が定まらない理由は? 「株価がもみ合い局面に入ったから」
だが今年はアナリストらが苦境に立たされている。親ビジネス的な政策が期待される中、「トランプ・トレード」が勢いづき、米株市場は好調なスタートを切った。その後、トランプ氏が「米国解放の日」に相互関税を発表し、1週間後には弱気相場圏の付近まで急落した。