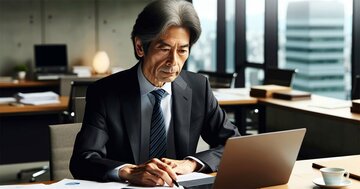「定年=引退」のモデルが崩れ、長期化するキャリアをどう歩むかが会社員の課題となっている。物価の上昇や年金支給額の実質的な目減り傾向も影響し、「定年後も働く」という選択を視野に入れる人は少なくない。
そんな中、「もし働くなら、どんな仕事を選べば収入面での安心につながるのか」を知っておくことは、これからの人生設計における選択肢を広げるヒントにもなる。さまざまな仕事の選択肢のうち、もっとも平均年収が高い職種とは?『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏に聞いた。(構成・聞き手/ダイヤモンド社書籍編集局、杉本透子)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
定年後も“稼げる”仕事No.1は「営業職」
――「定年を迎えたら引退したい」という方がいる一方で、「まだ現役で働きたい」「生活のために働かざるを得ない」という方も少なくありません。定年後に働くとしたら、どのような職種が収入面で有利なのでしょうか?
坂本貴志氏(以下、坂本):年齢を重ねてからの働き方には、さまざまな形があっていいと思います。引退することを選ぶのも、働き続けるのも、それぞれに意味がある選択です。
一方で、総務省の調査では、65歳以上の男性のうち約6割が就業しているという結果が出ています。これは、定年後も働き続けるのが決して特別ではない時代に入っていることを意味しています。実際、70代でも約3~4割の方が働いており、今後さらにその傾向は強まると見られています。
そうしたなかで、「働くなら収入面で安定している職種を選びたい」というのは、自然な関心ですよね。
私が総務省の「就業構造基本調査」をもとに、65歳以上の就業者に絞って職種別に平均年収を算出したところ、最も高かったのは「営業職」で、平均年収は373万円でした(※医師・弁護士などの高度な専門資格が必要な職種を除く)。
この数字はあくまで平均ではありますが、65歳以上で営業職に就いている方の約2割が年収500万円以上を得ているというデータもあります。定年後の仕事としては、トップレベルで高い収入を見込める職種のひとつといえるでしょう。
――なぜ、定年後も稼げるのでしょうか。
坂本:営業という仕事の特徴として、しっかりと利益を出すことが報酬につながる構造が挙げられます。年齢を重ねてもパフォーマンスを出し続けることができる人は報酬も維持しやすいのです。
また、これは働いている会社の報酬制度にもよりますが、固定給に加えて歩合制(インセンティブ)が設定されていたり、契約件数や売上額が収入に反映されたりするケースもあると思います。
年齢にとらわれず成果で評価される
――営業職は、年齢を重ねても成果を出せば評価されるということなんですね。
坂本:そうですね。年齢だけで評価が決まらないという点は、大きな魅力だといえます。
データをみてると、65歳以上で営業職についている人のうち、約3割が正規雇用です。これはほかの職種と比較しても高い割合で、定年制のない企業などで正社員として継続雇用されている方が比較的多いと見られます。
そのぶん労働時間も長い傾向にあり、週あたりの労働時間をみても、短時間勤務よりもフルタイム勤務のほうが主流であり、まさに現役時代の延長線上で働いている方が多いことがわかります。
それなりに体力や意欲が必要ですし、「目に見える成果が求められる」点では、向き不向きもあります。
――精神的・体力的に大変な面もありそうですが、65歳以降も営業職を続けている人は多いのでしょうか?
坂本:65~69歳の就業者数が12.2万人、70~74歳が5.2万人存在していますが、シニアになっても第一線で働き続けている人が主流というわけではありません。
就業者数の推移をみてみると、営業職は50代をピークに徐々に減っていきます。
やはり営業という仕事には、ノルマや達成目標があり、プレッシャーやストレスを感じる場合もありますから、年齢ととも「もう少し穏やかに働きたい」と思う方が増えるのではないでしょうか。
ただ、見方を変えると、続けている方にはそれぞれに「続ける理由」があるとも言えます。「自分の裁量で働ける」「やった分だけ報われる」「お客様とのつながりが生きがいになっている」など、現役時代から築いてきた経験や人間関係が活きている場面が多く見られます。