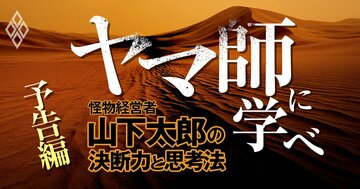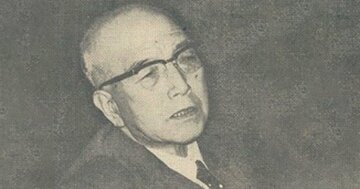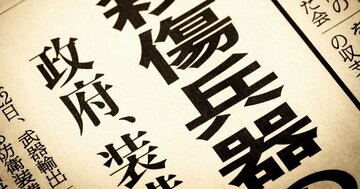Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。戦争を起こさせないために、私たちは何をすべきなのか――。かつて札幌農学校の学生だった太郎は、内村鑑三の「非戦論」に深く共鳴しつつも、それを貫く難しさにも真正面から向き合っていた。その思いは70歳を目前にして再び立ち上がり、中東での石油利権獲得という前代未聞の挑戦につながった。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。
「非戦論」は是か否か
札幌農学校・青年寄宿舎での激論
山下太郎が進学した札幌農学校(現在の北海道大学)は、初代校長のウィリアム・クラークゆかりの開拓者精神とキリスト教精神が息づいていました。特に内村鑑三や新渡戸稲造、宮部金吾といった2期生は、その影響を大きく受けました。
自称クリスチャンの太郎は、札幌農学校で教授となっていた宮部が舎長を務める札幌青年寄宿舎で生活を始めます。
寄宿舎では毎月、「月次会」と呼ばれる集まりがありました。土曜の夜、全員揃って食事をした後、そのまま食堂で会が始まります。舎生が持ち回りで、それぞれ自由なテーマで演説をします。研究発表する者や、時勢を論じる者、学生生活のあり方を提起する者、旅行談を語る者など、話題はさまざまだったそうです。また、二手に分かれて相対するテーマを論じることもありました。
あるとき、内村鑑三の「非戦論」が討論の議題になりました。
内村鑑三は、日露戦争に際して「非戦」を唱え続けたキリスト教徒です。キリスト教の「隣人を愛せ」という倫理的原則に基づき、平和的解決を強く主張しましたが、当時の日本社会、特に保守層や軍部から強い反発を受けました。
日露戦争は、太郎が札幌農学校に入学する前年の1905年に日本の勝利で終わり、世界中を驚かせました。その興奮の中で、内村の非戦論は世論の中でかき消されている向きがありました。この非戦論の是非について、賛成派と反対派に分かれて討論することになったのです。