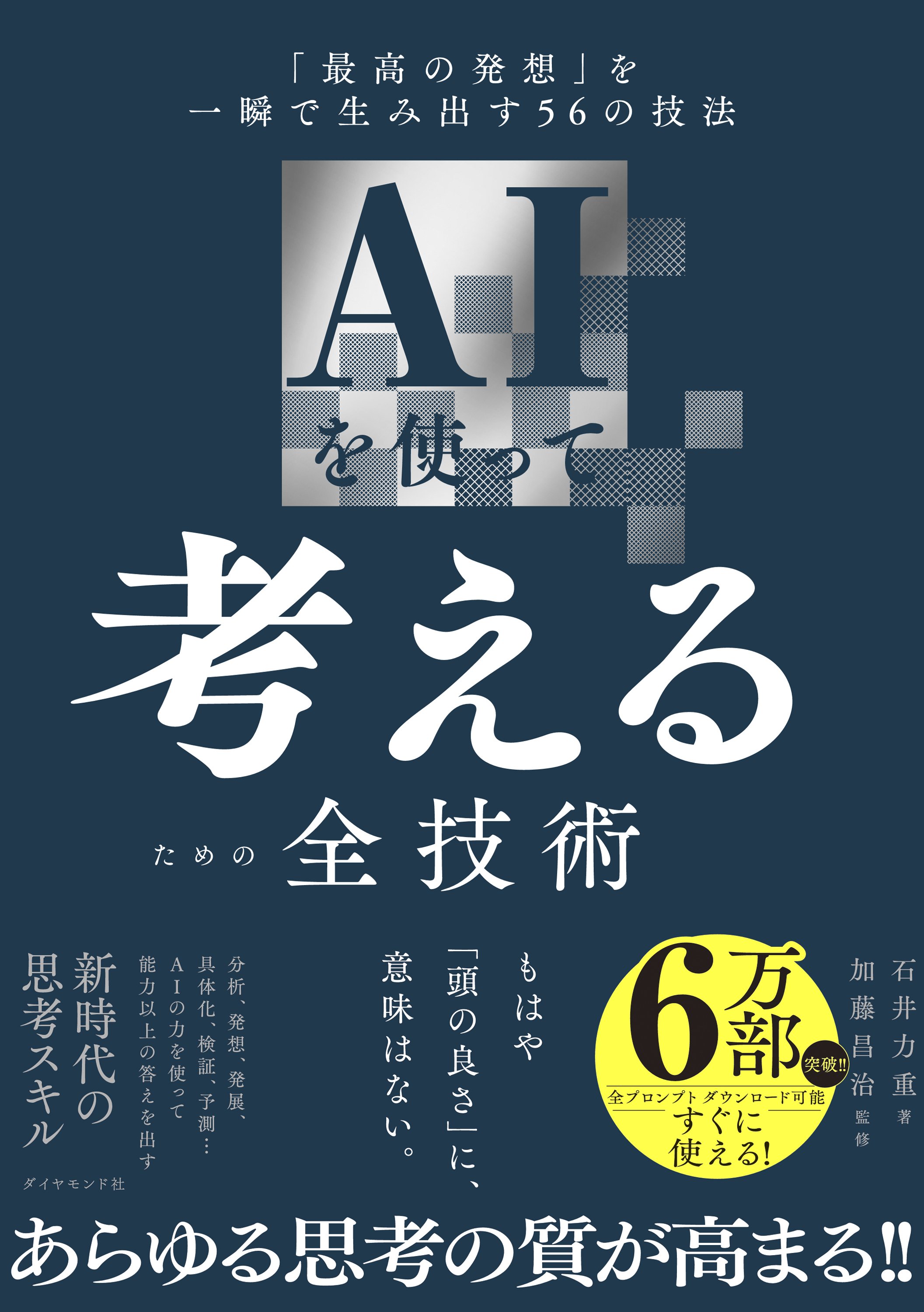顧客が「靴やスニーカー」に関してストレスを感じる要因はいくつかあります。主なものを挙げてみましょう。
・サイズの問題:サイズが合わない靴は、履いていて不快であり、足に損傷を与える可能性もあります。とくにオンラインで購入する場合、正確なサイズを選ぶのが難しいことがあります。
・価格:高品質やブランドのスニーカーはしばしば高価であり、予算によっては手が出しにくいことがあります。
・デザインと選択:流行りのデザインや特定の色がほしい場合、それが見つからないこともストレスの原因になります。
・耐久性と品質:靴の耐久性や品質が低いと、頻繁に新しいものを購入する必要があり、これもストレスになります。
・利便性と入手可能性:特定の靴やスニーカーが地域の店舗で入手困難、あるいはまったく利用できない場合もあります。
これらの要因は、顧客の靴選びの経験を複雑にし、しばしばストレスを引き起こします。
まだどこか表層的な印象がありますね。これではグループインタビューとそこまで変わらない、そう感じたときは「既存ユーザー」の設定を少し具体的にするのがコツです。続けます。
スニーカーを極めてたくさん所有するようなマニアックな人と、1足しか持たないような低頻度のユーザーが〈靴やスニーカー〉に関してストレスを感じる要因は何ですか?
顧客の部分に具体的な情報をプラスしてみました。ユーザーといっても千差万別ですから、あえて極端な2つを示しています。
スニーカーを極めて多く所有するマニアックな人(スニーカーヘッズ)と、逆に1足しか持たない低頻度のユーザーというのは、非常に異なる動機と行動を示します。それぞれについて詳しく見てみましょう。
スニーカーヘッズ(多くのスニーカーを所有する人)
・コレクション:これらの個人はスニーカーを収集することに情熱を注ぎます。彼らは限定版、レアアイテム、特別なデザインやコラボレーションモデルなど、特定のスニーカーを追求します。
・知識と専門性:スニーカーヘッズはしばしば、ブランドの歴史、デザインの変遷、市場価値などに関して豊富な知識を持っています。
・コミュニティとアイデンティティ:多くのスニーカーファンは、オンラインフォーラムやソーシャルメディア、イベントなどでコミュニティを形成します。彼らにとって、スニーカーは自己表現の手段であり、同じ趣味を持つ人々とのつながりを象徴します。
・投資と再販:一部のスニーカーヘッズは、限定品を購入して再販することで利益を得ることもあります。市場での需要と供給のバランスを理解しているため、これが有益な副業になることもあります。
1足しか持たない低頻度のユーザー
・機能性と実用性:これらのユーザーは通常、機能性や実用性を重視します。彼らにとって、スニーカーは日常生活での快適さと機能を提供するためのアイテムです。彼らはスニーカーをファッションアイテムとしてではなく、日常生活での実用的なニーズを満たすために使用します。
・シンプルさと最小主義:1足のみを持つ人々はしばしば、ライフスタイルにおける最小主義やシンプルさを重視します。彼らにとって、多くのアイテムを所有することは無駄や負担に感じられることがあります。
・経済性:コストを節約するために、必要最小限のアイテムしか購入しないこともあります。彼らは、1足のスニーカーですべてのニーズを満たすことを目指します。
・環境への配慮:環境保護やサステナビリティに重点を置く人々は、消費を減らし、持続可能な選択をすることを好むことがあります。これには、洋服や靴の購入を最小限に抑えることも含まれます。
これらの2つのグループは、スニーカーへのアプローチが大きく異なります。スニーカーヘッズは情熱、コレクション、コミュニティに重点を置き、一方で低頻度のユーザーは機能性、経済性、シンプルさを重視します。どちらのグループも、自分たちのニーズや価値観に合わせてスニーカーを選んでいます。
商品・サービスの種類を問わず、エクストリームユーザー(極めて多く使う顧客、反対に極めて使う量が少ない顧客)について聞くと、洞察の鋭い回答をキチンと返してくれます。
コレクションや投資を目的としたスニーカーなどは、周辺のサービスも含めていろいろとアイデアが湧いてきそうですね。
既存品の改良、改善案は、必ずしもすべてのユーザーニーズを網羅している必要はありません。明確な「誰かひとり」のストレスを解決できれば、それは充分に商品の新しい価値だと言えるでしょう。
技法その48「既存品のストレス」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)