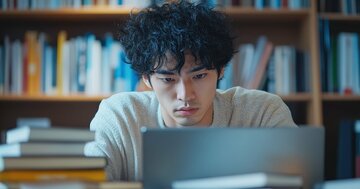AIに「考えてもらう」という姿勢は、ちょっともったいない。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「めちゃくちゃ充実している!」「値段の100倍の価値はある」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIに「考えてもらう」では、いけない
AIをうまく使いこなせれば、問題解決やアイデア発想といった「考える」作業の時間が短縮でき、数多くのヒントを手にできます。実際、本書で紹介する技法を使えば、AIの力によって今までより少ない労力でもっと確度の高いアイデアがいくつも手に入ります。
すると、あなたの思考も自ずと動き出し、前に進めます。
何も思いつかず立ち止まっているだけの「悩む時間」は、あなたの人生から消えるでしょう。
ただ、本書が提案したいのは「AIを使って考える」ことであり、「AIに考えてもらう」ことではありません。
世界を驚かせた「ある実験」
こんな実験が報告されています。
その実験では、19~40歳の人間256人と、3つのAIに、日用品の「本来とは異なる使い方」を多数回答してもらいました。その回答の「クリエイティブ」さを、科学的な分析に加えて、AIの回答が混ざっていると知らない審査員が採点しました。その結果は 2023年9月に雑誌「Scientific Reports」に掲載され、世界を驚かせました。
実験の結果、創造性のテストにおいて、平均点ではAIが人間を上回ったと報告されたのです。
※「Best humans still outperform artificial intelligence in a creative divergent thinking task」(https://www.nature.com/articles/s41598-023-40858-3)
AIを踏み台にして、「人が考える」
ただし、AIが人間を上回ったのは「平均点」でした。ここ、とても重要なポイントです。
同論文では、最高得点を獲得したアイデアは人間によって生み出されたという発見もされています。意外性のあるアイデアを考える作業において、優れた人間は依然としてAIを上回っていると、研究者たちは報告しています。
たしかにAIは、すんなりと「人間の平均点」を超えました。この結果は悲観することではありません。時間も労力もかけずに平均点以上を出せるのですから。その平均点を土台として、「あなた」が最高のアイデアを生み出せばいいんです。
富士登山でたとえるなら、これまで1合目から自力で登っていたのが、AIの力で一気に5合目まで行けるようになったということです。しかもあなたは、一切疲れていない。そこから本領発揮すれば、必ずこれまで以上の到達点にたどり着けるはずです。
人とAIは、それぞれ得意分野が異なります。ゆえに、お互いの強みを活かし、弱みを補い合いながら魅力的なアイデアを共に生み出すことが大切です。その考え方を本書では「人機共想」と称しています。
人と機械(AI)で、共に想う(考える)こと。AIが生成した回答を参照して、人間がさらにアイデアを付加することです。AIを活用することで、人は新たな視点を得たり、可能性を広げたりすることができます。その特性を活かし、うまく活用することで、AIはより多様で豊かなアイデアを生み出すためのパートナーになり得ます。
やがて必須になる「AIを使って考える」スキル
2024年10~11月に全国大学生活協同組合連合会が実施した、1万1590人の大学生を対象とした調査があります。そこでは、50.4%の大学生が「AIを継続的に利用している」と回答しました。つまり今後、社会に出てくる人たちの半数は、すでにAIを使いこなしているということです。もちろん、その「創造性」も存分に活用して。
脅すつもりはありませんが、AIを使って考えることが早晩ビジネスパーソンにとって、いや社会全体にとって必須スキルになることは、避けられない事実だと思います。パーソナルコンピュータが登場した際、発売当時は一部の専門職だけが扱っていましたが、あっという間にPCがないと仕事にならなくなりました。AIも同じくらい、仕事においてなくてはならないものになるでしょう。
けれども恐れることはありません。AIはひとつの道具であり、われわれ人間をサポートしてくれる存在です。人機共想の考え方と、本書の技法を手にしたあなたにとって、AIを使いこなすなんてあっという間。すぐにマスターできるはずですから。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)