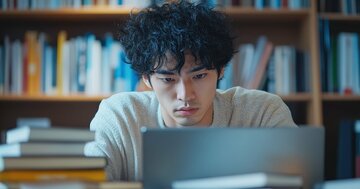AIに「ぜんぶ任せる」という姿勢は、ちょっともったいない。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「こんな使い方、知らなかった!」「値段の100倍の価値はある!」との声が相次ぎ話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの賢い使い方を紹介しよう。
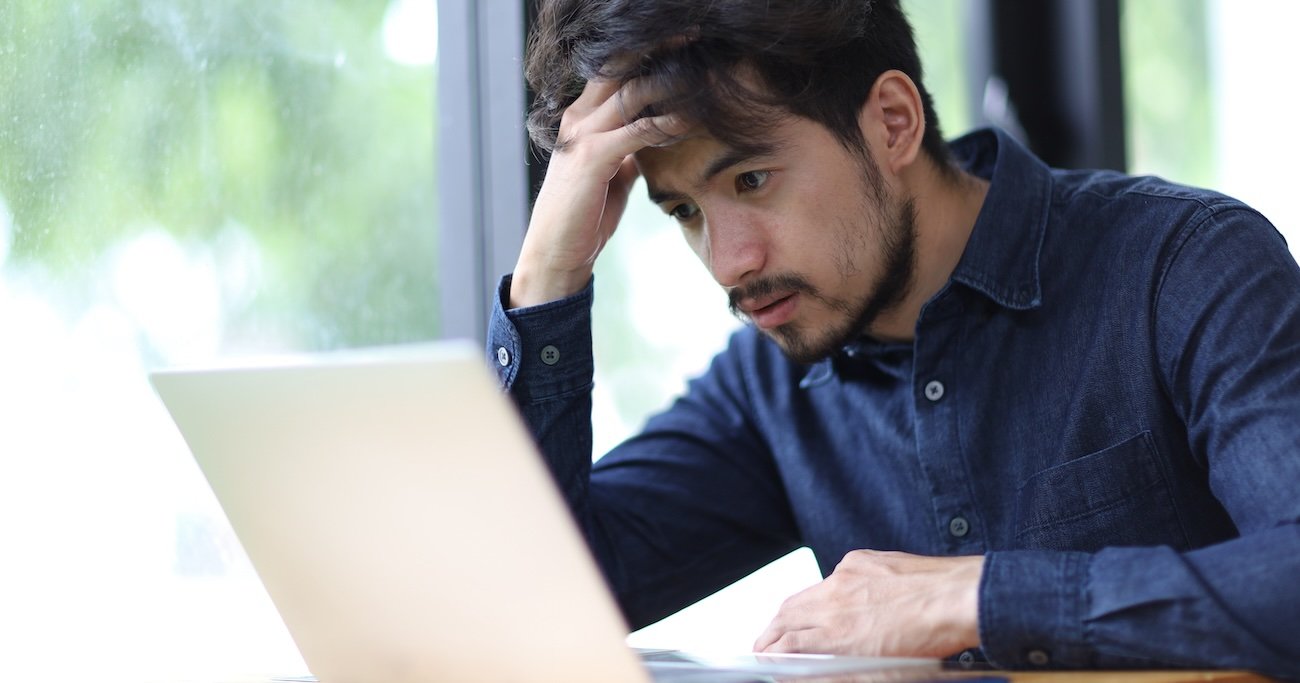 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「使えない」と一蹴するのはもったいない
AIから返ってくる返事には、とんちんかんなものが含まれることもあります。
人間が一度に考えられる量と幅には限界があるけれど、AIには限界が存在しません。よって回答の幅は広くなります。人間を超える幅の広さこそAIに期待する部分ですが、幅が広いがゆえにダメな回答も出てきてしまいます。それは避けようがありません。
大事なのは、それを見た人間側の態度です。
「使える」「使えない」と、一見確からしい有意性で瞬間的に峻別してしまうことは、創造工学の観点からは望ましくない行動です。
なぜならごった煮状態の情報群のシャワーは、アイデアにつながるヒントになるからです。
AIの回答をもとに「連想→想像→創造」を回す
AIが変なアイデアを出してきたなら、「それはそれで面白いじゃん!」「なるほど! じゃあこんなのは……」くらいの気軽さで、さらにアイデアを膨らませてみてください。悪ノリしてしまってかまいません。
ここで動き始めているのは、AIのアイデアや回答を見た人間の頭で生まれつつある「連想→想像→創造」の連鎖です。
これはアイデアを生み出すための基本的な流れです。
最初に「連想」によって物事や概念が結びつき、広がりを持ちます。次に「想像」では、連想で得たことをヒントにして自由な発想が拡がります。そして最後の「創造」で、これまでに想像したヒントがアイデアとして具体化していきます。
優秀な人は「人と機械」で共に考えている
AIが提案したアイデアや情報を土台にして人間が連想し、豊かな想像力を働かせ、最終的に創造的な解決策を考え出す。このやりとり、応酬を、私は「人機共想」と名付けています。
人と機械(AI)で、共に想う(考える)こと。AIが生成した回答を参照して、人間がさらにアイデアを付加することです。
AIを活用することで、人は新たな視点を得たり、可能性を広げたりすることができます。その特性を活かし、うまく活用することで、AIはより多様で豊かなアイデアを生み出すためのパートナーになり得ます。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを活用して思考の質を高める方法を多数紹介しています)