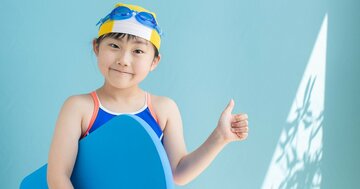お母さんやお父さんが学びに向かっていれば、子どもは「あ、勉強タイムなんだな」と察して、自分の宿題をするようになります。
これは余談ですが、私は子どもたちに本への投資は惜しむな!と伝えてきました。
本だけは、「買おうか迷ったら必ず買いなさい」と伝えていたのです。なぜなら、ネットの情報に比べて、格段に質が高く、子どもの探究心をくすぐるツールだからです。
著者が長年かけて培った経験や知識を、いつでもどこでも手軽に得られます。1冊の本をきっかけに「もっと知りたい!」という好奇心が広がり、新たなテーマへと向かうことも多くあるでしょう。
また、読んでみておもしろくなかった本は、最悪売ることもできますからね。売ったお金をまた次の本を買う資金にあてることができます。
照明を効果的に使うだけで
勉強スイッチはつくれる
わが家では、宿題タイムになると、電気を「スタディモード」に切り替えるようにしていました。
食事をしたり団欒したりするときは、リラックスできる暖色系の色味のライトにする。夕飯後、宿題や勉強をする時間になったら、「スタディモード!」と宣言して寒色系の明るいライトに切り替える。
そうすることで、「宿題をしなさい!」と直接言わなくても、スイッチの切り替えができるようになります。
「もう21時だから寝なさい!」「宿題をする時間でしょ!」と朝から晩まで子どものお世話を続けていると、親もへとへとになってしまいます。
わが家では、ぴったりの時間になると音楽が鳴るメロディ時計を使っていました。
メロディ時計を導入し始めたときは、「あ、21時になったね」など子どもの行動を促す声がけをしましたが、次第に音楽が鳴っただけで、子どもが自ら宿題を始めたり就寝準備をしたりするようになります。
宿題をする時間になったら、「飴いる人?」「ゼリー食べる人?」などと子どもをおびき寄せ(笑)、ちょっとしたお菓子を食べながら宿題をやっていた時期もありました。