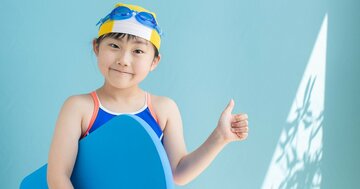毎日のくり返しで
学びを当たり前にする
なぜ、「時期もありました」とお伝えしたかというと、3人兄妹の末っ子になると、長男や長女の様子を見て「この時間は勉強するものだ」と自然に順応し、こういった仕掛けが不要だったからです。
「こういうものだ」というのが一度定着してしまえば、どんどんラクになります。
子どもを追い込んで宿題をさせ続けていると、机に向かって問題を解く勉強だけでなく、探究学習などを含む学ぶこと自体が「やらされるもの」だというイメージがついてしまいます。
大人になっても学び続けていくことは大切なのに、人生の早い段階で学びに対してマイナスイメージを持つことは、どう考えても得策ではありません。
大切なことは子どもが自分で気がついて、学びに向かっていくこと。学びのイメージダウンにならない仕掛けを上手に取り入れていきましょう。
宿題をやるかどうかも
子どもが自分で決めていく
宿題のことで、頭に入れておいてほしいことがもう1つあります。
学校や習いごとの宿題は「親」の宿題ではなく、「子ども」の宿題だということです。「宿題をするか/しないか」「宿題をいつするか」はあくまで子どもの選択です。
今は、「おうちの人が丸つけをしてあげてください」といった宿題が出るケースもあり、そうなると親としてはつい「自分に宿題を課されている」と感じてしまうかもしれません。
しかし、繰り返しますが宿題は子どものもの。親はあくまで、子どもが宿題に取り組むサポートをする存在です。
だから、家庭のルールで「毎日16時に宿題をする」と決めていた場合に、「○○ちゃんと遊びたい」といった予定が入ったら「遊びに行く前にやりなさい!」と親が言うのではなく、どうするかを子どもに考えさせてください。
そして、子どもが「帰ってきたらやる」と言えば、それを尊重します。