社会保障の財源は限られており、医療を必要とするすべてのひとに無料・あるいは安価に提供することはできない。そこで、有限の資源をどのような基準で分配するのが公平なのかが問題になる。
日本は長らく、この「不愉快な問題」を論じるのを避けてきたが、超高齢社会で医療費が膨張し、現役世代の負担が限界に達したことで、「誰が痛みを負うべきか」の議論が避けられなくなった。そのことがよく表われたのが、「高額療養費の見直し」問題だ。
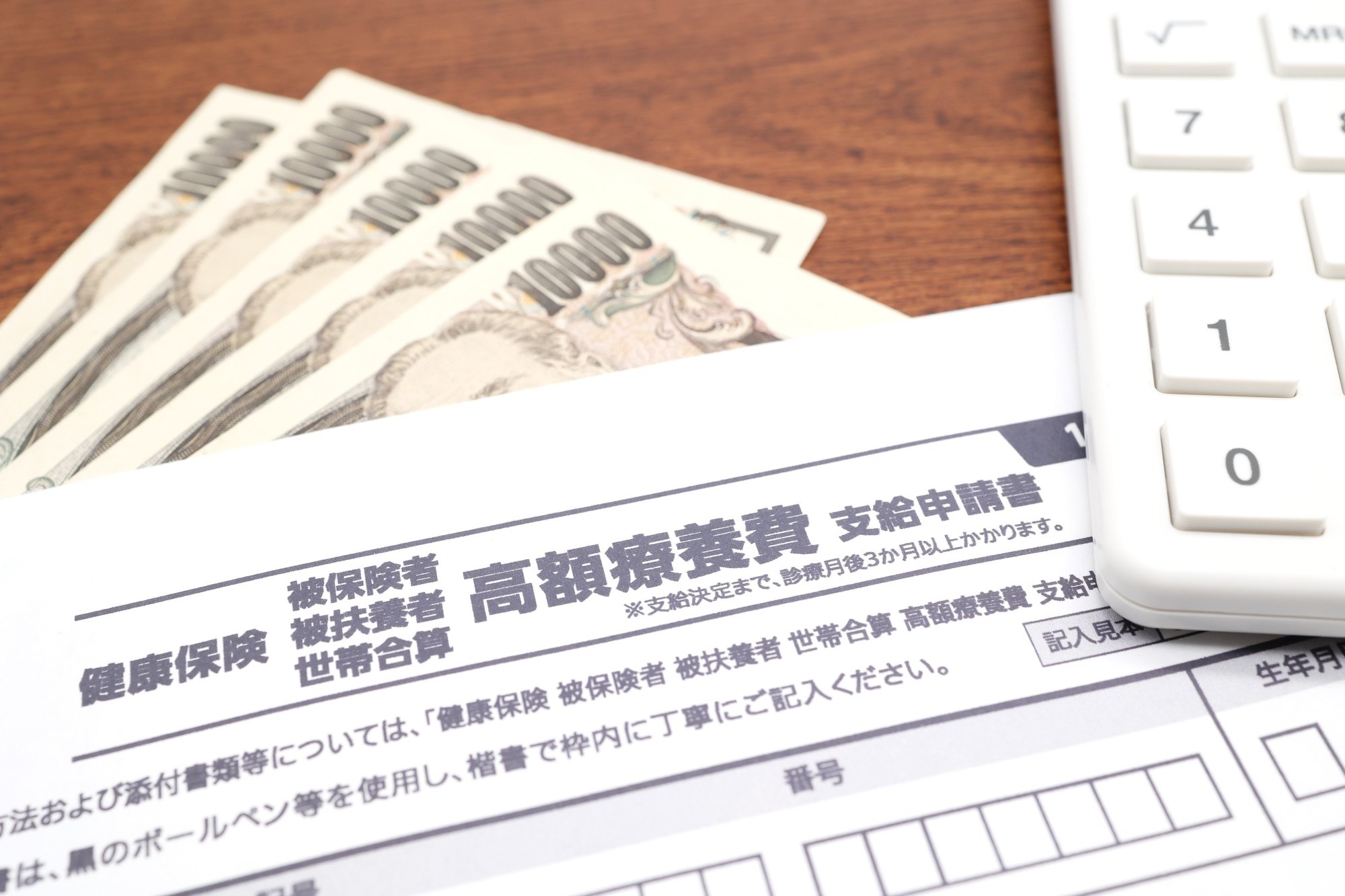 Photo/umaruchan4678 / PIXTA(ピクスタ)
Photo/umaruchan4678 / PIXTA(ピクスタ)
高額療養費制度の見直しは、高齢者の負担増が軽微にとどまる一方、子育てをしながらがんなどで困難な闘病をしている現役世代の家計を直撃することに
2023年12月、岸田文雄内閣は「異次元の少子化対策」を閣議決定し、28年度までに確保する財源3.6兆円のうち、1.1兆円を社会保障の歳出改革で賄うとした。この要請にこたえるために厚生労働省が持ち出したのが、高額療養費制度の見直しだった。
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合、自己負担額に上限を設け、それを超えた分を払い戻すことで、家計への過度な負担を防ぐ仕組みだ。
70歳未満の場合、所得に応じて住民税非課税世帯から標準報酬月額83万円までの五つに区分され、短期と長期の自己負担限度額が決められている。長期の「多数回該当」では、1年間に3カ月以上の高額療養費の支給を受けた場合、4カ月目から自己負担額がさらに軽減される。
年収500万円で1カ月の医療費が300万円のケースでは、3割負担なら患者の負担額は90万円だが、高額療養費制度が適用されて(80,100円+(総医療費-267,000円)×1%)自己負担額は10万7430円に減額される。それが厚労省の見直し案では、25年8月から11万5260円に上がる。長期療養患者の「多数回該当」では、同じケースでは4回目からの自己負担は現行で4万4400円だが、見直し後は4万8900円に増えることになっていた。
ここで押さえておくべきは、他の社会保障制度と同様に、高額療養費制度でも現役世代に比べて高齢者が優遇されていることだ。70歳以上の年金受給者に多い住民税非課税世帯では、医療費が300万円の場合、本来は1割負担で30万円の自己負担だが、高額療養費制度で1万5000円に減額され、見直し後もそれが1万5400円に増えるだけだ。そのうえ70歳以上の外来診療費への特例ルールがあるため、外来での負担上限額は現行の8000円のまま見直し後も変わらない。
厚労省の説明では、前回見直しを行なった約10年前からの平均給与の伸び率が約9.5~12%であることを踏まえ、年収約370万円から770万円の平均的な所得層の引き上げ幅を10%に設定したという。だがその間に給与から天引きされる社会保険料も大幅に上がっているので、名目賃金ではなく(社会保険料を考慮した)手取りの伸び率をベースにしなければ納得は得られないだろう。
さらなる疑問は、高額療養費制度はもともと所得が増えれば負担も増えるように設計されていることだ。インフレによって給与(名目賃金)が増えれば、それに応じて負担上限は上がっていくのだから、上限額を全体的に引き上げる理由にはならない。
見直しによる負担は一見、大きくないように思えるが、これが問題になったのは、現行の制度が所得区分ごとに負担額が決まる階段方式だったのに対し、見直し案では所得に連動して自己負担額の上限が上がるようになったため、患者によっては大幅な負担増になるからだ。
安藤道人立教大学教授によれば、「年収650万~770万円では(高額医療費は)月額約8万円から14万円の73%増、年収1650万円以上では約25万円から44万円の76%増」になる。
大阪医科薬科大学の伊藤ゆり准教授の推計では、改革案の上限額と同水準の負担に直面した場合、ほぼ全ての年収区分で世界保健機関(WHO)が「破滅的医療支出」と定義する水準に達してしまう。この水準は手取り所得から生活費を引いた額に占める自己負担額が40%以上とされている。
さらに東京大学の五十嵐中特任准教授の推計によれば、改革案が実現した場合、負担が上限額に達しないことで高額療養費の対象から外れてしまう人が、70歳未満で約8万人発生する可能性があった(安藤道人「政策哲学から再考を」日経新聞2025年3月27日)。
高額療養費制度の見直しは「異次元の少子化対策」の財源とされるが、高齢者の負担増が軽微にとどまる一方で、子育てをしながらがんなどで困難な闘病をしている現役世代の家計を直撃することになった。患者らの強い反発によって凍結に追い込まれたのは当然といえよう。







