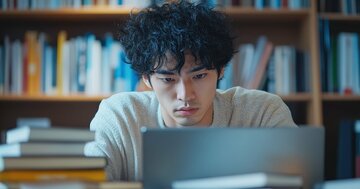AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
アイデアを発展させる手法「プレイズファースト法」
たくさんのアイデアが出揃ったら、そのなかから魅力的に感じるアイデアを選び、磨いていきます。
その際に迷うのが「短所を補う」か「長所を伸ばす」か。特定のアイデアを発展させるとき「ダメ出し」と「良いところへのコメント」のどちらからするべきか。迷いませんか?
じつはこの点、創造工学研究の観点では答えが出ています。それは「先に褒めよ」。「プレイズファースト(先に褒めよ)法」と言います。
「ダメなアイデアなのに、褒める?」。日本企業の職場が一般的に持つ雰囲気だと「そんな生ぬるいこと言える空気じゃないでしょ」と思われるでしょう。
しかし、先にダメ出しをしてしまうと「今はまだ曖昧だけど、磨けば光るかもしれないアイデア」が育ちません。アイデアは未成熟な存在です。大きくなったり小さくなったり、揺れている未成熟なアイデアに先にダメ出しを浴びせると、「削りとろう」という意識が働いてアイデアが細くなりますし、その時点で見捨てられてしまいます。
これは可能性を自ら狭めることであり、やるべきではない行為です。
懸念点の「4倍」、褒める
褒めるとは「アイデアの良いところに光を当てる」ことでもあります。つまり褒めようとすることで、アイデアの持つ潜在的な可能性が末端まで照らし出され、見えてくる。
ゆえに先にプレイズ(称賛)を浴びせると、「あ、そうか。気づかなかったけれど、たしかにこの案はそういう良い側面もあるな」「これはかなり可能性を秘めているぞ」という期待感が生まれます。
もちろん、それぞれのアイデアには改善の余地があるでしょう。まだ完璧なアイデアではないはずです。ただ、そうだとしても、まずは良い点を言うんです。それも、懸念点として指摘したいことの4倍ぐらい良い点を言う。
褒めて褒めて褒めて褒めて。その後で、懸念点の指摘をします。先に褒められた後での改良点指摘ならば、なんとか頑張って改良しようとするのが人間の心理ですから。
AIがどんなアイデアも褒めてくれる技法「着想の良いところ」
「褒める」のが苦手な人もいるでしょう。照れるというか恥ずかしいというか。自分のプライドが邪魔してしまうときもあります。それに、どれだけ考えても「良いところ」が発見できないアイデアも、ときにはあるでしょう。
ならば、プレイズファースト法をAIで実践する技法「着想の良いところ」を使ってみてください。
こちらが、そのプロンプトです。
アイデアを言うので、そのアイデアの良いところを4つ、発展のために考慮すべきことを1つ、コメントしてください。
〈アイデアの候補を記入〉
場に出ているアイデアをAIに入力し、「良いところ」を4つ、改善点を1つだけ出してもらいます(4倍褒めてもらいます)。そのアイデアが持つ潜在的な可能性が描き出されるだけでなく、改良のヒントも手に入り、アイデアをさらに発展させることもできます。
大抵のアイデアには改良改善の余地があるので、どんなアイデアに使っていただいてもかまいません。とくにおすすめなのは、有望視しているアイデアに対して使うこと。人間同士のブレインストーミングでも、可能性があるアイデアには追加案や改善案がどんどん出てきます。その構造はAIでも同じです。
なお、カジュアルなテイストでの出力を促すため、あえてプロンプトでは「アイデアを言うので」「コメントして」と、表現を意図的にカジュアルにしています。
技法「着想の良いところ」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って“思考の質”を高める方法を多数紹介しています)