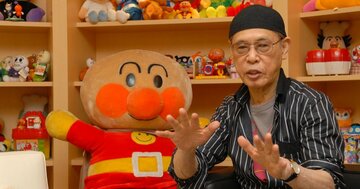写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
noteの記事をきっかけに注目を集め、新進気鋭の文筆家として活躍する伊藤亜和氏。セネガル人の父と日本人の母との間に生まれた彼女は、「頭の良い人」に憧れる一方で、「地頭が良い人」という表現にはどうも嫌悪感を感じるのだとか。伊藤氏の独自の感性を通して、「頭が良い」という表現への解像度を上げてみよう。※本稿は、伊藤亜和『わたしの言ってること、わかりますか。』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
「頭の良い人」が
好きな理由
私は「頭の良い人」が好きだ。「頭が良い人」の定義について、最近の世の中、とくに私が活動拠点としているSNSでは、さまざまな議論が飛び交っている場面をよく見かける。
今流行っているのは「地頭」というやつだ。勉強ができるうんぬんではなく、あらゆる場面に適した立ち回りや、筋道を立ててなにかを論ずるということが、とくに訓練したわけでもなくできる人のこと。「地頭」という言葉の便利な点は、それを評価する際にこれといった資格や証明のようなものが必要ないことだ。
人が誰かを「地頭が良い人」と評価するとき、その根拠はそれを評価した個人の感性に大概ゆだねられていて、誰かが誰かを「地頭が良い」と評価したとき、それを証明する確固たる事実はほとんどない。それゆえ、それを否定する余地も残されてはおらず「地頭が良い」と誰かが言ってしまえば、周囲の人も「あの人は地頭が良いのか」と、なんとなく評価することになる。
だから「地頭が良い」というのは、結構言ったもん勝ちで、言われたもん勝ちなのではないかと私は思う。似たような言葉に「頭の回転がはやい」なんていうのもあるが、最近ではこの辺りが「本当に頭が良い人」というくくりで圧倒的な支持を獲得しているように見える。