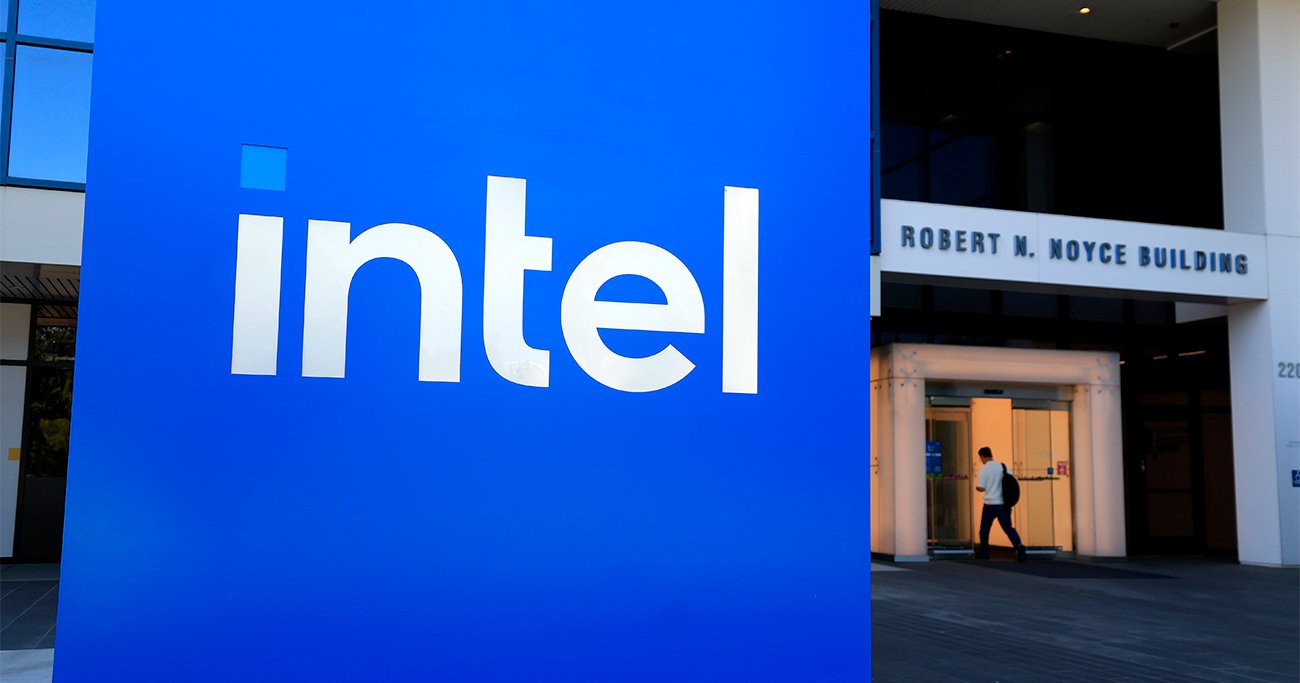 Photo:Justin Sullivan/gettyimages
Photo:Justin Sullivan/gettyimages
リップブー・タン氏(65)は、人生で最も重要な会談に向けて不安を抱えながら準備を進めていた。
米半導体大手インテルの最高経営責任者(CEO)に就任してわずか5カ月のタン氏は、既に自身の職を守るための戦いを強いられていた。その数日前、ドナルド・トランプ米大統領は、中国人民解放軍との過去のつながりを理由にタン氏の辞任を要求していた。
インテルの経営陣はパニックに陥った。直ちにホワイトハウスに会談を申し入れ、タン氏はワシントンに向かった。同氏は10日、数時間にわたりアドバイザーらと協議した。事情に詳しい複数の関係者によると、アドバイザーらは、トランプ氏が「CEOとの会談を好む」ため、公に非難した相手であっても話を聞いてくれるはずだとタン氏を安心させた。
翌日、タン氏は大統領執務室でトランプ氏、ハワード・ラトニック商務長官、スコット・ベッセント財務長官と会談した。自身が中国のスパイではないこと、また現代経済を支えるコンピューターチップの国産メーカーとして数少ない存在であるインテルの強化が米政府にとって長期的な利益になることを、大統領に納得させようとした。
タン氏の主張は説得力があった。トランプ氏はまた、マレーシア生まれ、シンガポール育ちの米国市民で、かつてプロバスケットボール選手を目指したこともあるタン氏に好感を持った。そしてCEOの解任要求を取り下げた。
しかし、この「停戦」には代償が伴った。トランプ氏の支持と引き換えに、政権はインテルへの出資を提案した。2022年のCHIPS法の一環としてインテルに約束していた90億ドル(約1兆3200億円)近くの補助金を同社株式の10%に転換することを決めた。この異例の取り決めにより、政府はインテルの筆頭株主となる。
インテルはかつて米国で最も尊敬されるテクノロジー企業の一つだったが、もう何年も下降スパイラルに陥っている。この会談は、混乱のさなかにある同社にとって転換点となった。タン氏の辞任を求めるトランプ氏の要求(これはフォックス・ビジネス・ネットワークの番組がきっかけとなった)による悪影響を抑えようとする同社の慌ただしい対応は、トランプ政権下で大手企業が直面する予測不可能な環境を浮き彫りにしている。
2週間のジェットコースターのような展開の末、タン氏の職は安泰となり、インテルを巡る状況も安定化した。ソフトバンクグループ(SBG)は、トランプ氏の歓心を買おうとインテルに20億ドルを出資することで合意した。インテルとホワイトハウスは22日に正式に取引条件を明らかにした。







