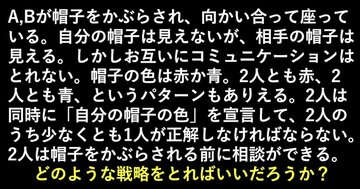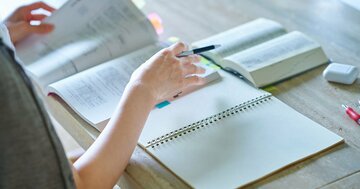このような学校選びのためのデータは、前回もお伝えした「受験軸」に沿った受験校を選ぶ際に、我が家の「軸」にぴったりの学校を見つけるのに役立ちます。
 中曽根陽子(なかそね・ようこ)
中曽根陽子(なかそね・ようこ)数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリスト/マザークエスト代表 小学館を出産で退職後、女性のネットワークを活かした、編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに、数多くの書籍をプロデュース。教育ジャーナリストとして、紙媒体からWEB連載まで幅広く執筆する傍ら、海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエイティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。最新刊『<中学受験>親子で勝ちとる最高の合格』(青春出版社)他著書多数。
わが子の中高生生活をイメージする学校研究の方法は?
図1「学校特色分析グラフ」は、学校の特色を7つの視点で数値化しています。すべての受験校がそれぞれのご家庭で理想とする「受験軸」の指標をすべてカバーしているなどということはありません。だからこそ「ここは譲れない」「これがカバーされているなら大丈夫」と思える指標を見つけることで、すべての受験校を「入学できたらうれしい学校」に捉えなおすことが可能になるのです。
図2「学校傾向分析シート」は、入学後の学生生活をより細かくイメージするのに役立ちます。教育内容ひとつとっても、横軸にあるように宿題が多く、授業に遅れないように手厚いサポートがある学校なのか、それとも生徒の自主性を重視しているのかによって、入学後の生活は大きく変わります。また縦軸の「探究」をはじめとしたいわゆるプログレッシブ教育を重視しているのか、それとも大学進学を重視して受験科目の履修の比重を大きくしているかによっても、日々の授業内容は異なるでしょう。
子どもにどのような6年間を過ごしてほしいのか、その結果何を学びとして得てほしいのか、各家庭の「受験軸」によって判断が分かれるところです。
子どもの直感をどう受け止める? 毎日楽しく通える学校はどこか
入学後の友達や先生との関係については縁もありますが、あらかじめ学校を研究しておけば防げる「齟齬(そご)」もたくさんあります。
校長先生の話や教育理念を聞いて共感できるか、在校生の様子を見て、その中にわが子がいる姿をイメージできるか、子どもが何かしらの居心地の悪さを感じていないか。一度足を運ぶだけでもわかることはたくさんあるでしょう。
学校説明会の日程は限られていますので、都合がつかない場合は、個別で学校訪問を受け入れているところもあります。少なくともわが子が受験する学校には、かならず一度は親子で足を運んでみてください。
ご家庭の「受験軸」にあてはまる部分はどこなのか、特に気になるポイント、大事にしたい軸に関わる事柄については、個別相談などを利用して訪問したすべての学校で同じ質問をぶつけてみてください。対応の違いを比較すれば、より詳しく学校ごとの特色が分かるようになります。