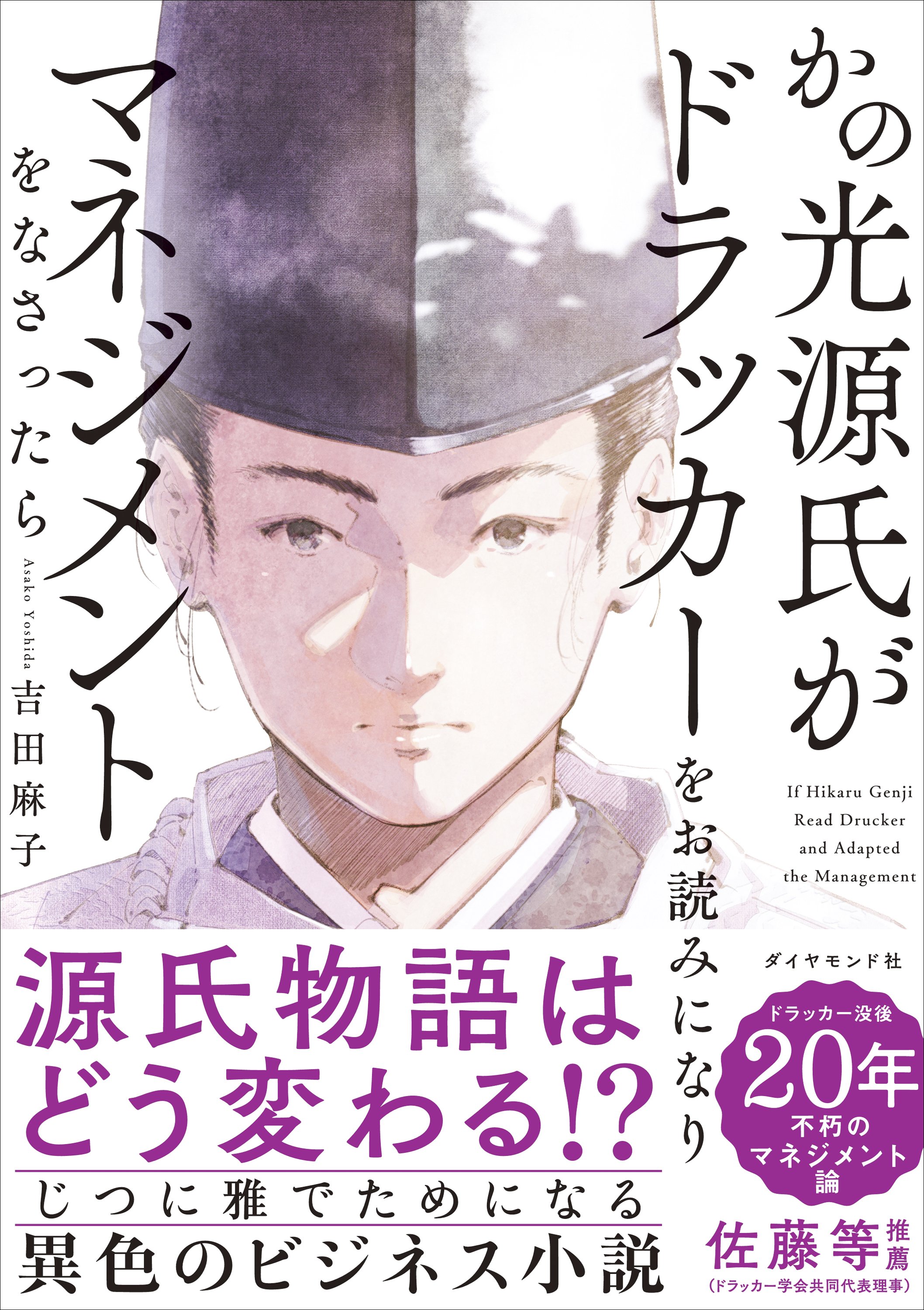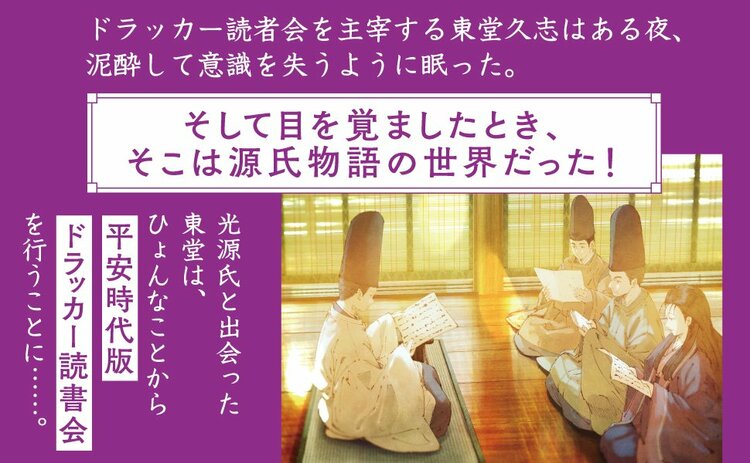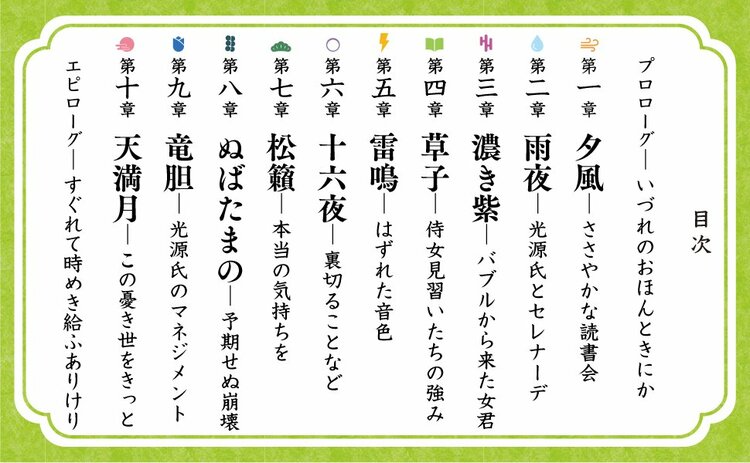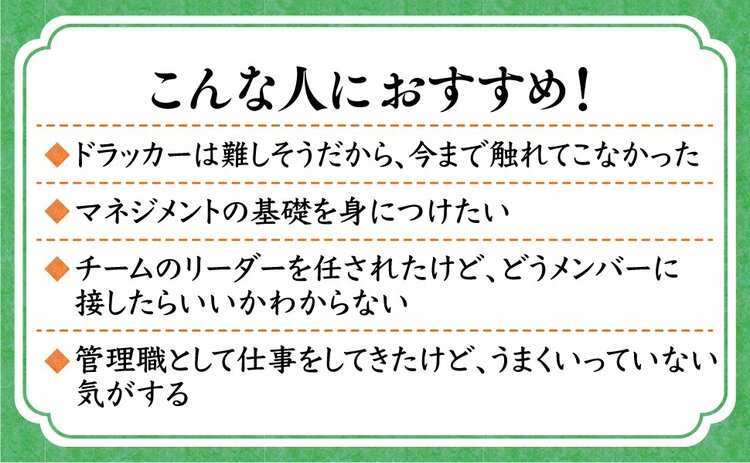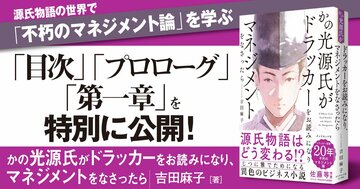「会議が多い」の目安
ドラッカーは同じ章の中でこう言っています。
「時間の四分の一以上が会議に費やされているならば、組織構造に欠陥があると見ていい」
一日につき、2時間程度の会議に出席している方にとっては耳の痛い指摘なのではないでしょうか。
複数の人が働く場面において会議はどうしても必要であると考えるケースも多いと思います。いきなり会議をゼロにすることが難しい場合も多いでしょう。
すでに実施している会議をよりよいものにするところから始めるのも手です。
「会議の成果をあげる」ということについて、同じ『経営者の条件』の『第三章 どのような貢献ができるか』という章で言及されていますので見ていきましょう。
この章では、組織に属する一人ひとりが組織の成果に貢献するということについて書かれています。
「貢献に焦点を合わせることによって、自らの狭い専門やスキルや部門ではなく、組織全体の成果に注意を向けるようになる。成果が存在する唯一の場所である外の世界に注意を向ける」
手元の仕事から顔をあげて目標に目を向ける。自分の仕事は外の世界における成果につながってしかるべきであり、今やっている仕事は「処理」ではなく「成果という組織みんなで目指しているものへの前進」であるという考え方が述べられています。
この貢献の章に「会議の成果をあげる」という節があります。
ここでは会議という道具を互いの貢献のために使うために、大切なポイントが述べられています。
それは、
「成果をあげるには、会議や報告書やプレゼンテーションから何を得るべきかを知り、『何を目的とすべきかを知らなければならない』」
ということです。
会議を成果あるものにするために、具体的には、
◻︎会議の冒頭に、会議の目的と果たすべき貢献を明らかにしなければならない
◻︎会議をその目的に沿って進めなければならない
◻︎勝手に意見をいい合う懇談の場としてはならない
◻︎誰かのプレゼンテーションの場にさせてはならない
◻︎出席者の全員を刺激し、全員を挑戦させるものにしなければならない
◻︎会議の終わりには、冒頭の説明にお戻り、結論を会議開催の意図と関連づけなければならない
というように詳述されています。
「結局今日の会議って何だったんだろう」
「ダラダラしてよくわからなかった」
そのような印象のある会議は、目的を明らかにすることでぐっと変化しそうですね。
ここでは
「最も重要な原則は、会議の冒頭から貢献に焦点を合わせることである」
ともあります。
参加者が貢献を意識することで会議がより生産的なものになっていくはずです。
ドラッカーは同書の『序章 成果をあげるには』の中でも「会議の生産性をあげる」ことに言及しており、そこにはこのような言葉があります。
「会議の生産性をあげるにはかなりの自制を必要とする。会議の目的を決めそれを守らなければならない。目的を達したときには直ちに閉会する。別の問題をもち出してはならない。総括したら閉会する」
とてもストイックな手法に感じるかもしれませんが、どれか一つでも実践してみると新しい変化が訪れるかもしれません。
「人は、仕事をするか、会議に出るかである」
よりよい仕事をするために、会議という道具をよりよいものにしていきましょう。
明日の会議は、どんな工夫ができそうですか?