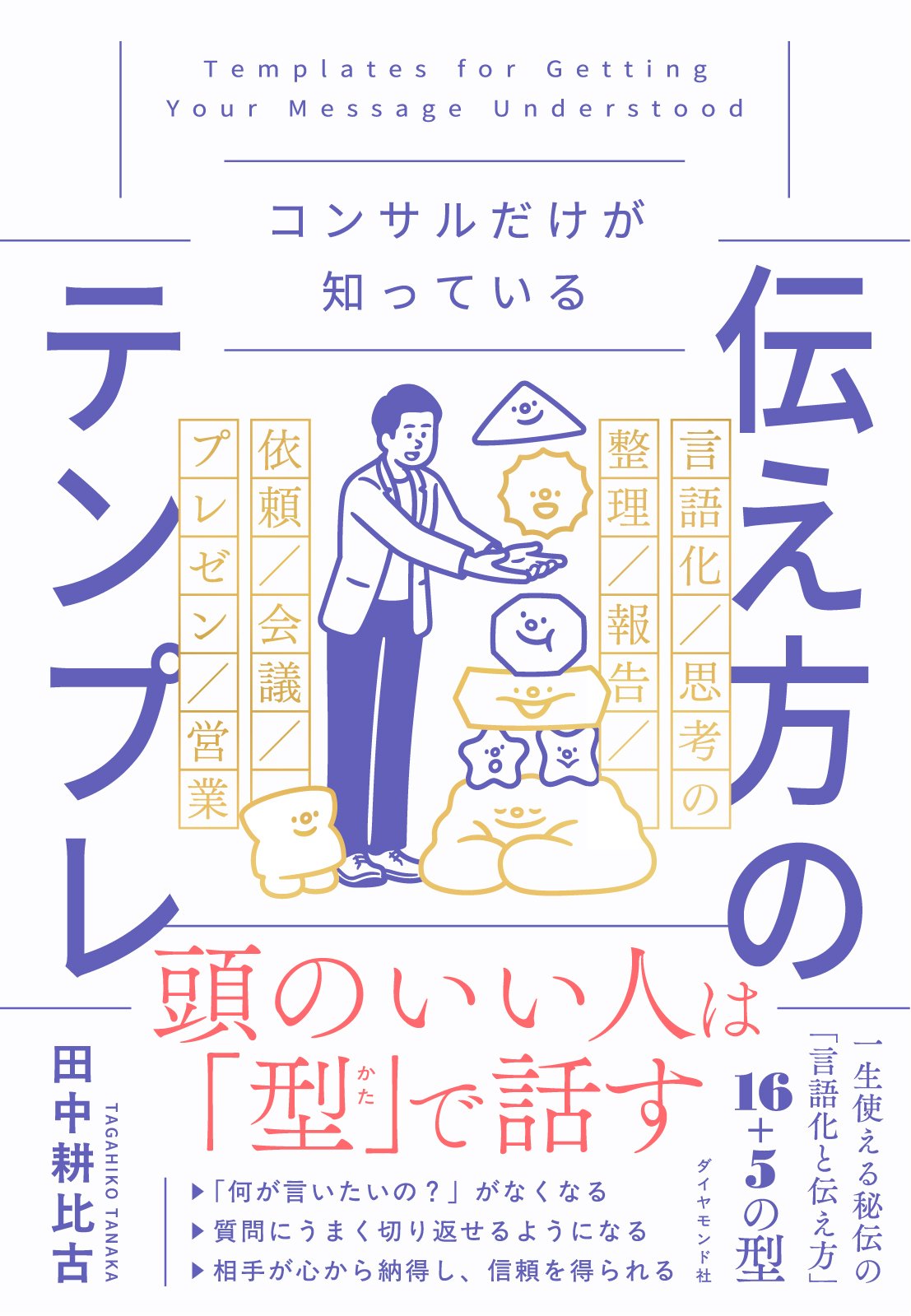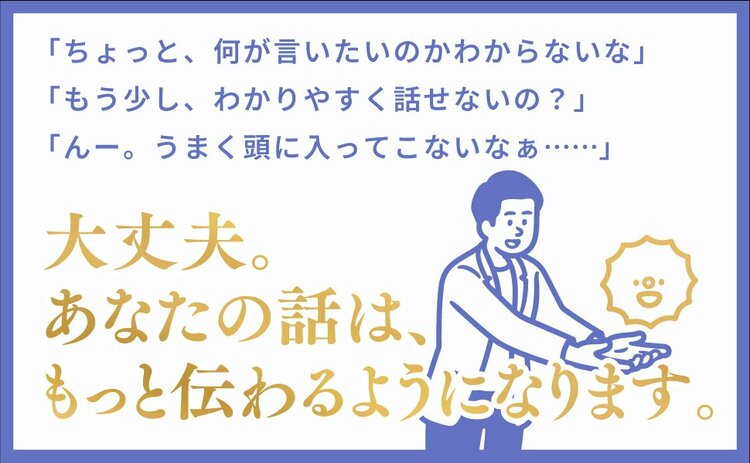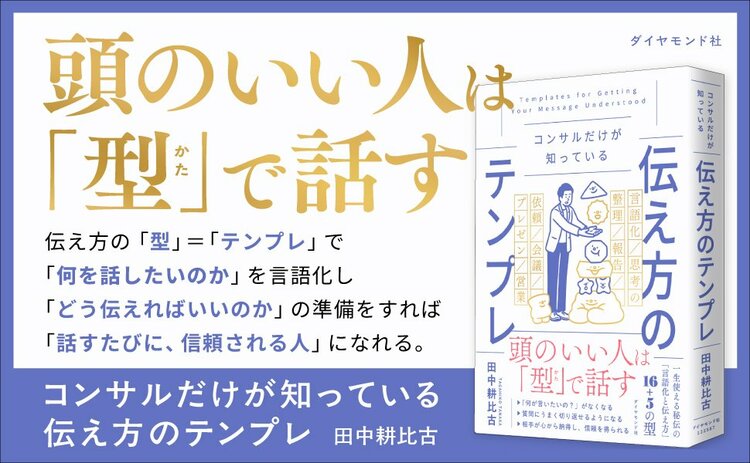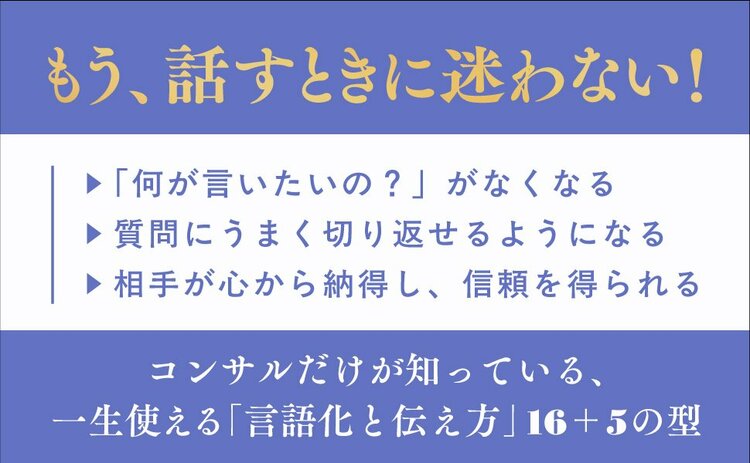「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
話す前に頭の中で情報を整理する
世の中には、伝えるのがうまい人がいます。
そういう人たちの中には、頭の回転が速くて、情報を素早く処理するタイプの人もいるでしょう。
即興で、スマートに話す人たちです。とてもうらやましく感じますね。
しかし、伝えるのがうまい人、話すのがうまい人が、みな「即興が得意」とは限りません。
むしろ、大多数は「その場で対応するのが苦手」だったり、「急に言われても困る」と感じていたりします。多くの人は、話す前に、頭の中で情報を整えているからです。
結婚式や会社の懇親会などで「挨拶のスピーチ」を頼まれたとします。
当たり前ですが、普通は、しっかりと準備をして臨みます。
文章として書いて、声に出して読んでみて、おかしなところがないか推敲します。
場合によっては、原稿やメモを持って、それを見ながら話すこともあるでしょう。
何かをしっかり伝える、話す、というときには、しっかり準備をするものなのです。
頭の中に浮かんだこと、思いつきを、そのまま口に出すわけじゃありません。
どういうことを伝えるか、どの順番で話すのか、最後のオチはどういうふうにするのか。
あらかじめ、伝えたい内容を洗い出して、その要点を整理する。
伝える順番を組み立てて、相手の理解が進む速度に合わせて情報をどう渡すのかを調整する。
聞いている方からすると、そつなくこなしているようでも、こうした「見えない準備」に時間と労力を割いている人が大半なのです。
優雅に泳ぐ白鳥が、水面下ではバタ足をしているという話と似ていますね。
日常会話においても、同じことが言えます。
パッと思いついたことを好きなように話すのは、もちろん悪いことではありません。
みんなで楽しく会話して、盛り上がる際に、いちいち準備をする必要はないでしょう。
しかしながら、何かお願いごとがあるとか、伝えた情報を記憶に残しておいてほしいとか、コミュニケーション上の「目的」がある場合には、伝え方を工夫するための準備を行うべきです。
ちなみに、目的といっても、いつもカッチリした真面目なものであるとは限りません。
目の前の人を笑わせたいとか、その場を盛り上げたい場合にも、伝え方に少し工夫をすると思います。
相手に伝えたい内容を、うまく伝えて、こちらの思ったとおりの感情・気持ちになってもらう。そのために、準備をするわけです。
考えていることを整理してから話す
準備といっても、長いスピーチ原稿を書くような労力をかける必要はありません。
また、プレゼン資料を完璧につくり込むような重たい作業でもありません。
必要なのは、自分の考えを整理して、まとめる。ただそれだけです。
自分が考えていることを言葉で整理して、「どんな順番で」「どれくらいの深さで」「どれくらいの細かさ(粒度)で」伝えるのかを、話し始める前に設計する。
それが伝える前の準備です。
例えば
「最初に、結論を伝えよう」
「この話題に触れるのは久しぶりだから、前の記憶を思い出してもらってから、本題に入ろう」
「かなり込み入った話だから、最初に『複雑な話なので、しばらく我慢して聞いていてください』とお願いしてから話し始めよう」
「『今日は三つのポイントをお話しします』と切り出そう」
など、あらかじめ方針を決めて話し始めるだけでも、聞き手が受ける印象は大きく変わります。
「三つのポイントで話します」、と言われれば、相手は一つめのポイントについて聞きながら「あと二つあるんだな」と思ってくれます。
「複雑な話だから」と言われれば、相手は「ちゃんと聞いて理解しよう」とか、「少し話が長くなりそうだな」と、頭の状態を「深く考えるモード」にセットします。
相手の頭の中を「伝わる状態」に切り替える
このように、相手の頭の中、脳内のモードを切り替えてもらうと、うまく伝わるようになります。
例えば、お笑い芸人さんも、いきなりお客さんを笑わせるのは難しいと思うんです。
彼らも、ちゃんと「あたためる」というステップを踏みます。
漫才で言えば「つかみ」、落語で言えば「まくら」ですね。
お笑いの舞台やテレビ番組を収録する際の「前説」などもそうでしょう。
お客さんに、笑う準備を整えてもらう、つまり、笑うモードに脳内を調整してもらうわけです。そこから、本題のネタに入ります。
こうしたお笑いのテクニックは、かなり洗練された「型」として、長年かけてつくりあげられています。
芸人さんたちは「型」を理解し、それを自分たちなりに解釈して、手を加えています。
物事を説明する際も、これと同じように、相手の脳内を「伝わる状態」にするのがポイントです。
そして、お笑いと同様に、伝わる状態をつくるにも「型」があります。
この「型」を知り、理解し、実践することに、センスや特別な能力は必要ありません。
私がコンサルタントとして新人教育、若手育成をしていると、その人の実力以上、あるいは、その人が持っている知識以上に「うまい伝え方」をしてくる人がいて、驚かされます。
そういう人たちは、話す前に「話の構造」を考えています。
これは決して、言葉を操るセンスの話ではなく、話す前に構造を描く習慣があるかどうかの違いです。
そして、まさにこれが、「伝わりやすさ」を大きく左右するポイントなのです。
伝え方を磨きたい。うまく伝えられるようになりたい。
そのためには、話し方の勉強をするよりも、「話す前に情報を整える時間を取る」ほうが近道です。
そして、その「話す前の準備」を「型」として理解し、身につけると良いでしょう。
話し始める前の準備の時間。そこに、伝わるかどうかの鍵があると私は思います。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)