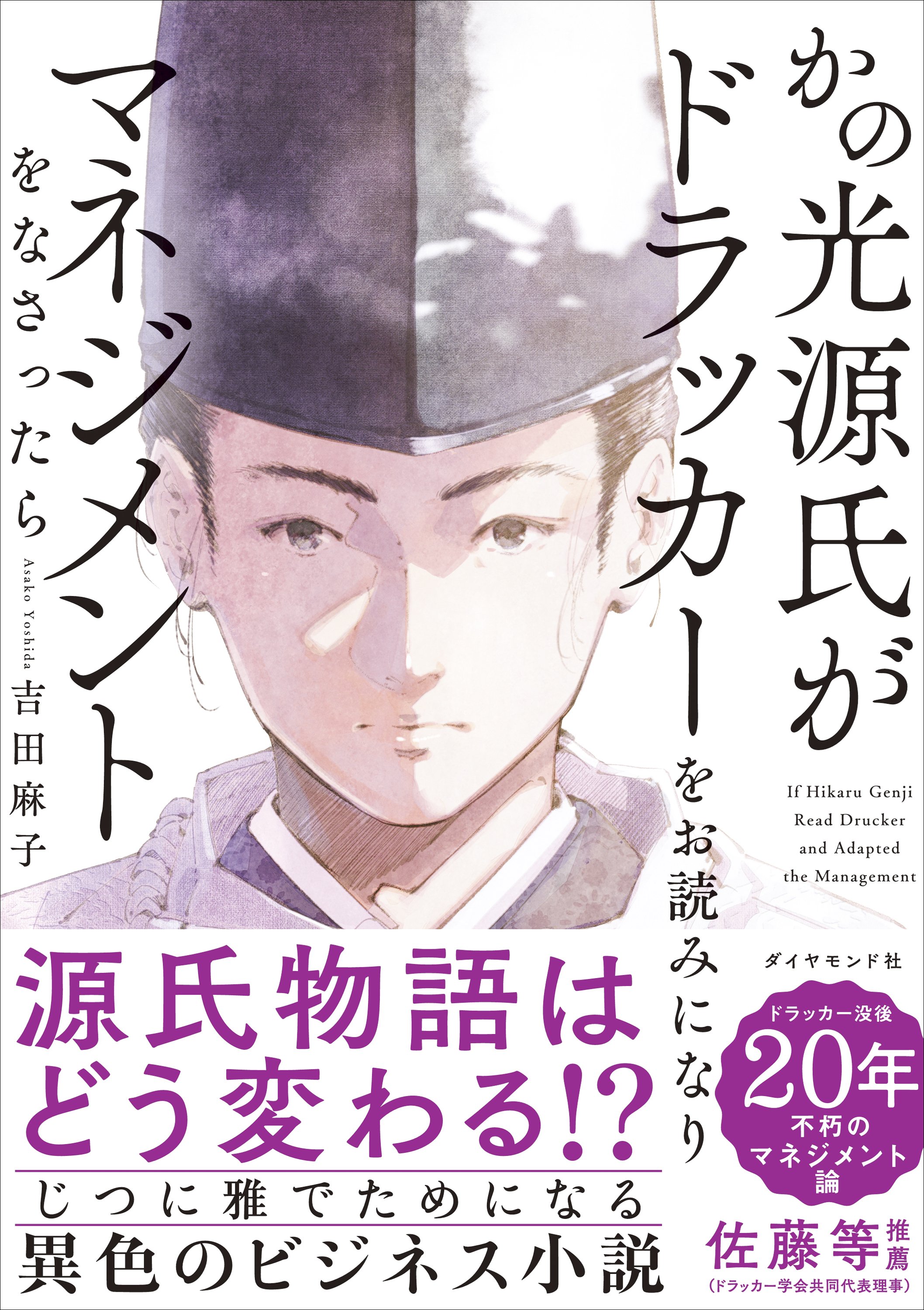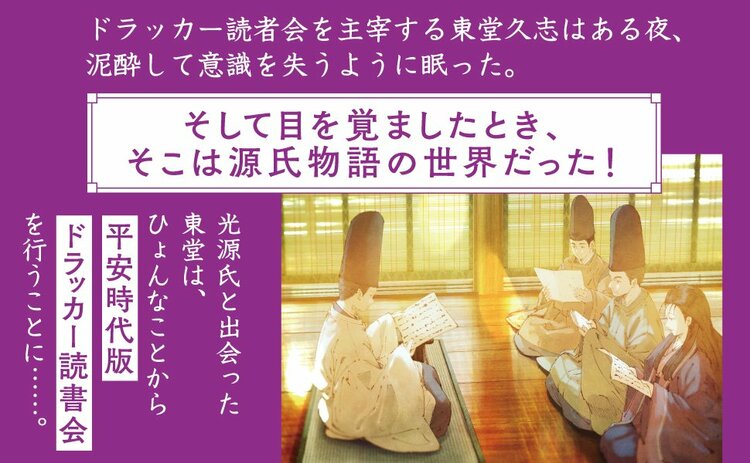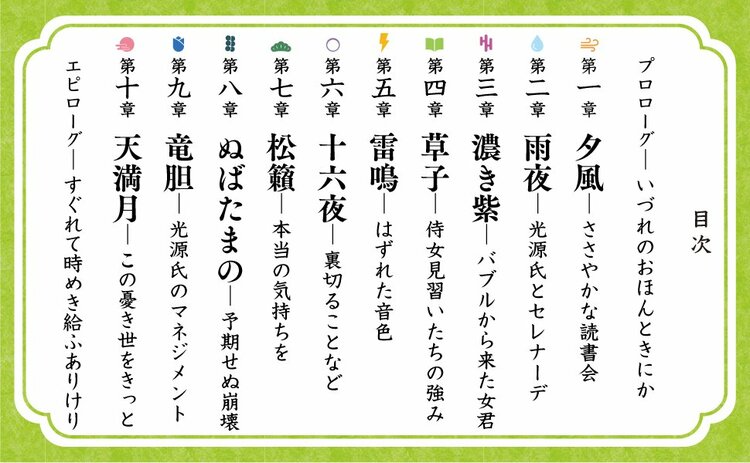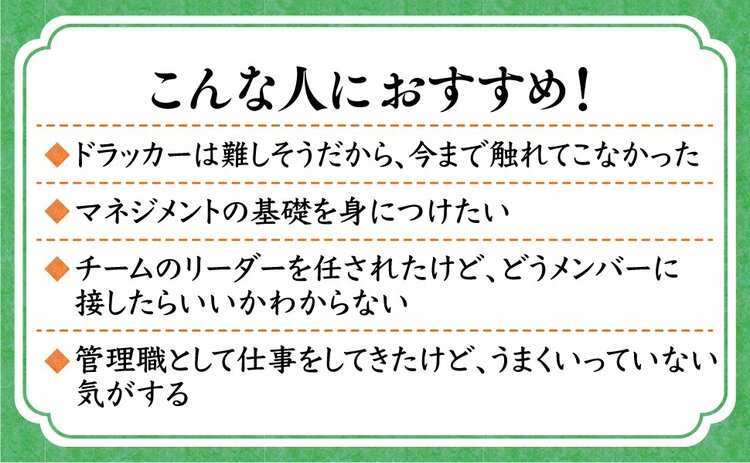知識労働の生産性を向上させる6つの条件
ドラッカーは『明日を支配するもの』の『第5章 知識労働の生産性が社会を変える』の中で、知識労働の生産性向上のための6つの条件を述べていますので、紹介していきましょう。
知識労働の生産性を向上させる6つの条件
(1)仕事の目的を考える
肉体労働では重要なことは仕事の方法です。
例えば時間内にいくつのものを作る、といった明確な目的があり、そのために手順などのプロセスがあります。
ところが知識労働においては「仕事は何か」ということが中心的な課題となります。教師や看護師が本来行うことは何か、など仕事を定義し、それに集中することが求められます。
(2)働く者自身が生産性向上の責任を負う
仕事が何かが明らかになれば、組織の成果に貢献することについての責任をもつことができます。仕事の質や量、時間やコストについて具体的にどれくらいやればよいのかを考えることができます。
(3)継続してイノベーションを行う
組織の成果のために何をなすべきかが明確になれば、それを行うにあたり、体系的廃棄を行い、変化を機会と見る姿勢をもち、なすべきことに向けて継続的イノベーションを行っていくことができます。
(4)自ら継続して学び、人に教える
昔学んだことは古くなります。情報や能力のアップデートをし続けることが必要です。
また、ドラッカーは『マネジメント(中)』の『第33章 マネジメント教育』で、「人に教えることほど自らの勉強になることはないのと同様、人の自己啓発を助けることほど自らの自己啓発に役立つことはない」といっています。
(5)知識労働の生産性は、量よりも質の問題であることを理解する
ドラッカーはこの6つの条件に続く文章の中で、「仕事の定義の仕方そのものが、知識労働の質の定義や生産性向上の方法を大きく変える」といっています。
自分にとってこの仕事の目的は何であり、どのようなことによって組織の成果に貢献ができるか。そしてそのことをなすということに責任をもっているのか。これによって質の方向性が異なります。
(6)知識労働者は組織にとってのコストではなく資本財であることを理解する
経済学や現実の企業経営では肉体労働者をコストとして扱うのに対し、知識労働者を生産的な存在とするためには資本財として扱わなければならないとドラッカーはいいます。
組織にとっては、知識を頭の中に保有しており、しかも流動性のある知識労働者という人財をいかに引きつけておくには何が必要かを考えることもまた求められています。
生産性を上げる第一歩は「シンプルな問い」から
白井課長は頭の中が整理でき、すっきりした気持ちになった。
「そうか、彼らの生産性を高めるにはこれらについての認識を共有すればいいんだ」
さっそく、同章に書かれている問いを見つけ、それを手帳にメモした。
「行うべき仕事は何か」
「何でなければならないのか」
「何を期待されているか」
「仕事をするうえで邪魔なことは何か」
生産性を高めるとは、単に効率を上げることではありません。
真に成果につながる仕事に集中することです。
知識労働者の時代にあって、マネジメントの役割は「成果を生み出す仕組み」を設計し続けることにあるといえます。
そのためには、部下一人ひとりの強みを引き出し、不要なノイズを取り除き、集中できる環境を整えることが欠かせません。
生産性向上の第一歩は、壮大な改革からではなく、シンプルな問いから始まります。
――「行うべき仕事は何か」。
この問いを繰り返し投げかけることこそ、組織を未来に向けて動かしていく確かな小さな一歩なのです。