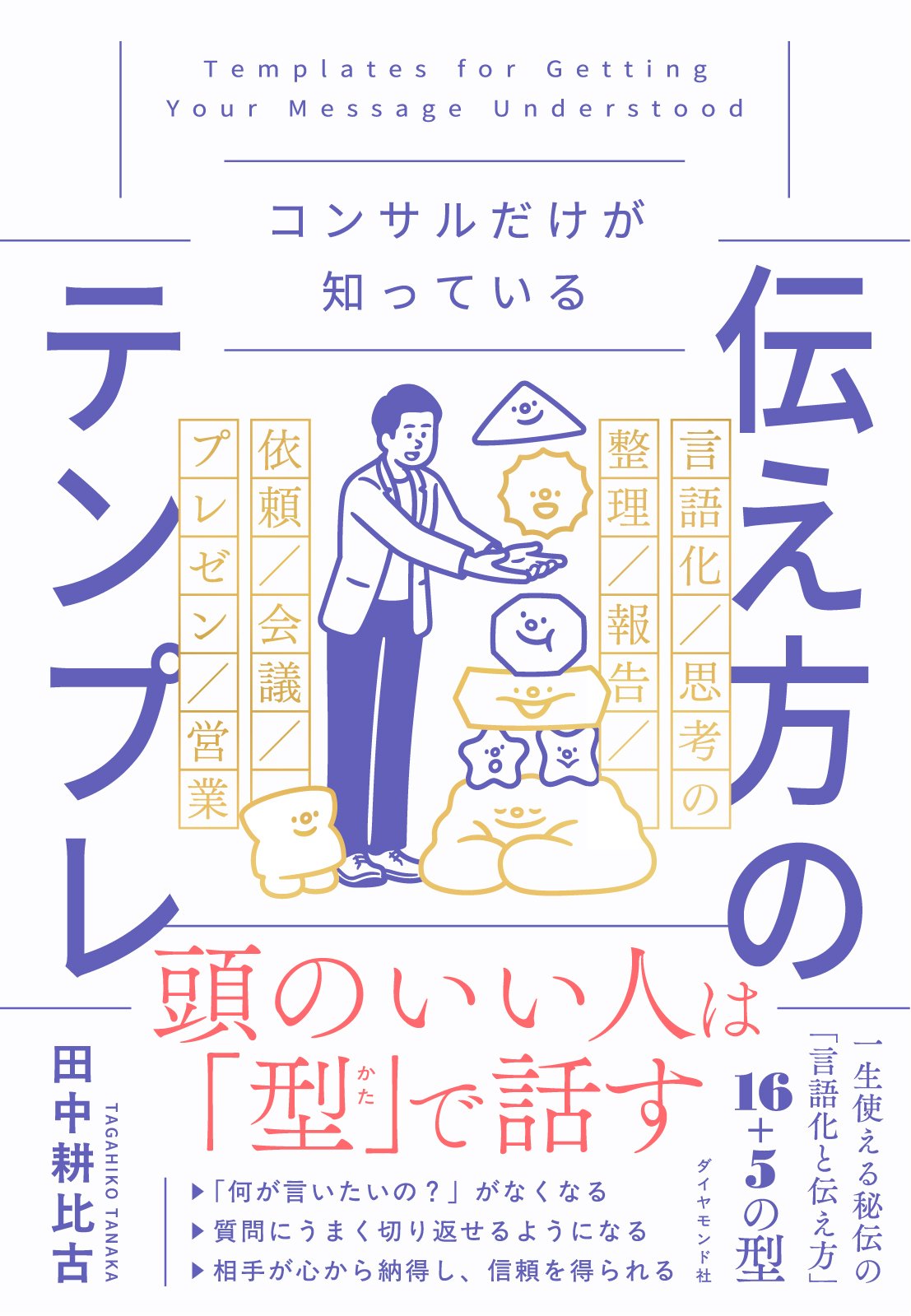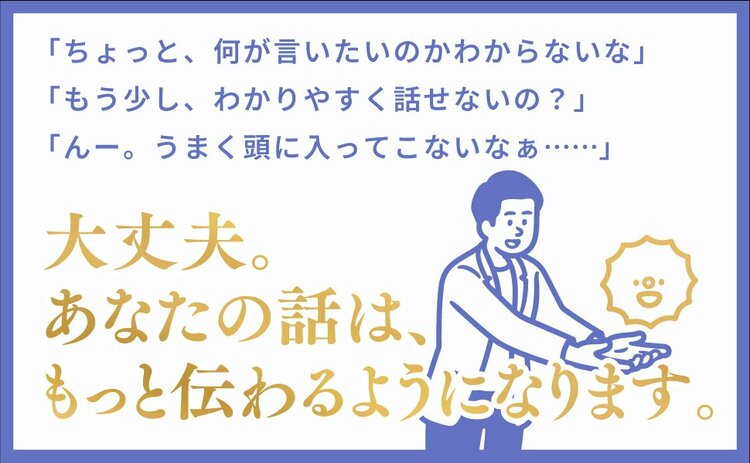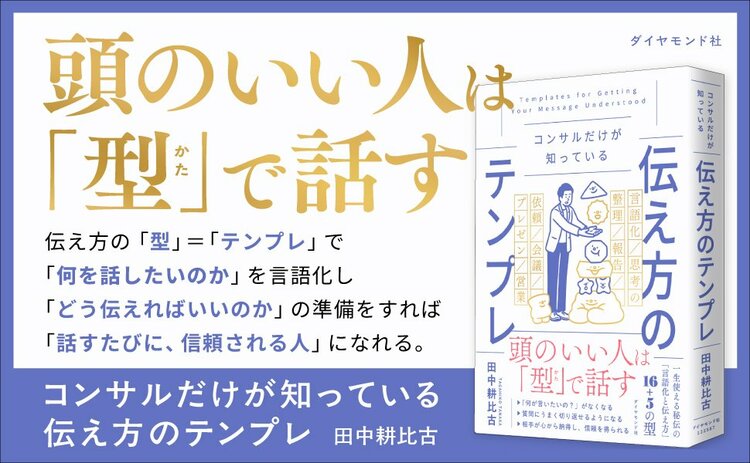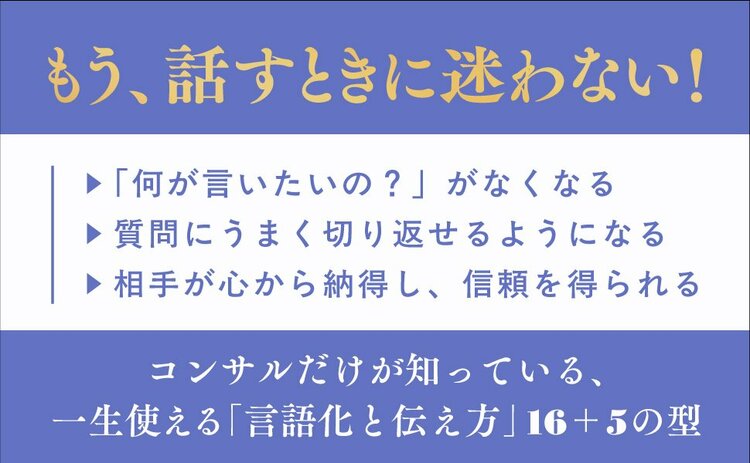「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「経験の浅さ」は相手にとって関係ない
コンサルタントという仕事に就いたときに、上司に言われた中で最も印象に残っているのが、「君たちは、会社を一歩出たら『プロ』として見られている。それを自覚しなさい」という言葉でした。
研修中に受けた講義の中でのひと言です。その講義は1時間ほどのもので、講師を務めてくださった部門長(もちろん、とても優秀な現役コンサルタントでした)に有意義な内容をたくさん教えてもらいました。
ひととおり話を聞き終わった後に、
「さて、皆さんは、いま私が話した内容を、そのまま誰かに説明できますか?」
という質問を投げかけられたのです。
当然ながら、誰一人として「はい。できます」なんて答えることはできず、かなり長い沈黙が流れました。
そのあとに続けられたのが冒頭の「プロとして見られている自覚を持ちなさい」という言葉です。
コンサルタントが、「若手だ」とか「経験が浅い」とか、なんなら「配属初日だ」などということは、クライアントには関係がありません。
高いフィー(報酬)をいただいて、それに対して価値提供をする仕事なのだから、研修中でも甘えてはいけないという教えでした。
もう20年以上前のことなのに、思い出すと、いまでも背筋がピンと伸びるような気持ちになります。
新人であろうと「コンサルタント」として振る舞うことが求められる。
これは、とてつもないプレッシャーです。
しかし、そんなに簡単にコンサルタントとしての知識やスキルが身につくわけもありません。
明らかに実力不足の状態でありながら、百戦錬磨のベテラン経営者や、脂が乗りに乗った現場のリーダーたちと対等に議論する必要があるのです。
そうなると、その場の即興で何とかしようというのは、土台無理な話です。
そうです。話す前に徹底的に準備をすることくらいしか、できることがないのです。
徹底的に準備した上で「話の構造」を整える
コンサルタントは準備として何をするのでしょうか。
まず、クライアント企業のことを徹底的に調べます。有価証券報告書やアニュアルレポート(年次報告書)を5年分見る。
複数の事業があれば、それぞれの関係性や規模などを把握する。競合企業の情報も同じように見て比較し、強みや弱みを考える。
もちろん、これまでのプロジェクト資料などがあれば、すべてに目を通して、どこに課題があり、どこに解決の糸口があるのか(正確に言うと、課題や解決の糸口は何であると、これまでに定義されてきたのか)を理解します。
そして、集めた情報を元にして、相手の立場、ポジションなどを踏まえて、どういうことに興味があり、どういうことを考えているのかを想像します。
相手のことをある程度理解できたら、次に「伝えること」を考えます。
その人の関心領域、興味範囲に則して、どういう情報を、どのように伝えるべきか。
また、自分が説明をした上で、相手にどんな気持ち・感情を抱いてもらいたいか。その結果、どういう行動をしてもらいたいのか。
伝える内容・順番・相手の感情・行動などを整理していきます。
このように徹底的な準備をすることにより、20年、30年という期間をその企業・業界の第一線で活躍してきたクライアントにも、何とか話を聞いてもらえる状態まで持っていくわけです。
ここで役立つのが「話の構造」です。
構造を整えて話すことで、聞き手の脳内が整理され、話の内容に耳を傾けてくれるようになります。
何が課題か。何が解決策か。なぜそれが有効なのか。
それらを無理なく、相手の理解速度に合わせ、順序だてて説明する。
結論を先に伝えたり、あるいは、前提を揃えたりするところから始める。
聞き手の思考の進み具合に合わせて、根拠を伝えたり、具体例を伝えたりして、理解を深めてもらう。
議論すべきポイントを明らかにして、話の構造を示し、納得してもらえる順番で説明していきます。
そうすることで、相手は、「話を聞く価値のある人」としてこちらを認識してくれるようになります。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)