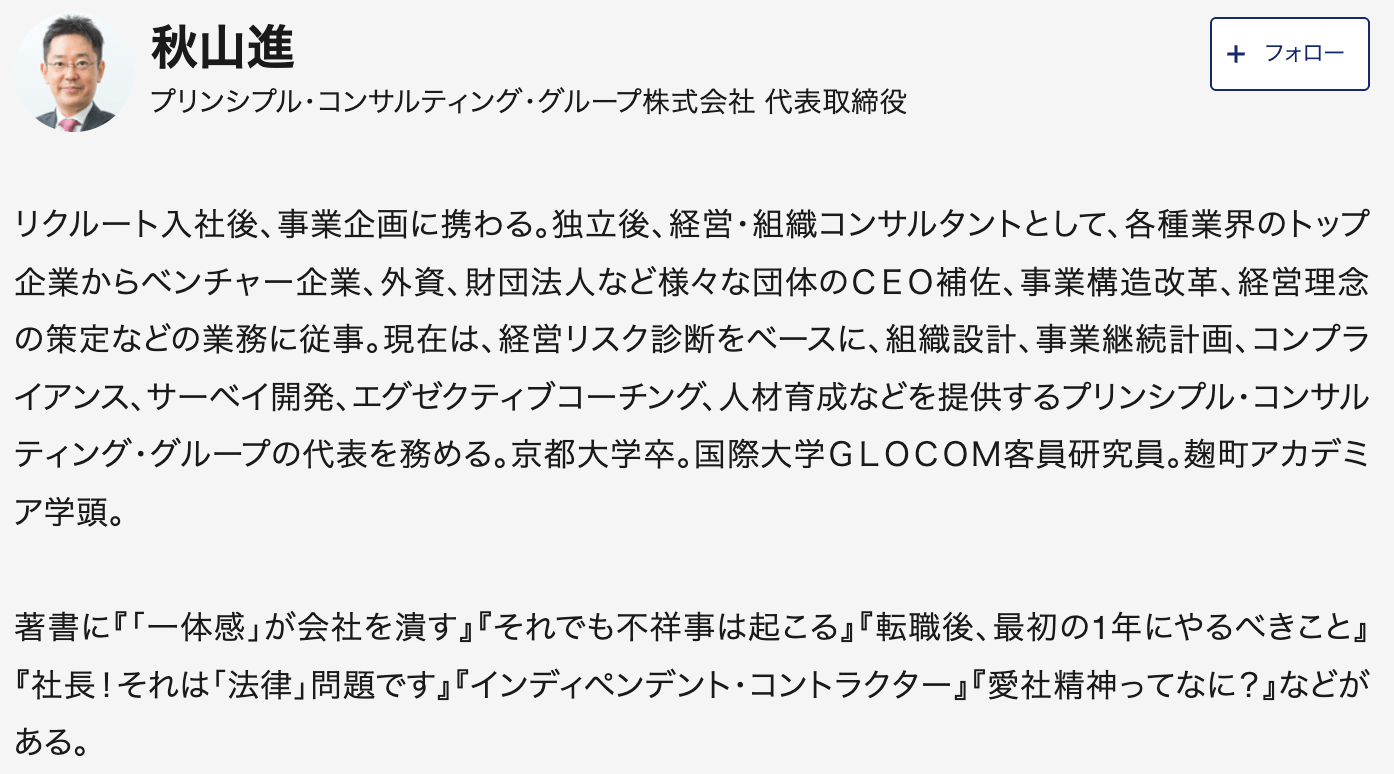内集団びいきの個体差
もう一つ考慮しておくべきことは、内集団びいきの強さは人によって異なるということである。
ある人は内集団に属していることを積極的に表明する。慶應の三田会の熱烈さはその典型である。少し“暑苦しい”と感じることがないわけはないが、その連帯はビジネス界において好影響があり、声高に語るメリットがあるのだろうと推察できる。
一方で、意識的に集団から距離を取る人もいる。むしろ集団に属さないことに矜持を持ち「自分の実力で勝負したい」と考える人も少なくない。
ただし、ビジネスは団体競技なので、公式の権限規定に基づく組織運営だけでは行き詰まることもある。
こんなときは、内集団を巧みに利用する人がうらやましく思えたりもするだろうが、内集団に参加することで「奪われる」個人の時間やお金といったコストを考えると、とても付き合いきれないと思い直す。それはそれでひとつの見識である。
いずれにしても、内集団活動については、興味のある人はいるし、興味のない人もいる。参加を無理強いするものではない。
結論――2つの処方箋
以上のようなことから、人によって集団への帰属意識の深さは異なることを前提に、組織は内集団とうまく付き合う必要がある。では、どうすべきだろうか。方法は大きく2つあると考えられる。
1つ目は、標準的な方法である。評価基準を厳格化し、内集団びいきを排除することを目指す。
採用や昇進で出身校や人脈を外し、成果や能力だけを基準にする(現に、あえて面接官が応募者の大学名を見られない状態で面接する企業もあると聞く)。これは理屈としては正しく、公平性を担保できる。
しかしながら、人間の本能にも近いであろう内集団びいきを、人工的に作った評価基準でうまく制御できるかどうか、実際には難しいところがある。
もう1つは、むしろ内集団びいきを前提にして、たくさんの内集団をクロスオーバーさせることだ。社内のスポーツクラブや趣味の会、同郷会や同期会、部門を超えた研修やワークショップ、勉強会など、いくつもの小集団の活動を活発化させ、特定の内集団だけが突出しないように仕向けるのである。
人間関係を固定化させず、流動化させ、いろいろな領域でさまざまなつながりを持たせる。
見た目には前者が理想的に思える。だが現実に機能するのは後者だろう。内集団がたくさんあることにより、特定の内集団だけが突出して得をする構造を無くすのである。
しかし、この方法も、自分の出身部門や自分の後輩筋ばかりを出世させるような特定の内集団をてらいもなくひいきするトップが出てくると、とたんに機能しなくなる。
よって、「落としどころ」としては、上記2つのハイブリッド作戦が取られるのだが、それでもなかなかうまくいかない。
今後はAIなどを利用して内集団ひいきを制御すべきという話になるだろう。しかし、そうすると内集団びいき問題どころか、あらゆる評価があらゆるバイアスによってゆがめられていることがわかって、頭を抱えることになる。
甲子園にまつわる「自分がどこの高校を応援するか」問題は、意外に根深く解決が難しいのだ。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)