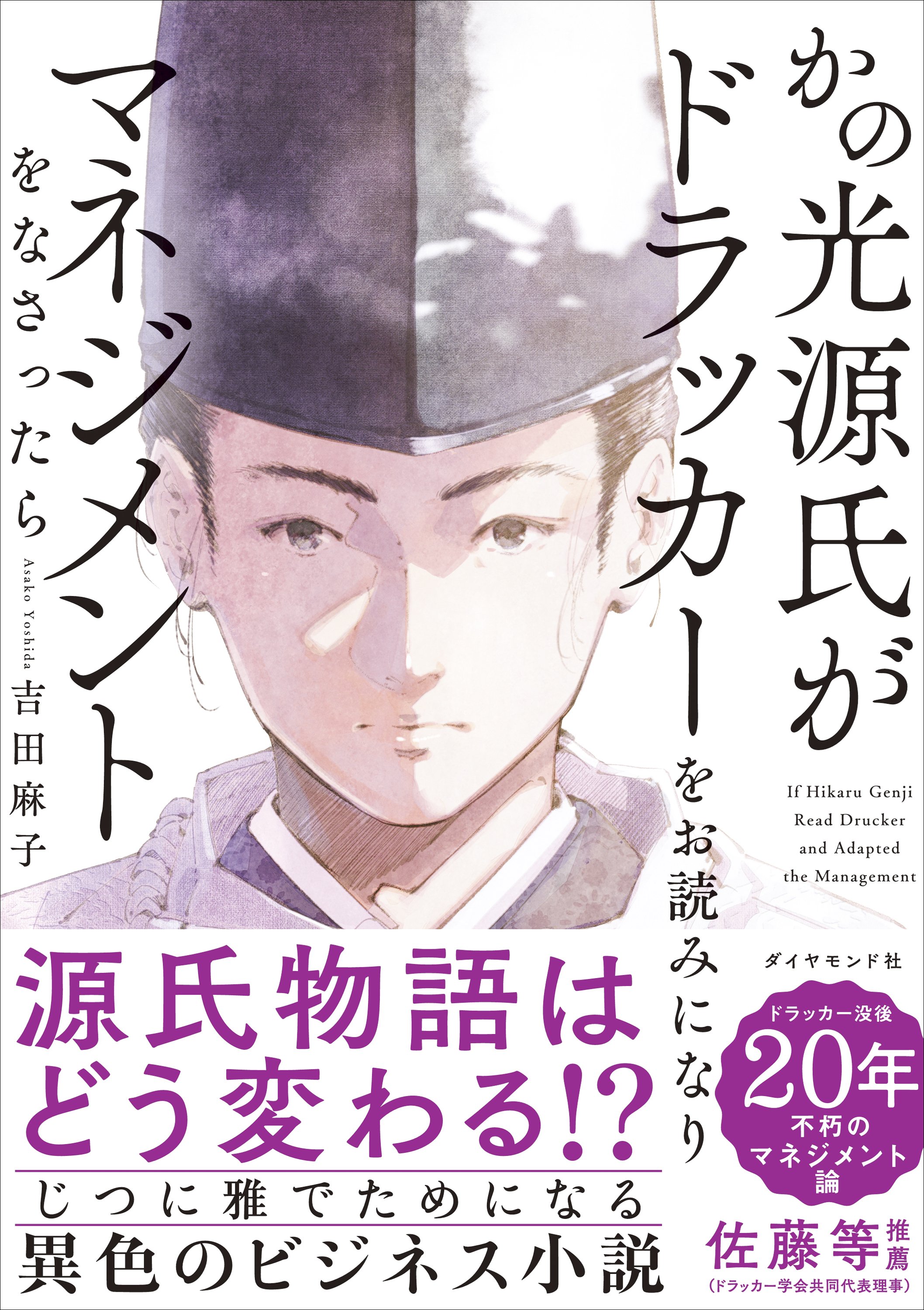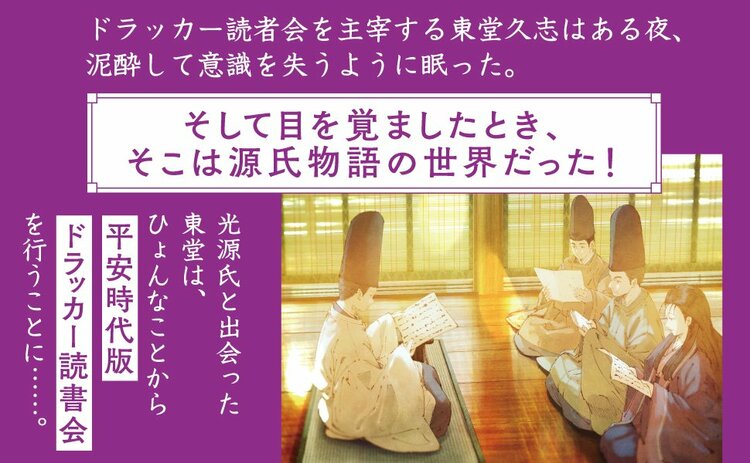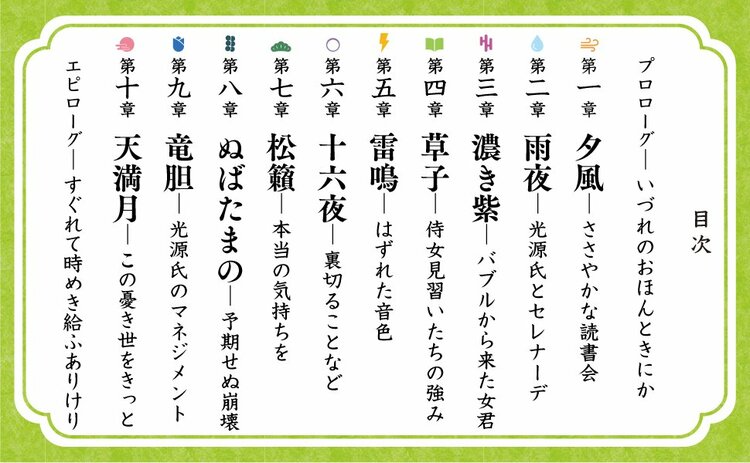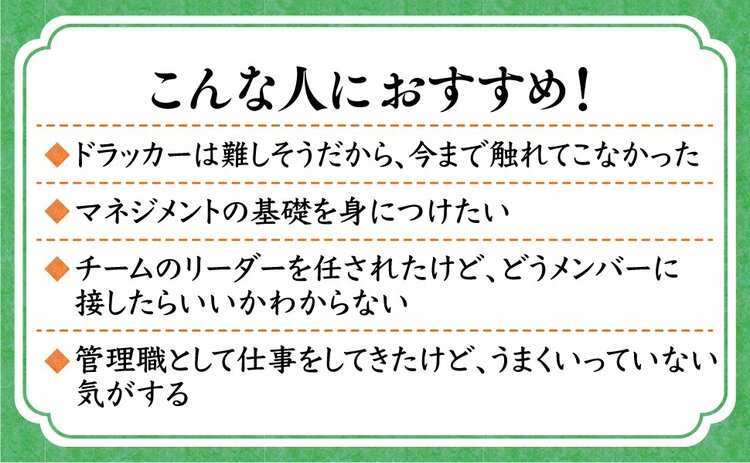「貢献」を要求するための問い
今、うちのチームに足りないものはこれかもしれない。
佐々木だけが結果を出し、周りが委縮している状況。
もしも佐々木が「貢献」の視点を手に入れたらどうなる?
いや、佐々木だけでなくメンバー全員が「貢献」の視点を手に入れたら……。
「成果をあげるには、自らの果たすべき貢献を考えなければならない。手元の仕事から顔を上げ目標に目を向ける。組織の成果に影響を与える貢献は何かを問う。そして責任を中心に据える」
――うちのチームが一皮むけるチャンスかもしれない。
この章には上司が部下に貢献を要求するために聞く問いが書かれていた。
・組織および上司である私は、あなたに対しどのような貢献の責任を期待すべきか
・あなたに期待すべきことは何か
・あなたの知識や能力を最もよく活用できる道は何か
――さっそくこれを佐々木に聞いてみよう。いや、メンバー全員に聞いてみよう。自分自身にも問いかけよう。これによって、皆が果たすべき貢献を考えることになるのだ。
「果たすべき貢献を考えることによって、横へのコミュニケーションが可能となり、その結果チームワークが可能となる」
赤坂課長には、新しいチームの姿が見えてきたようだった。
――そうだ、確か……。
赤坂課長はふと思い出して『非営利組織の経営』を開くと、この言葉を見つけた。
「チームの目的は、メンバーの強みをフルに発揮させ、弱みを意味のないものにすることである。こうして一人ひとりが力を発揮する。大事なことは一人ひとりの強みを共同の働きに結びつけることである」
チームの中で一人が突出すること自体は悪いことではない。
だが、その強みを共同の働きに結びつけなければ、成果は続かない。
大事なのは、一人の強みを組織の成果へと結びつける設計をすることなのだ。
赤坂課長はさっそくノートを開いて新しいタスクを書き込んだ。
強みと貢献を結びつける
佐々木のような「成果を出すが、チームを疲弊させる人材」は、どの組織にも存在するかもしれません。
ドラッカーの示す解決策はシンプルです。
弱みを矯正するのではなく、強みを生かし、貢献という軸で再設計すること。
そのとき初めて、個人の成果が組織の成果に結びつき、チームが本来の力を発揮できるのです。
あなたの組織には、今まさに“強みと貢献を結びつける”視点が必要な場面はありませんか。