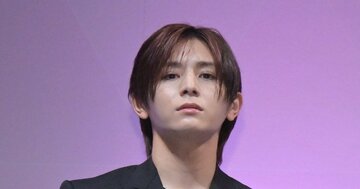今回の構図はこれにぴったりはまったので、ネットメディアが大喜びで、SNSでの反応(実際の世相)以上に、「YOSHIKIが叩かれています!」とやっている。筆者はそのような印象を持っている。
こうした問題を目にするにつけ想像されるのは、SNSの運用の難しさと共に、著名人の生きることの大変さである。誰でも人間だし気分や機嫌はある。いつもなら許せる言葉が、聞き流せる言葉がどうしても気になってしまうこともある。
使用許可は取るべきだった?
「オマージュ」そのものに対する議論
「HAYASHii」は「お囃子」で「林」じゃないんだから何をぐちぐち言ってるんだ、みたいなことを発信している人も散見されるのだが、こればっかりはYOSHIKIが勘違いするのも無理はない。偶然の妙が絡んだ不運としかいいようがない。
本人にとっては繊細な問題なのだから、他人がそれを切って捨てるのは思いやりが不足しているように感じる。何しろ本人はその勘違いについて詫びているのである。
そうした、ちょっとした失言や勘違い、失敗に世間は非常に厳しい。そういうものと言ってしまえばそれまでだが、世の中で飛び交っている言葉がもう少し優しくなればいいのになあと思わずにはいられない。
一応の解決を見て、YOSHIKIが締めくくりポストをしたのだから、閉幕後の舞台上に識者かなんかがまた出てきて「やっぱりYOSHIKIさん、残念でしたね」とやるのはオーバーキルでまぜっかえしである。「YOSHIKIさんのあそこが残念でしたが解決してよかったですね」とやれれば美しい。
「オマージュされる側は異論を挟まず理解すべし。さもなくばカルチャーは衰退する」という声も出てきている。言わんとするところはわからなくもないが、理解の押しつけは暴力的になり得る点について、求める側は自覚的でありたい。
今回のこの問題ではオマージュやパクリについてのそもそも論への踏み込みも見れた。
・制作は使用許可を取っておけば何も問題なかった→許可の打診の強要はエゴではないか。
・いちいち使用許可を取るとスピード感損ねるし、本来法律上は問題ないけど道義上筋を通すために許可を取ろうとしてるのに「ダメ」って言われたらダメになっちゃうし、許可してくれても口出しされて作品がゆがめられる可能性はあるしで、最初から許可を求めないままやっちゃった方が作品にとってはリスクが少なく賢明ではないか。
・いちいちパクリって騒ぐのは表現の自由の阻害ではないか→じゃあパクる自由は法に触れなければ無制限に認められるのか。