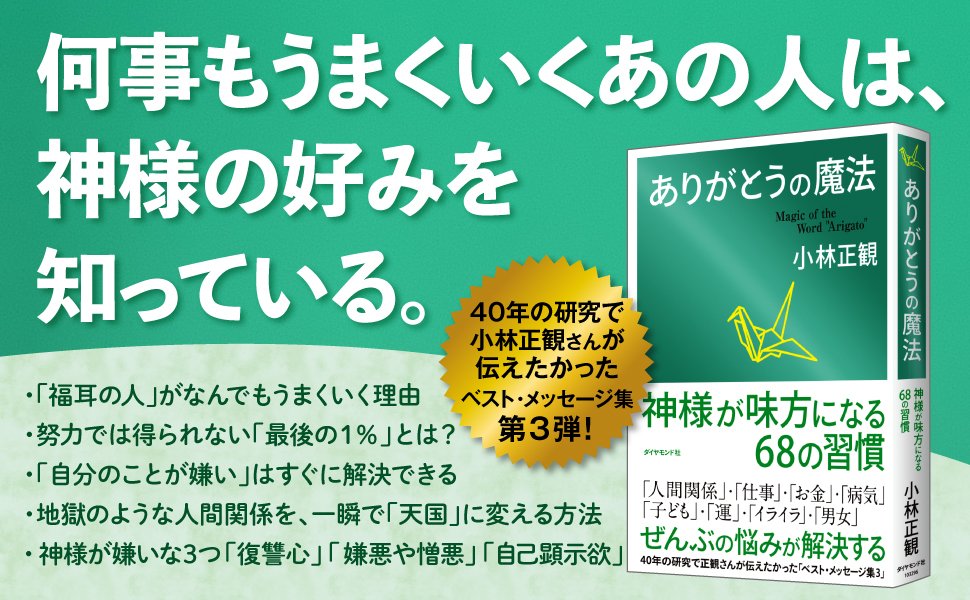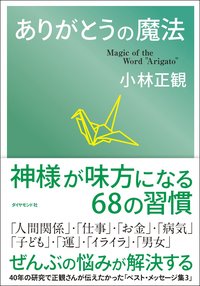2017年の発売以降、今でも多くの人に読まれ続けている『ありがとうの魔法』。本書は、小林正観さんの40年間に及ぶ研究のなかで、いちばん伝えたかったことをまとめた「ベスト・メッセージ集」だ。あらゆる悩みを解決する「ありがとう」の秘訣が1冊にまとめられていて、読者からの大きな反響を呼んでいる。この連載では、本書のエッセンスの一部をお伝えしていく。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「言葉」には、神様が宿っているらしい
「愛語」という言葉は、良寛和尚が好んで使っていたと言われています。良寛和尚の「愛語の心」とは、こういうものだと聞きました。
「自分は貧しいひとりの修行僧なので、人に与えるもの、あげるものが何もない。だからせめて、心をあたたかくするような、心を安らげるような『言葉』をあげたい。それならいくらでもあげることができるから」
良寛和尚は、自分の口から出てくる言葉を「あたたかい言葉」「やさしい言葉」「思いやりに満ちた言葉」にしたいと思っていたようです。
言葉には、どうも、すごい力が宿っているようです。
「Oリング(オーリング)」という実験があります。自分の利き手の手のひらを上に向け、親指と人差し指でアルファベットの「O」の形をつくります。「つらい」「苦しい」「つまらない」と言ったあとに(誰かに言ってもらったあとに)、Oリングが開かないように指に力を入れ、誰かに開けてもらいます。
開ける人も、両手にOリングをつくり、開けられる人のOリングに通して、左右に引っ張ります。すると、なぜか力が入らずに、簡単に開けられてしまいます。
その反対に、「嬉しい」「楽しい」「幸せ」と言ったあと(誰かに言ってもらったあと)は、なぜかOリングは、なかなか開きません。
「つらい」「苦しい」「つまらない」と言うと(言われると)力がシュンと抜けてしまい、「あたたかい言葉」「やさしい言葉」「思いやりに満ちた言葉」を言うと(誰かから言われると)、筋肉や細胞に力がみなぎるらしいのです。
日本の神道には「言霊」という概念があります。
「言葉には神が宿っている」という考え方ですが、私たちは、普段、使っている言葉のひとつ1つに、相手に大きな影響を与える力(神)が宿っていることを忘れていたのかもしれません。
良寛和尚は超能力的な解釈から「愛語」に至ったわけではなく、与えるものが何もなかったから「愛語の心」に行き着いたのだと思いますが、「人をシュンとさせる言葉は使わない」という思想は、「宇宙的事実を読み取っていた」とも解釈できるでしょう。
京都に、空也上人の木像があります。木像の口から細い板が出ていて、その上に、小さな仏様が何人も立っています。
説明によると、「空也上人の口から発せられるひと言ひと言が、すべての人を救いに導く『仏』であった」というのです。
私はこれまで、「不平不満・愚痴・泣き言・悪口・文句」を言うことは、「悪臭を放つ花の種を蒔くこと」と同じだと考えていましたが、一歩進んで、自分の口から発せられる言葉をすべて、「あたたかいもの」「勇気づけるもの」「安らげるもの」「幸せを感じさせるもの」「喜びを与えるもの」にできたらと思います。
そうすれば、「芳香を放つ花の種を蒔く」ことにもなるでしょう。
「悪臭」の中で生きるか、それとも「芳香」の中で生きるか……。芳香の中で生きるほうが、楽しそうです。
「言葉には『神』が宿っている」という考えは、「言葉には『気』が込められている」という考えでもあります。
だとすれば、人の心を明るくする気を込めたいものです。人に対して、「愛語」を考えるだけでも、生活が変わってくるような気がします。