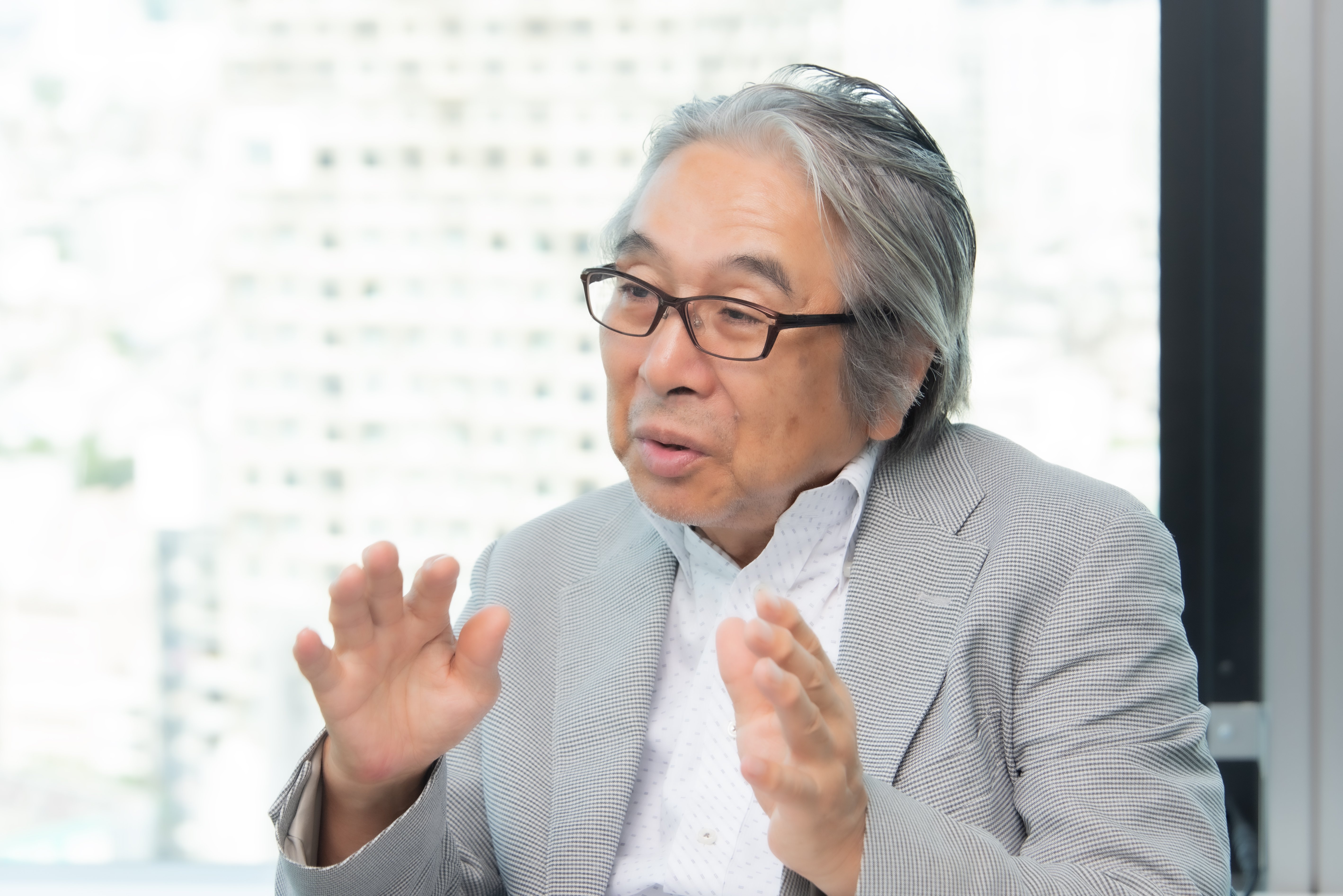 クオリティメディアコンソーシアム事務局長、BI.Garage 特命顧問の長澤秀行氏
クオリティメディアコンソーシアム事務局長、BI.Garage 特命顧問の長澤秀行氏
あなたの会社の広告が、意図せず不適切なサイトに表示されているかもしれない――。そんなことが現実となり得るのが、現代のデジタル広告の世界である。2022年には日本の広告費7兆1021億円のうち約44%を占めるに至り、最大の広告手段となったインターネット広告の信頼はなぜ揺らぎ、課題を抱えることになったのか。その根深い構造的問題と、これからのメディアや企業がとるべき未来への針路とは。日本のデジタル広告の品質改善に長年取り組んできた、クオリティメディアコンソーシアム事務局長の長澤秀行氏に聞いた。(聞き手/Diamond WEEKLY事業部 編集長 小尾拓也、撮影/平野晋子)
「もうコンテンツ製作コストが持たない」
危機感から始まったコンソーシアム
――まず、長澤さんが主宰されているクオリティメディアコンソーシアムがどのような役割を担い、参加されているメディアの方々がどのような課題意識をお持ちなのか、お聞かせください。
クオリティメディアコンソーシアムは、5年前に「コンテンツメディア価値研究会」として立ち上がりました。当時から、広告の世界ではプラットフォームが圧倒的な力を持っており、個々のコンテンツメディアの広告の価値は認められにくい状況でした。インターネット広告の世界では、広告費は少なく、広告単価も他社と変わらない。いわゆるオープンウェブ(マーケターが制限なしにオーディエンスと関わり、製品を宣伝し、コンテンツを配信できる場)の世界は、日本市場では2割にも満たない規模です。
現在のネット広告のモデルでは、コンテンツメディアが取材や編集にかけるコストを賄えなくなるのではないか。そんな危機感を多くのメディアが持っていました。もちろん、サブスクリプション(一定期間の利用に対して料金を支払うビジネスモデル)やIP(知的財産)活用といった広告以外の収入源もありますが、やはり広告に頼る部分は大きい。
そこで、広告の価値や収益を上げていくために、1社だけでは厳しいので、大手が手を取り合ってやろうじゃないか、ということで始まったのです。
新聞社、テレビ局、デジタルメディアといった主要ニュース媒体を中心に、当初は30社以上が集まり、さまざまな調査研究を行いました。たとえば、ユーザーの脳波測定による感性分析を使ってメディアのコンテンツと広告の相関関係を見る調査も実施しました。
――サプライサイドであるメディア側だけで価値を訴えても、プラットフォーム中心の流れはなかなか変わりませんよね。
その通りです。そこで、メディアを指定して広告を取引できるPMP(プライベートマーケットプレイス)の仕組みを立ち上げ、事業化しようということになりました。マスメディアや、きちんとコンテンツを作っているメディアを中心に、事業としてやってみようと。最終的に28社に賛同いただき、結成したのがコンソーシアムの始まりです。







