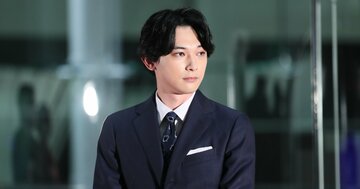Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
医者が処方する治療アプリの国内3例目となる「CureApp AUD 飲酒量低減治療補助アプリ(以下、本アプリ)」が保険診療で利用できるようになった。適応は減酒が治療目的となる初期のアルコール依存症(アルコール使用障害:AUD)患者だ。
日本国内のAUD患者は約54万~107万人と推測される一方、専門的な治療を受けている患者はおよそ5万人にすぎない。背景として専門医へのアクセスのハードルが高い、また「断酒/禁酒」の2文字に抵抗を覚えるAUD初期の患者が多いことが指摘されている。
このため近年は、初期AUD治療の担い手を専門医からかかりつけ医へ、また「何が何でも断酒」から「まずは減酒(飲酒量低減)」へと治療戦略そのものが変化してきた。本アプリはこうした流れを受けて開発されたもので、一般内科や普通の精神科、心療内科での処方を想定している。
本アプリは、当事者がバーチャルアシスタントの“ナンシー”の支援を受けながら、問題がある飲酒行動を誘発するリスクの理解や健康的なストレスケアなどに取り組む「患者用アプリ」と、患者の飲酒行動の把握と心理教育、動機付けの強化に使う「医師用アプリ」で構成される。
飲酒量低減療法の適応となる20歳以上を対象とした国内の臨床試験では、本アプリと一般的な飲酒日記アプリ(対照群)とで「大量飲酒日(HDD)」の変化量が比較された。介入前のHDDは、本アプリ群が19.4/28日、対照群は19.1/28日だった。
本アプリ群136名、対照群142名で検証した結果、アプリ使用後12週目のHDDは本アプリ群が-12.2日、対照群は-9.5日と、本アプリ群で有意に減少。また、1カ月間にHDDを繰り返す頻度や飲酒量も有意に減少した。
ちなみに、一般内科で「危険な飲酒者」に対して1分未満の口頭アドバイスを受けたとしても、12週後の飲酒行動には何ら影響がないことが国内の研究でわかっている。不適切な飲酒行動を改めるには、一時的な指導ではなく、日々諭してくれる相棒が必要らしい。
AUDは明確な健康リスクだ。もし、自分でもままならない飲酒癖に悩んでいたら、風邪や高血圧の診察ついでに相談してみるといいだろう。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)