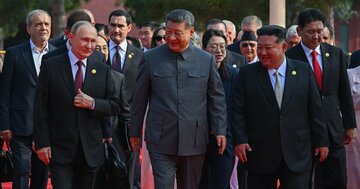さらに、米シンクタンクであるスティムソン・センターのユン・スン氏は『フォーリン・アフェアーズ』への寄稿で、2期目のトランプ大統領が人権問題で中国に圧力をかけることを避け、関税に偏重した政策に終始した結果、中国がレアアース分野で押し返し、主導権を奪われなかったことに安堵していると指摘している。
https://www.foreignaffairs.com/united-states/strategies-prioritization-lind-press
このようにトランプ政権が同盟国に厳しく、中国に思いのほか妥協的であることに対して、不満を持っている国が少なくないことが見て取れる。
中国資本を受け入れる
イギリスを優遇する矛盾
今回の相互関税政策において、注目すべきはイギリスの扱いだろう。
イギリスはブレグジットの反動による需要縮小で、中国との貿易や投資を強化してきた。ロンドン金融市場は依然として中国資本の流入を受け入れ、中国企業のロンドン上場も続いている。
それにもかかわらず、トランプ政権は英米の「特別な関係」を理由に、イギリスに対しては制裁や関税を緩和している。
これらは、スターマー政権がトランプ大統領を異例の二度目の国賓として迎え入れ、王室外交をフル活用した結果だろう。
イギリスが王室外交を使い、相互関税を10%に抑えた背景には、ピーター・マンデルソン氏が在米英国大使としてうまく立ち回ったことが大きかったと伝えられている。マンデルソン大使は未成年少女への性的虐待で逮捕された故エプスタイン氏との関係が取りざたされ、9月に解任されたが、米英関係はその後も良好に進んでいる。
日本やEUがトランプ高関税の打撃を受ける一方で、イギリスはFTA交渉の優先順位を高められ、一部製品は関税免除の対象となっている。対中強硬ではないイギリスの関税率が10%と最も低いものになったことは、安全保障問題を大義名分に関税交渉をしている意義をあいまいにしている。
このダブルスタンダードは、中国包囲網に対する意欲を失わせ、日本や欧州の対米不信を強めている。イギリスもEUも、むしろ以前より積極的に中国接近を試み始めており、トランプ外交は一期目より一貫性を失っている。