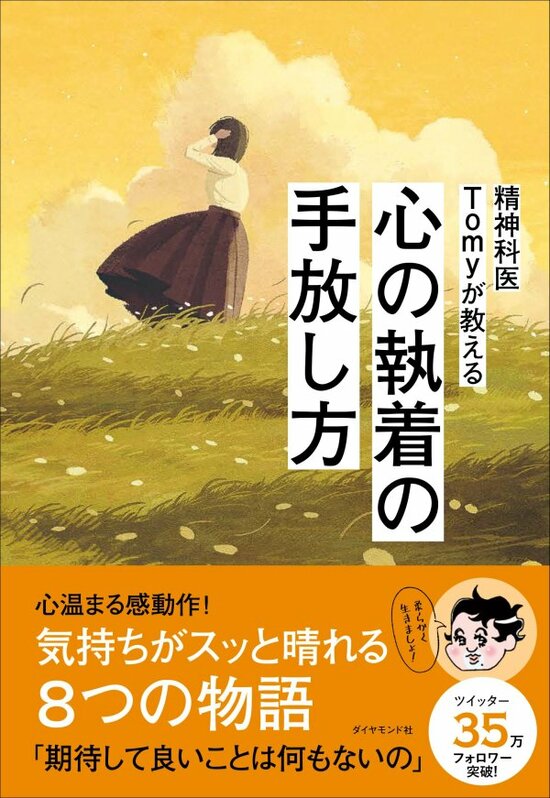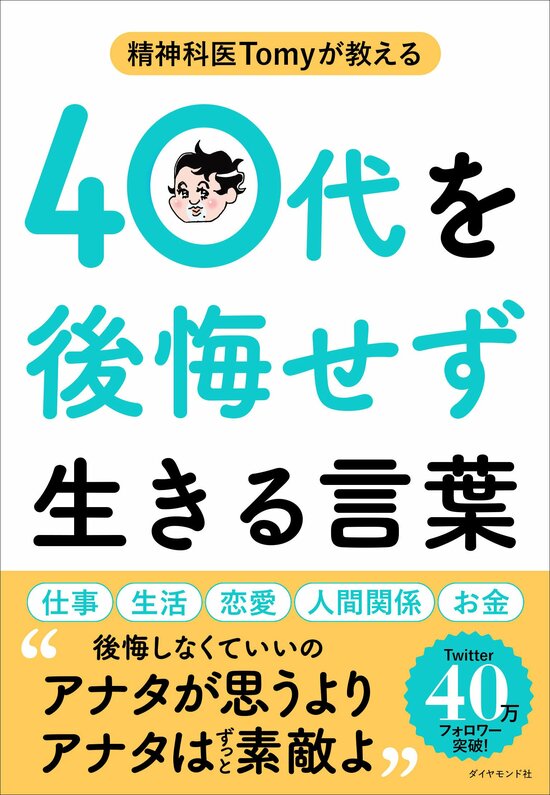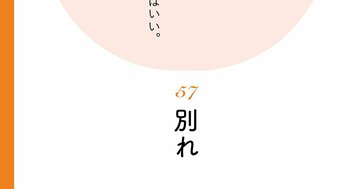マイナス思考に囚われる人と受け流せる人の決定的な“口癖”の違い
誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える心の執着の手放し方』(ダイヤモンド社)など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「マイナス思考から抜け出す」という考え方の落とし穴
今日は「マイナス思考から抜け出す方法」という、最近よく耳にするテーマについてお話しします。
結論から申しますと、「マイナス思考から抜け出そう」と考えること自体が、実はあまり効果的ではありません。なぜならマイナス思考は、無理に抜け出そうと意識しなくても、自然と離れることができるものだからです。
考えてみてほしいのですが、一日中ずっとマイナスなことばかり考えている人は、世の中にいるでしょうか。おそらく、いないはずです。たとえネガティブになりやすい傾向がある人でも、起きている間ずっとマイナスのことを考えているわけではありません。
人は何かの作業をしている時はそのことに集中しますし、楽しいと感じている時は、マイナスなことは考えていないもの。マイナス思考は、あくまで「ふとした瞬間」に湧いてくるものなのです。
なぜ「抜け出そう」とすると、かえって囚われてしまうのか
問題なのは、この湧いてきたマイナス思考に対して「抜け出さなければ」と強く意識してしまうことです。そう思うと、何が起きるのでしょうか。それは「記憶の強化」です。
「私は今、マイナス思考に陥っている。なんとかして抜け出さなくては」と考えることは、自分自身に「マイナス思考をしている人間だ」というレッテルを貼る行為に他なりません。「早く消さなくては」と焦れば焦るほど、そのマイナス思考を何度も自分の中で反芻し、心に深く刻みつけてしまうことになるのです。これでは、抜け出せるはずがありません。
マイナス思考は「心の暇」にやってくる
では、どのような時にマイナス思考は湧いてきやすいのでしょうか。それは多くの場合、「今やっていることに集中していない時」、つまり心がお暇になっている時です。
毎日、私たちは仕事や家事など、やるべきことがたくさんあります。仕事に取りかかった瞬間は仕事のことだけを考えていますし、美味しいご飯を食べている時は、その味に集中しているはずです。その間は、マイナス思考が入る隙はありません。
しかし、作業が一段落したり、手持ち無沙汰になったりすると、ふとネガティブな感情が湧き上がってくるのです。
最も効果的な対処法は「それはさておき」
では、マイナス思考が湧いてきた時、具体的にどうすれば良いのでしょうか。
おすすめしたいのは、「それはさておき」という言葉を使って、意識を「今やるべきこと」に向けることです。
「それはさておき、勉強を始めよう」
というように、目の前のタスクに意識を切り替えるのです。そうすると、いつの間にかマイナス思考のことは忘れてしまっているものです。このように、マイナス思考から無理に抜け出そうとせず、ただ受け流して現在の行動に集中することが、最も健全で効果的な対処法と言えます。
感情は時間と共に自然に弱まっていくものです
人間の感情というものは、発生した瞬間が最もエネルギーが強く、その後は時間と共に少しずつ弱まっていく性質があります。もちろん、ふと思い出して感情の波が再び高まることもありますが、基本的には自然に減衰していくものなのです。
本来であれば、放っておけば静かに消えていくはずの感情を、「このマイナス思考をなんとかしなくては」と考えることで、わざわざエネルギーを注ぎ足し、消えないようにしてしまっているのです。これでは、いつまでもマイナス思考から解放されません。
マイナス思考はあって当たり前
結論として、「マイナス思考から抜け出そうとするから、抜け出せなくなる」のです。
マイナスなことを考えてしまうのは、人間としてごく自然なことです。それを悪者扱いして無理に消そうとする必要は全くありません。「あ、また考えたな。それはさておき、今の作業を続けよう」と軽く受け流す。
この記事が、心の中のネガティブな感情と上手に付き合っていくための一助となれば幸いです。
※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。