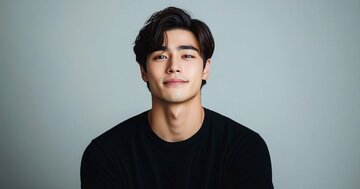AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“解決策”を見つける「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、課題の解決策を見つけたいときにおすすめなのが、技法その39「促進の要因」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈課題を記入〉という問題の解決に役立つ要素は何ですか? 異なる視点から、各分野の専門家として、詳細に可能性をリストアップしてください。
課題に対して、どこから考えていいのか見当がつかないとき、すぐに諦めたりツールなどに飛びついたりするのではなく、まずは視点を変えて「課題を分析」してみてください。
ただ、人の視点は悪気なく固定されるもので、変えようにも「どう変えたらいいのかわからない」となるのが普通です。先入観が、私たちの邪魔をします。
その余計な先入観を、AIでとっぱらいます。
技法「促進の要因」は、AIを使って各種の専門家を呼び出して様々な視点から課題を分析してもらい、解決に関わる要素を拾い上げてもらう使い方です。人間なら迷うところを、多面的な観点から課題分析してくれます。
「英会話教室を黒字化させる」ためのヒントを探してみよう
では、実践してみましょう。
扱うのは赤字経営の英会話教室。コスト削減だけが解決策のように思ってしまいがちですが、それでは根本的な解決にはなりません。競合と比較して潤沢な資金やリソースを持たない小規模事業者が採るべきは、一点突破のアイデアでしょう。その一点を見つけるために、現状課題の多角的分析から始めて、広範に可能性を拡げてみます。
〈A市で3店舗を運営している英会話教室が、過去4年間、収支が赤字に陥っています。このままでは倒産、もしくは教室を閉鎖する必要があります〉という問題の解決に役立つ要素は何ですか? 異なる視点から、各分野の専門家として、詳細に可能性をリストアップしてください。
課題解決を試みるときには「問題」や「未充足なニーズ」といった不満や未達部分に目が行きますが、まずは冷静な現状把握からスタートしましょう。