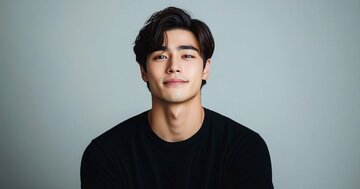AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使ってアイデアを“検証”する「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、仕事において生み出したアイデアに対して「自社でやるべきか?」「やるならどう改良するか?」と検討したいときにおすすめなのが、技法その28「強みの検証」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈ビジネスのアイデアを記入〉
この事業を成功させるのに必要な強みは何ですか? この事業を行うのに最適な企業はどこですか?
<AIへの指示文(プロンプト)②>
自社の強みがより活きるようにアイデアを改良するならば、どのようになりますか?
〈自社の詳細を記入〉
※プロンプト①で示された強みが自社にはないときに②を使ってください
自社の「強み」が活かせて、競合他社に対して優位性のある新規事業こそ、ローンチする意義があります。この「強み」の把握、そして他社との比較や優位性の明確化。これらをAIで一気に実践してしまうのが、技法「強みの検証」です。
この技法によってAIが明らかにしてくれるのは、自社視点から離れて考えた際の、そのビジネスアイデアに必要な強みです。発案者なら当然ある程度の“当たり”はついていると思いますが、改めて外部視点から「見える化」できます。
新しいコーチングビジネスの「強み」を検証してみよう
では、実践に行きましょう。
ここでは例として、「若手ビジネスパーソン向け格安コーチング」で考えてみましょう。この事業プランを遂行するには、どんな強みが必要なのでしょうか。
〈若手ビジネスパーソン向け格安コーチングビジネス〉
この事業を成功させるのに必要な強みは何ですか? この事業を行うのに最適な企業はどこですか?
AIが出してくれたアイデアをそのままコピー&ペーストして挿入してもかまいません。日本語のつながりが多少変でもAIは拾ってくれます。