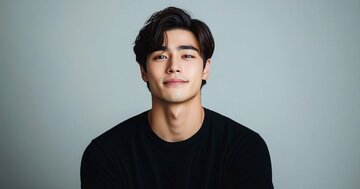AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って人の“悩み”をとらえる「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、顧客やユーザーといった人たちの「本当の悩み」をとらえたいときにおすすめなのが、技法その47「主な困りごと」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈人や属性を記入〉が困っていることをあげてください。
「人の悩みをとらえる」ことは意外と簡単ではありません。同じように見える悩みも、細分化されていたり人によって事情が異なっていたりします。「悩みはなんですか?」と聞いても、素直に本心を答えてくれるとはかぎりません。それ以前に、そもそも自分の悩みに気づいていない、ということもあります。
そこで役に立つのが、この技法です。とてもシンプルなプロンプトであるからこそ、対象となる属性の人たちが何に困り、苦しんでいるのかを、先入観なく広く挙げてくれます。かなりニッチな存在(人)でなければ、ある程度の確からしさで困りごとを把握できるでしょう。
「焼肉店のお客さん」の困りごとを分析してみよう
では、実践に行きましょう。
ビジネスシーンでのケーススタディを見てみましょう。ファッションにおけるSPA(製造小売業)のように、牛肉の卸業者が小売り、すなわち焼肉店などの経営にも事業拡大するケースが散見されます。商材はどちらも「お肉」ですが、卸業はB2B、店舗はB2C。業態が変わればお客さんも変わります。「飲食店に来るお客さんの要望なんて考えるまでもない」とタカをくくらず、AIの力を借りてみましょう。
〈焼肉店を利用するお客さん〉が困っていることをあげてください。
誰しも一度は焼肉店に行ったことがあるでしょう。けれども、自分の感覚を過信しない意味でもAIからの回答を待ちます。