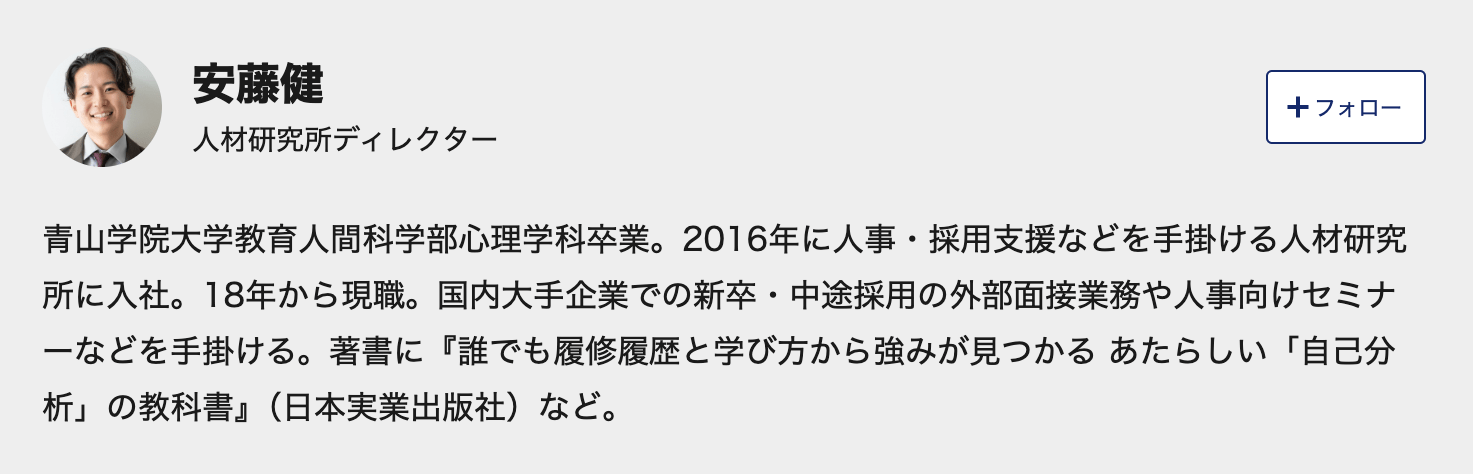85年当時は転職そのものが一般的でなく、SNSもないので、親のつてで紹介してもらうとか、親しい友人の知り合いを紹介してもらうといった形の縁故採用が主流でした。ところが、時代が下って転職が一般的になると同時に、転職活動のやり方も変わり、2000年代のSNSの普及で薄いつながりでネットワーキングできるインフラが整ったということが大きく影響しています。
弱いつながりで
「打席に立つ」回数を増やす
もちろん、自分のことを昔からよく知ってくれている人(強いつながりの人)が紹介してくれた仕事や、転職先は、仕事内容や社内の雰囲気などが、自分に合っている可能性が高く、精度が高いものになるかもしれません。
しかし、たとえば誰かがSNSで転職したいと発信すると、その人のことを全然知らないフォロワーや、そのSNSを外から覗き見ただけの人も、求人があれば紹介してくれることがあります。たとえマッチング的な精度が高くなかったとしても、そういったさまざまな機会が薄く広がっていて、いろいろな話が舞い込む可能性があれば、「打席に立つ」チャンスが増えます。結果的によりよい結論やチャンスに巡り合う確率が高くなるのです。
何と言っても、SNSの普及が、この効果を後押ししています。最近、SNSはSNS疲れ、闇バイトや未成年の犯罪、炎上といった負の側面ばかりが注目され、知らない人とむやみにつながらず、半径3メートル以内の人との仲を深めようという風潮もあります。
しかし、SNSとは、本来弱いつながりの集合を可視化したものでもあります。会ったことのない人と会ったり、X上だけで仲良くなったりする人は確実に増えており、特に若い人ほどこの傾向が強くなっています。SNSの本来の長所を活かす形で、上手に使えば、弱いつながりを基にした、キャリアや転職に役立つツールとして活用できるのです。
【参考文献】
※1 Granovetter, Mark(1973)“The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology, 78, pp.1360-1380.
※2 渡辺 深「転職とネットワーク――1985年から2002年までの日本の労働市場におけるジョブ・マッチング過程の変化(特集 現代の雇用危機を考える)」『学術の動向 : SCJフォーラム』20巻9号、pp.20-25、2015年9月