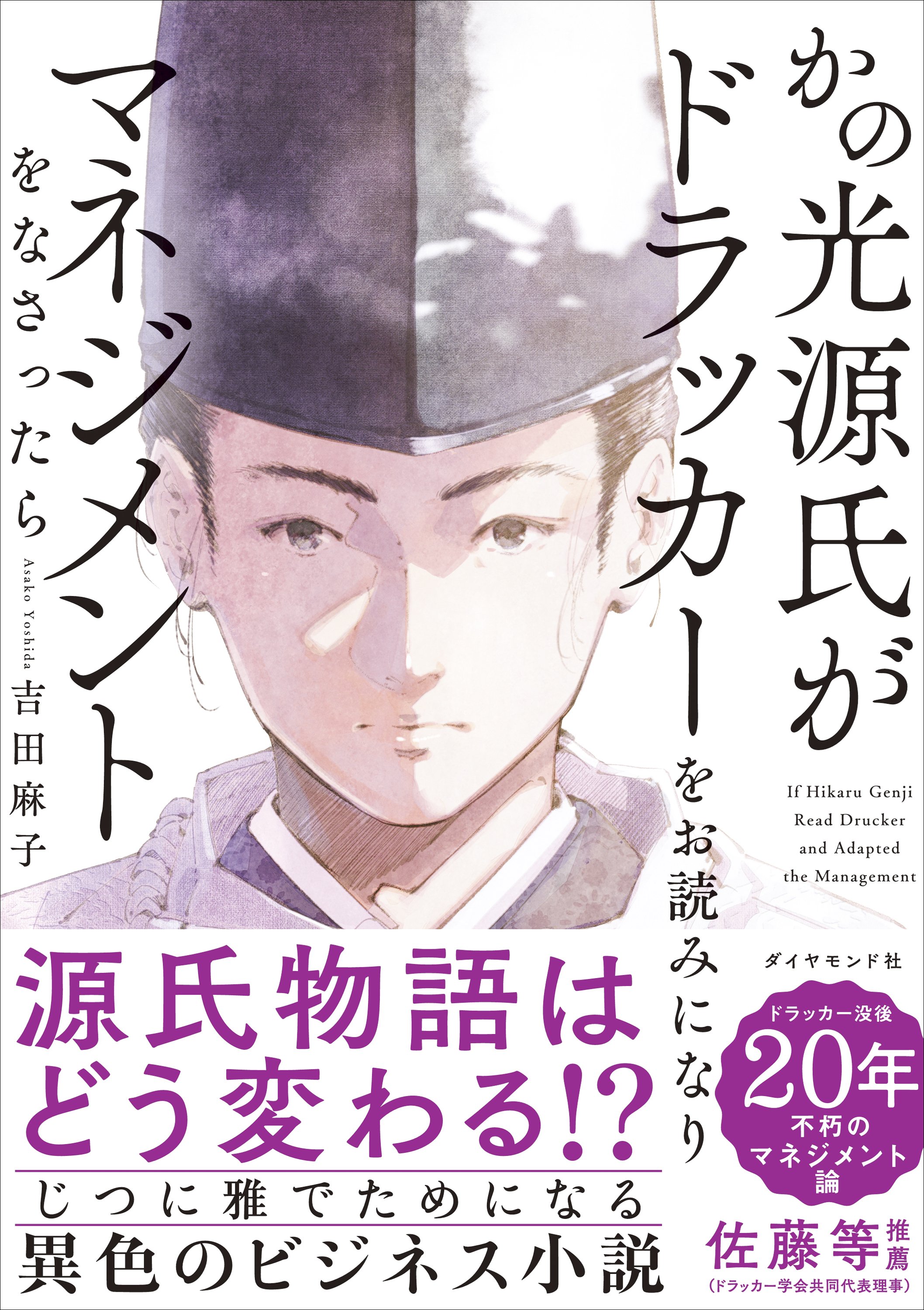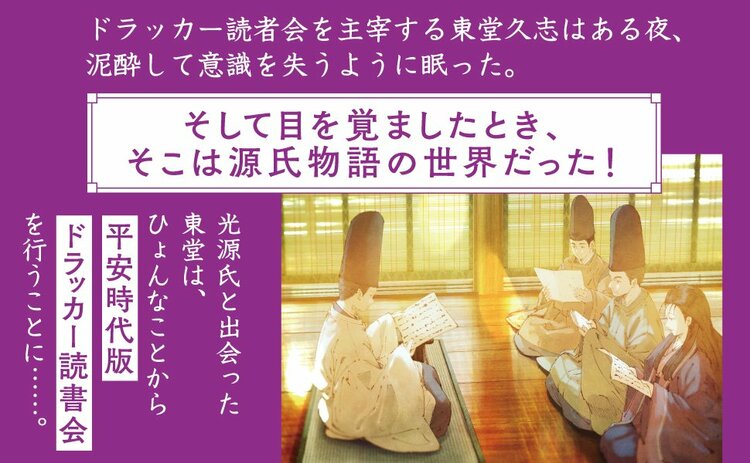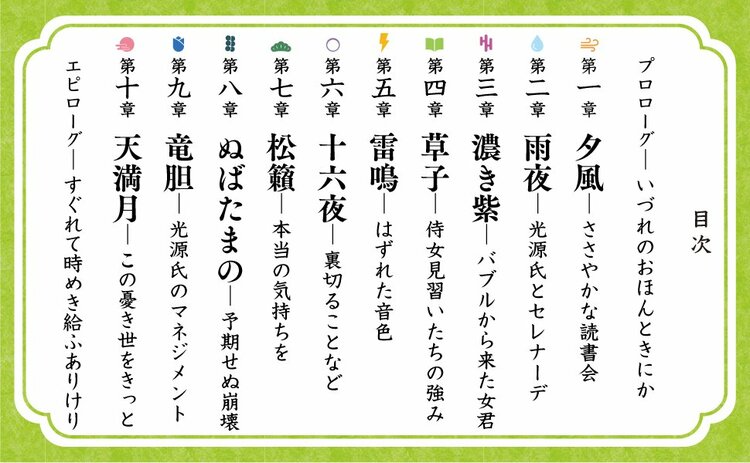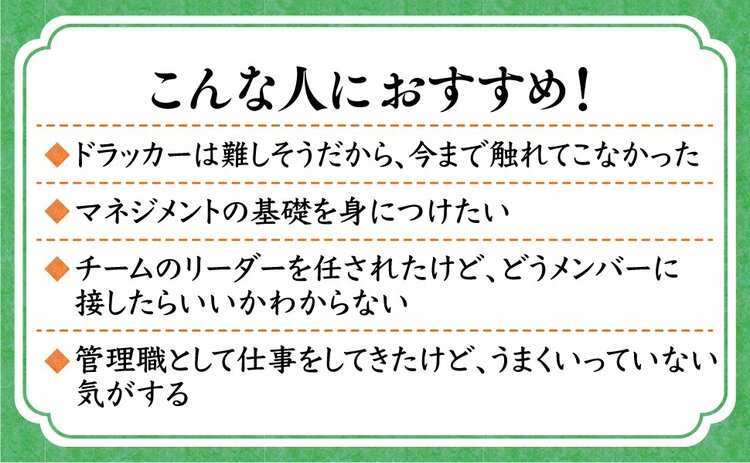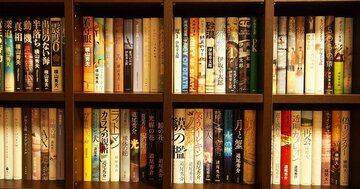成果を出せない“伸び悩む人”はどうする?
――では、成果が出せないような“伸び悩む人”をどう承認し導けばよいでしょう?
吉田:どうして「伸び悩む人」になっているのかを見ていくことが必要ですよね。
まず重要なのは「成果を出せない原因」を“本人の資質”に帰さないことです。
組織の成果に対してどのような貢献をしたらいいかがあいまいになっていたり、強みが生かせていなかったり、どのような努力をすればよいかがわかりづらくなっているという構造的な要因が多くあります。
ドラッカーは『経営者の条件』の『第3章 どのような貢献ができるか』で、「われわれは貢献に焦点を合わせることによって、コミュニケーション、チームワーク、自己開発、人材育成、という成果をあげるうえで必要な四つの基本的能力を身につけることができる」としていて、部下の成長と貢献の関係性について述べています。
具体的にはこうあります。
「自己開発は、その成果の大部分が貢献に焦点を合わせるかどうかにかかっている。組織に対する自らの貢献を問うことは、いかなる自己開発が必要か、いかなる知識や技能を身につけるか、いかなる強みを仕事に適用するか、いかなる基準をもって自らの基準とするかを考えることである」
「自分は組織にどう貢献できるのか」という問いを持たせることが、伸び悩む人を導く鍵となります。
組織の成果に自らの強みを生かして貢献すること。手元の仕事をこなすだけではなく、外の世界の変化に関わろうとすること。
このように視点を高く、遠くにすることによって、意識が変わります。
承認は「小さな改善」や「部分的な強み」に光を当てることから始まります。
「前回より説明が整理されていたね」
「その正確さは報告書づくりにも役立つよ」
このように“できていること”を次の場面へつなげる橋渡しをしていくのです。
リーダーの実力が試されるとき
ドラッカーは「人は自らが自らに課す要求に応じて成長する」といっています。
そして「自らに少ししか求めなければ成長しない。多くを求めるならば何も達成しない者と同じ努力で巨人に成長する」といっているんです。
もしかしたら伸び悩んでいる方は、目の前の仕事と組織の成果を結びつけることができずに、ただ指示を処理する状態に陥っているのかもしれません。
目線をあげて、そもそも何のためにその仕事をしているかを話し合うような機会をつくるところから始めてみてはいかがでしょうか。
伸び悩む人をどう扱うかこそ、リーダーの真摯さが試される瞬間です。
人格ではなく仕事ぶり、弱みではなく強みに焦点を合わせること。そして承認の言葉を投げかけ続けること。
その小さな積み重ねが「貢献の手応え」となり、やがて大きな成長をもたらします。
明日から、目の前の部下に小さな承認をひとつ探してみてください。それが本人にとって大きな一歩になるはずです。