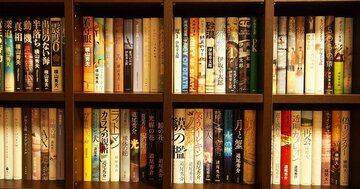もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。
想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。
今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。
「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしいストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。
本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
部下を評価するときにやってはいけないこと
――著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』では、光源氏がドラッカーを学び従者たちを認められるようになったことで、従者たちがいきいきと動きだす場面があります。実際の現場で部下を承認するとき、意識する点はありますか?
吉田麻子(以下、吉田):承認するときに気をつけたいのは、その人の人格や人柄を評価することではなく、「仕事ぶり」「成果」に光を当てることです。
「評価は、仕事に対して行わなければならない」とドラッカーは『現代の経営』でいっています。
部下を褒めるときにたとえば「あなたは優しいね」ではなく、「お客様への説明がとても丁寧でわかりやすかった」と具体的な行動を指摘して承認する。
人格に踏み込む評価は一歩間違えると上下関係の押し付けや表面的なお世辞になってしまう危険があります。
一方で、具体的な仕事ぶりや成果を承認されると本人の自信につながり、再現性のある行動として強みを発揮しやすくなります。
逆に承認ではなく注意をするときも同じですね。
「お前の声小さいな」ではなく、事前に“うちの会社ではお客様への電話対応では相手に聞き取りやすい声の大きさを心掛けること”と評価の基準を明らかにしたうえで、「今の電話の出方は少し声が小さかったね」と仕事ぶりを評価していきます。
――たしかに、上司に注意される場面があったとしても、「仕事ぶり」に対してであれば「次はミスしないようにしよう」と前向きに捉えられる気がします。
吉田:ドラッカーは具体的にこのように書いています。
「評価は、仕事に対して行われなければならない。評価とは判断である。判断には常に基準が必要である。判断とは、一定の価値を適用することである。明確かつ公にされた基準に基づかない判断は恣意である。評価する者とされる者の双方を堕落させる。
いかに科学的であり、いかに多くの洞察を与えてくれるものであっても、潜在能力、人柄、将来性など、証明済みの仕事ぶり以外のものに焦点を合わせた人事評価は、力の濫用である」
このようなことを意識することで、部下を承認する前に必要な基準の提示や、承認するべきポイントなどが明らかになっていくのではないでしょうか。
リーダーは部下の人柄ではなく“仕事ぶり”を承認することが優れた組織の文化を醸成することにつながっていきます。