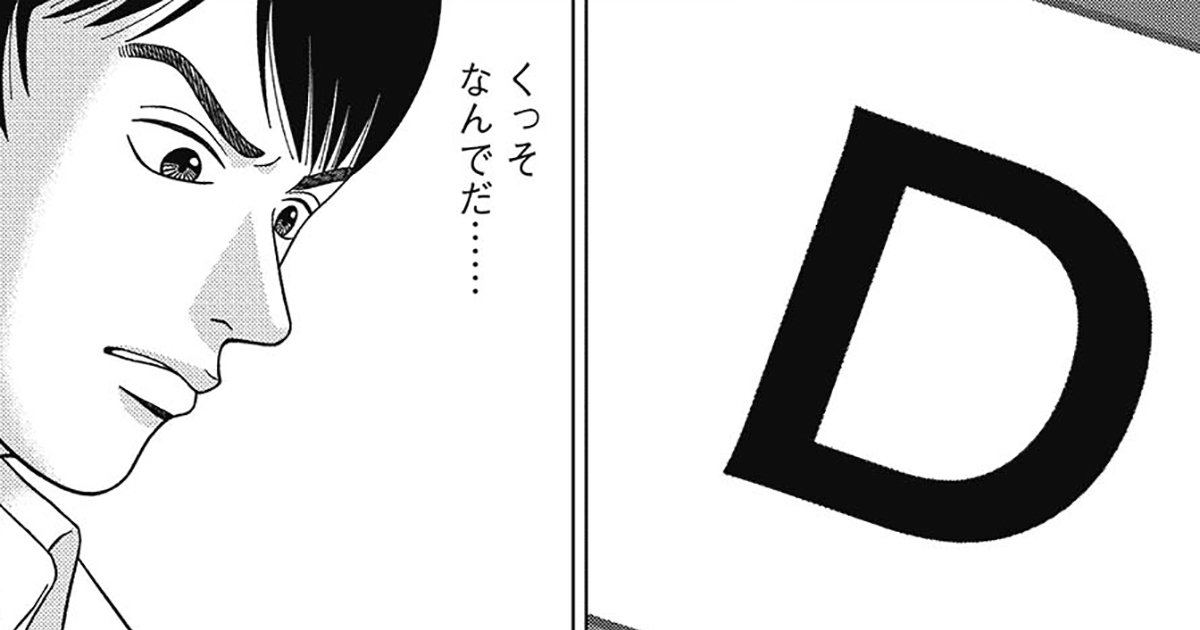 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第90回は、「模擬試験の合格判定」について考える。
「判定」は、どのように算出されるのか
東京大学現役合格を目指し、初めての東大型模試を受けた天野晃一郎と早瀬菜緒だったが、合格可能性はE判定だった。一方、同級生の小杉真里はA判定をとっていた。
塾によって若干の差はあるが、一般的に「A判定」と言えば、合格可能性が80%以上であることを示す。B判定だと60%〜80%、C判定だと40%〜60%といった具合で、E判定だと20%以下だ。ちなみに駿台予備校の東大実践模試など、まれにE判定がない模試もある。
この「合格可能性」は、過去の模試成績と合否の相関や年度ごとの志望者数をもとに、各塾が独自に算出するものだ。模試によってはみんな同じような点数をとるため、わずか数点の違いで判定が2つ3つ変わることもある。
例えば河合塾が実施した第2回共通テスト模試における点数ごとの合格可能性を見てみよう。
東京大学ではA判定とE判定の間がおおむね70点ほどだ。東大受験に必要な共通テストの科目(国語200点、数学200点、英語200点、情報100点、理科社会計300点の合計1000点)を考えると、各科目で数問の差である。頑張れば逆転できるし、逆にいえば逆転される点差だ。
むしろ、D判定とE判定のボーダーに乗ることが大事になってくる。前述した共通テスト模試では、そのボーダーの点数は最も低い文科三類で830点、最も高い理科三類で890点だ。
「E判定→A判定」突然伸びたように見えるが、実は…
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
たとえ共通テストで8割をとってもE判定となるシビアな世界だとE判定の中の位置が重要だ。
「もうすぐD判定のE判定」なのか「まだまだE判定のE判定」なのかは、A判定とE判定の差以上に大きい。仮にE判定をとってもすぐに落ち込むことはせず、E判定の中でどのくらいの順位にいるのかの確認が必要である。
さらに言えば、その模試が共通テスト模試なのか、記述模試なのか、冠模試(各大学に特化した模試)なのか、あるいはどこの塾が実施しているのかといったことでも異なる判定が出ることがある。
特に、人数が少ない模試だとサンプルが偏ることもあり、実力以上の判定が出ることもあるから油断は禁物だ。
個人的には、この合格可能性は天気予報のようなものだと思っている。2週間前に雨予報だった日が前日になるにつれて徐々に晴れていくことがあるように、本番に近づくにつれて正確な値になっていく。もちろんたまたま得意なジャンルから問題が出たといったことはあるだろうが、過去の成績を過度に恐れる必要はない。
私自身、高2から高3の夏まではE判定しかとったことがなく、初めてA判定をとったのは共通テスト後の本番直前模試だ。
こう書くと直前でとても実力がのびたかのように思われるかもしれないが、実際はE判定の間で着々と順位はのびていた。1つの模試の成績にだけ着目するのではなく、推移を見つめることが肝要だ。
判定はあくまでも点数や順位をわかりやすいように抽象化したものにすぎない。各模試の後に配られる詳細な資料を見て、冷静な戦略を立てることが合格への秘訣だろう。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







