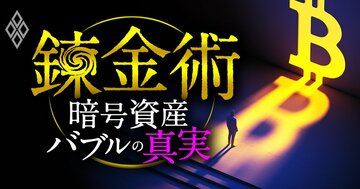「頭をあまり使わずにすむ一方的な会話ばかりしていると、認知機能が衰えやすくなります。
普段、『喋りたいことを勝手に喋る』『他人の話にしっかり耳を傾けない』『質問しようとせず、聞き流す』といったコミュニケーションをしていないか、振り返ってみてください」
会話は互いに球を打ち合うテニスに似ている。相手がどんな球を打ってくるかわからないからこそ、テニスは難しい。
だが、一方的な会話をしている人にとって、ネットの向こうに対戦相手はいない。勝手に球を打つだけのプレイだからさほど難しくないはずだ。
ありがちな会話スタイルが
脳をサボらせる
頭を使わない会話をしているとき、脳では何が起きているのだろう。
脳は基本的に省エネモードだ。脳の重量は体重の2%程度であるにもかかわらず、脳の神経細胞が消費するエネルギーは全身の20%を占めているからである。
人のいない部屋の電気を消すように、脳も使わない神経細胞にはエネルギー、つまり血液中の糖分を出し渋る。
通常、神経細胞は刺激を受けると電気信号を発生して、ほかの神経細胞に情報を伝達する。だが、エネルギー不足の神経細胞は電気信号を発生しなくなり、神経ネットワーク自体が“通行止め”状態となる。
やがて、反応の悪い神経細胞や死滅した神経細胞が増えると、神経ネットワークは“通行止め”から“閉鎖”へと移行してしまう。
次のような会話スタイルは「頭を使わない会話」の典型例だ。定着していれば、神経ネットワークにさまざまなトラブルが生じる可能性がある。
武勇伝好きタイプ
何かといえば過去の手柄話や著名人との親交などを自慢する。毎度同じ話を聞かされ、周囲がうんざりしていてもおかまいなし。
話題どろぼうタイプ
相手が言いかけた話を最後まで聞かず、途中で話題をさらって自分の話を始めてしまう。
無反応タイプ
他人の話を積極的に聞いていない。「ふーん」「へー」ととりあえず相槌を打っているが、実は聞き流して別のことを考えている。知らない言葉が出てきても質問しない。
とりあえず否定タイプ
必ず相手の話を否定する。口癖は「そうじゃなくて」「っていうか」。