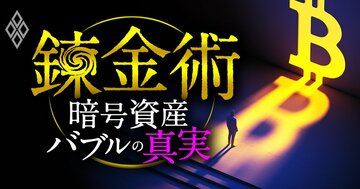(3)「なぜ」を禁句に
ストレートに答えを引き出す「なぜ」ではなく、「いつから」「誰と」「どこで」などを使い、具体的な質問をする。
例えば、自転車通勤している同僚に「なぜ電車を使わないんですか」ではなく、「いつから自転車通勤を始めたんですか」と聞けば、「3年前、親友が自転車を譲ってくれて……」などと語ってくれるかもしれない。
さらに質問を繰り返していけば、相手の人となりや人生が見えてくる。質問しながら洞察力、思考力を駆使しよう。
(4)最近の話をする
昔話ではなく、最近の出来事を語る。
新しい体験や発見、驚きなどを話題にすると、「覚える(記銘)」→「覚えておいて(保持)」→「思い出す(想起)」という3つの記憶の機能を強化できる。常にアンテナを立ててネタを探しておき、アウトプットすることを心がけたい。
(5)固有名詞+数字を駆使する
記憶機能が高い人ほど、体験を具体的に語れることが過去の研究からわかっている。
例えば、旅行で城めぐりをしたのであれば、「天守閣に登ってみたら楽しかった」で終わらせるのでなく、城の名前や築いた大名などの「固有名詞」、天守閣の高さといった「数字」を添えて話すといい。
(6)笑いを仕込む
相手を笑わせる工夫をする。恰好のネタが失敗談だ。
ちょっとしたドジやミスなど、ささやかな“やらかしエピソード”を披露してみる。コントなどを見てお笑いのテクニックやアドリブに学ぶのもいい。
柔軟な発想力、話の構成力、状況判断力、瞬発力を磨くと、脳の神経ネットワークの可塑性も高まる。
常識にしがみつくと
脳は老化で衰えていく
脳の老化による認知機能低下の予防を目指し、2007年から大武氏が提唱してきた会話法が「共想法」だ。大武氏が代表を務める特定非営利活動法人ほのぼの研究所が参加者を募り、実践・普及してきた。約18年間にわたる参加者数はのべ1万人超に上る。
やり方は簡単だ。
3~6人のグループを作り、それぞれ持ち寄った写真や話題について、話し手と聞き手が交互に会話する。制限時間付きで「話す」「聞く」「質問する」「答える」の4プロセスを進めるため、誰かが喋りすぎたり、聞きっぱなしになったりすることがない。