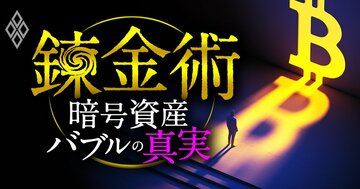「会話内容を分析した結果、共想法に続けて参加した人は言葉をすらすら取り出すとき用いられる認知機能、『言語流暢性』が向上していることがわかりました。言語流暢性は、いわば認知機能のバロメーター。放っておくと加齢とともに衰えてしまいます」
そうなる前に言語流暢性を高めておけば、冒頭のような“困った現象”は起きにくくなるだろう。
「共想法そのものを真似しなくてもいい。会話の習慣を変えることで、脳の神経ネットワークを再構築し、認知機能の底上げができる可能性がある」と大武氏。
その際、先述のポイントに加え、ぜひ意識したいのが「常識にしがみつかないこと」だ。
「常識は国によって違いますし、業界、組織ごとに異なりますよね。時代を経て変わることもしばしばです。人によっては正反対ということもある。この事実を忘れ、『自分は常識的な人間だ』と思い込んでいると、他人の視点を想像できなくなってしまいます」
「到底、共感できない」と思っている他人の価値観も、その人の視点をイメージすることならばできるかもしれない。メガネをかけ替えるようにいろいろな相手の視点を想像し、視点の背景にある立場や状況に思いを馳せる――。
心理学の世界で「パースペクティブテイキング」と呼ばれるこの能力こそ、脳の老化対策における最大の武器、と大武氏は語る。会話を通して多様な考え方を知り、新しい視点として取り入れることで脳の可塑性は高まっていくはずだ。
「相手の視点を見るメガネ」をかけて話を聞き、「最近の話題」を語る。頭に負荷をかけながら会話し、日々、脳を育て直していきたい。
おおたけ・みほこ/理化学研究所革新知能統合研究センター チームディレクター、NPO法人ほのぼの研究所 代表理事・所長。ロボット工学者、認知症予防研究者、博士(工学)(東京大学)。2児の母。認知症を予防する会話支援手法「共想法」を開発。理化学研究所にて認知症予防のためのAI・ロボット研究をチームメンバーと共に推進。文部科学大臣表彰「若手科学者賞」、人工知能学会「現場イノベーション賞」、ドコモ・モバイル・サイエンス賞社会科学部門「選考委員特別賞」などを受賞。主な著書に『脳が長持ちする会話』(ウェッジ)、『介護に役立つ共想法』(中央法規出版)『Electroactive Polymer Gel Robots』(Springer)など。