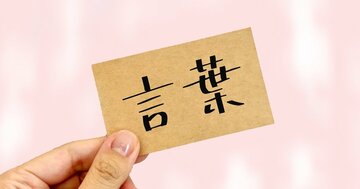これは言葉足らずですが、日本ではごく普通の会話です。この場合あなたは「似たようなデザインで、もう少し軽いものはありませんか?」と言いたかったはずです。
「軽いものはありませんか?」の理由に過ぎない「ちょっと重いんですけど……」だけを伝え、肝心なことは店員さんに察してもらうというコミュニケーションです。
私のパソコンに表示された先ほどのメッセージも、この「察し合う文化」に基づいた文章なのでしょう。
「察し合い」に甘えた説明は
あとでツケが回ってくる
ネット・バンキングでは、送金者がパソコンから受取人の銀行名、支店名、口座番号、口座名義人名などを入力します。普通、ATM機などでの振込では、指定された受取人の口座が本当に存在するかどうか、その場で確認されます。
しかし、当時、私の銀行のネット・バンキングでは、入力された受取人の口座が本当にあるのかどうか、その場では確認されませんでした。たとえ私が振込先の口座番号を間違えて入力しても、ネット・バンキングは、この「振込依頼」を引き受け、しかも「依頼成立」として手数料を徴収するのです。
しかし実際に振込処理される瞬間になって、相手銀行にはその口座がありませんから、この振込依頼は拒否され、振込金額は私の口座へ戻されます。ところがこの場合、手数料は返金されません。銀行は実際に手数を掛けていますし、振込失敗の原因は私の不注意であって銀行のミスではありません。したがって手数料は返金しません――というのが銀行の言い分なのでしょう。
あの短いメッセージで銀行が利用者に伝えたかったことは、以上のようなことなのです。それなら、警告メッセージをたとえば次のように、肝心なことを正確に伝える「分かりやすい文章」にするべきではないでしょうか。
《受取人の口座情報は正しく入力してください。入力された受取人口座が送金先の口座と一致するかどうかの事前確認はしておりません。誤って入力された場合でも、振込のご依頼自体は成立し、振込金額は後日、返金されますが、手数料が発生します。》