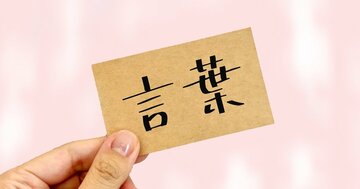写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
読みにくく、何を言っているのかよく分からない――そんな文章に出会ったことはないだろうか?そんな「分かりにくい文章」は、もしかしたら「下手だから」ではなく、“わざと”そう書かれているのかもしれない。なぜ一見して理解し辛い文章が生まれるのか、実例とともに見ていこう。※本稿は、藤沢晃治『「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。
国語的には間違っていないが
肝心なことが分からない文章
ネット・バンキングで自分の銀行口座の入出金を管理している方は多いでしょう。私が買い物代金をネット・バンキングで振り込もうとして、受取人の銀行名、支店名、口座番号、口座名義人名を入力し終えたとき、次のようなメッセージが表示されました。
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
《お振込の受付時に、お受取人名などが正しく入力されているかの確認は行っておりません。》
△△△△△△△△△△△△
この文には、国語的な意味での「表現のまずさ」や「分かりにくさ」はありません。しかし、じつは肝心なことが書かれていない「分かりにくい文章」の典型なのです。
相手の気持ちを察し合う日本独特の文化で暮らしている私たちは、肝心なことをはっきり伝えなくてもコミュニケーションは支障なく進みます。
たとえば、時計屋さんで気に入った腕時計を腕に試着させてもらったところ、予想外に重かったので、あなたは店員さんに言います。
「ちょっと重いんですけど……」