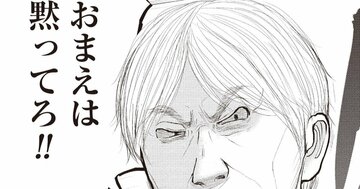『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
さまざまなメディアで取り上げられた押川剛の衝撃のノンフィクションを鬼才・鈴木マサカズの力で完全漫画化!コミックバンチKai(新潮社)で連載されている『「子供を殺してください」という親たち』(原作/押川剛、作画/鈴木マサカズ)のケース3「母と娘の壊れた生活・後編」から、押川氏が漫画に描けなかった登場人物たちのエピソードを紹介する。(株式会社トキワ精神保健事務所所長 押川 剛)
家族という血のつながりは「冷酷さ」もある
トキワ精神保健事務所の「精神障害者移送サービス」にはさまざまな相談が舞い込むが、今回の依頼者は和田朋子(38)で、家に引きこもっている姉(晴美)の「支配下」にある母親を助けたいという内容だった。
押川らは、警察とも連携して和田の実家に入るが、晴美と母親の対応に戸惑う――というのが、今回の漫画のあらすじだ。
初めて晴美さんと対峙したとき、私はその太り方に衝撃を受けた。
部屋のなかにはファーストフードの空き袋や紙コップが散乱していて、毎日食べていたのだろうと想像がついた。私は晴美さんとファーストフードの残骸を見比べ、太った理由を即座に理解した。
体型だけではない。私の経験上、晴美さんは精神疾患ではないかと感じる点が多かった。
私はあえて、彼女の被害妄想の一つである、隣人の「田中さん」のワードを出した。晴美さんは、「ぜんぶ田中が悪い」「あんたたちも田中のグルだ」と言った挙句、同行した警察官までも偽物扱いした。
それは晴美さんが長年抱えてきた彼女の「真実」であり、病状の重さを感じさせるに十分だった。
ほぼ20年ぶりに第三者と対峙する娘を前に、母親は「朋子ちゃんが呼んだ」と、次女のせいにした。この他責思考は、子どもの精神疾患を認めない親の特徴の一つとして、よくみられる。
つまり、自分自身の非を認められる親は、子どもの病気を認めることもできる。自責の念を持てるかどうかは、我が子の病気を受け入れられるかどうかのバロメーターにもなると、私は考えている。
他者に対しても被害妄想や暴言をいう晴美さんを前に、私は警察官が同行してくれたことを非常に心強く感じていた。その心強さもあって、私も彼女と向きあうことができた。私はストレートに「今から病院に行きましょう」と伝えた。
外に出た晴美さんは、その場に立ちすくんだ。20年もの月日を、新聞紙で閉ざされた暗い家のなかで過ごしてきたのだ。陽の光を浴びるのも20年ぶりかもしれない。呆然と立ちすくむ晴美さんの姿を見て、私もまた、陽ざしのまぶしさを痛いほどに感じた。
このケースでは「家族であるがゆえの残酷さ」を感じさせられる場面があった。
晴美さんが病院に向かったあとに、室内を見てまわる妹(朋子さん)の姿である。妹は散々たる家のなかで、淡々とものを探しはじめた。まるで、数日ぶりに実家に寄ったかのような振る舞いである。
母親は、娘の精神疾患を「恥」と捉え、その恥をさらすことを永遠に拒否し、「我が家には病人などいない」という姿勢を貫いた。妹も同じく、姉という事実を無いもののように扱っていた。
逆にこの家を見て、「大変なことになっている!」と思える家族であったら、もっと早くに本人を精神科医療につなげられただろう。私はそこに、家族特有の冷酷さを感じる。血のつながりは、ぬくもりとともに冷たさもあわせ持っているのだ。
晴美さんは、今はグループホームを拠点とした生活を送っている。身体的にはすこぶる健康だが、母親と共依存の関係を築き、長期間ひきこもり生活を続けた事実は重い。
自己中心的な振る舞いから他者とぶつかることも多く、何度も入退院を繰り返し、病院もグループホームも転々としている。しかし初動から携わっている我々からすると、晴美さんがわがままを言いながらも社会とつながり生きている姿は、たくましくもあり微笑ましくもある。
晴美さんと離れることで、母親も心身の健康を取り戻した。母親は数年前に亡くなられたが、晴美さんについて触れることは一切なかったという。
不思議なもので晴美さんもまた、母親や妹について尋ねてくることはなかった。母親の死を伝えた際も、取り乱すでもなく「そうですか」と言うだけだった。
強固に依存しあっていた母娘だが、真の「心」のつながりはなかったのだろう。そんな家族のなかで唯一、相談者である朋子さんだけが、母親の存在を心に宿らせていた。
それは、朋子さんが15、6歳で「家を出たい」と告げた際に、母親が「いいよ」と人間らしい対応したことに帰結する。あのときの母親の「心」によって、朋子さんの「心」も育まれた。
「ひとの心」がなければ、心を病んでいる方を助け出すことはできない。そのことを私自身が学んだケースでもある。
現代社会の裏側に潜む家族と社会の闇をえぐり、その先に光を当てる。マンガの続きは「ニュースな漫画」でチェック!
 『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
 『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社