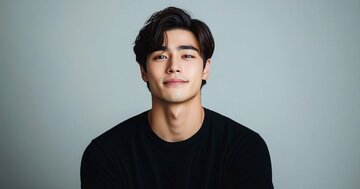AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“専門家”を呼び出す「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、問題の解決策を見つけたいときにおすすめなのが、技法その5「各種専門家の案」です。
こちらが、そのプロンプトです。
多数の専門家(クリエイティブな専門家、技術専門家、ビジネス専門家、学術研究者、社会科学者、ユーザー、ディスラプター、ユーモアのセンスを持つ人々、冒険家)として〈アイデアを得たい対象を記入〉について具体的な案を考えてください。
何回か試したことのある人ならわかると思いますが、ブレインストーミングはマンネリになりがちです。複数人のチームメンバーで話していても、結局は“いつもの”系統のアイデアばかりになる。そんな苦い経験をしたことがある人もいるでしょう。
一方で、この技法を使うとAIが専門家に成り代わって、広範な知識のなかから適切な情報やアイデアを探してくれます。それも1人だけでなく、議論に幅を与えてくれそうな多様な人材を呼び込んで、ブレインストーミングをすることができます。
1人だけでアイデアを出さなければいけない。リソースが不足している。そんなときに、この技法を使ってください。
「赤ちゃんを泣き止ませる方法」を専門家たちと考えてみよう
では、実践してみましょう。この技法の汎用性の高さを感じていただくために、ここはあえて仕事以外の悩みで。
「赤ちゃんを泣き止ませる方法があればいいのに……」。子を持つ親なら、誰もが一度は考えたことのある悩みです。こんな生活の悩みも、広く専門家に考えてもらいましょう。
多数の専門家(クリエイティブな専門家、技術専門家、ビジネス専門家、学術研究者、社会科学者、ユーザー、ディスラプター、ユーモアのセンスを持つ人々、冒険家)として、〈赤ちゃんを泣き止ませる方法や道具〉について具体的な案を考えてください。
プロンプトの中には子育ての専門家はいませんが、さて、どんなアイデアが出てくるのでしょうか?