連動装置とは、駅や信号場でポイントを転換する前に出発したり、走行中に転換したりすると脱線してしまうため、信号とポイントを連動して制御するシステムだ。現在はATCに連動するコンピュータ制御だが、レバーとロッドを組み合わせた物理的な装置は19世紀半ばに発明されている。軌道回路より早く誕生した鉄道の安全の根幹をなす技術である。
梶が谷駅は改修以前、2番線から5番線への進路と、上り本線から3番線に入る進路を同時に構成できなかったが、線路形状を変更して解消した。ところが、なぜかその際、3番線から5番線に入る線路に列車が存在していても、上り本線から3番線に入る線路に青信号が現示される設定になってしまっていたのである。
本来は上りホームである3番線から5番線へ入る列車は1日に1本しかなく、その列車がORPで停止するのはレアケースだったため、誤設定は10年間、見過ごされてきた。今回の回送列車がもし、もっと手前で停止していたら、列車側面に正面から衝突していた可能性も否定できない。事故の芽はいつも思いもよらないところに潜んでいるのだ。
条件が漏れていた原因は調査中で、暫定対策として梶が谷駅5番線の使用を停止し、信号プログラムを改修の上、10月9日に使用再開する。また、同形状の留置線を持つ3駅を含む全駅の連動装置の安全確認を行うとともに、チェック体制の見直しを進めていくとしている。
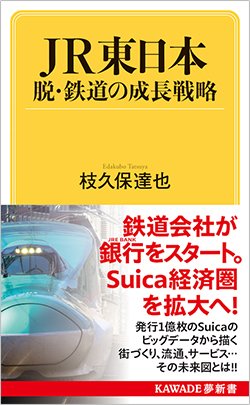 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
今回の事故でATCに対する不安の声があがったが、ある意味でATCは「正常」に機能したのである。ただし、ATCは誤った設定の連動装置が発する指示通りに機能したのである。ATCは極めて安全性の高い保安装置だが、それは設計の範囲内であることが前提だ。
ATCや連動装置の設計に抜け漏れがあった場合はもちろんだが、同じくATCが導入された東横線元住吉駅では2014年2月、大雪の影響でブレーキ性能が低下したことで止まりきれず、停車中の先行列車に追突してしまった事故が起きている。
システムが完璧だったとしても、システムを作る私たちが完璧とは限らない。他社も他山の石として、今回の事故を教訓としてほしい。







