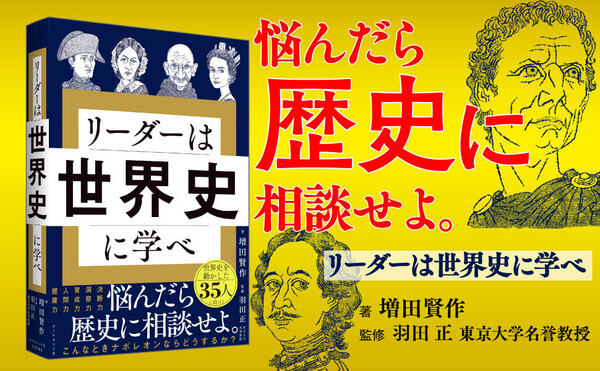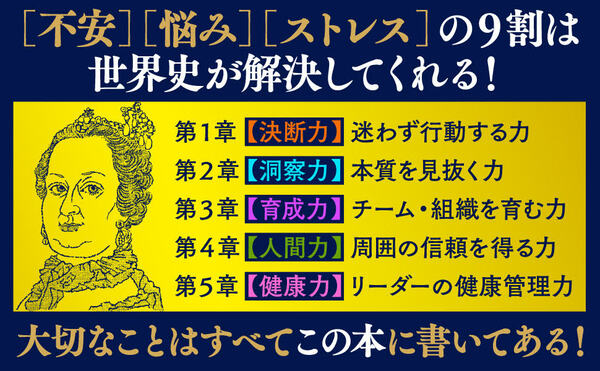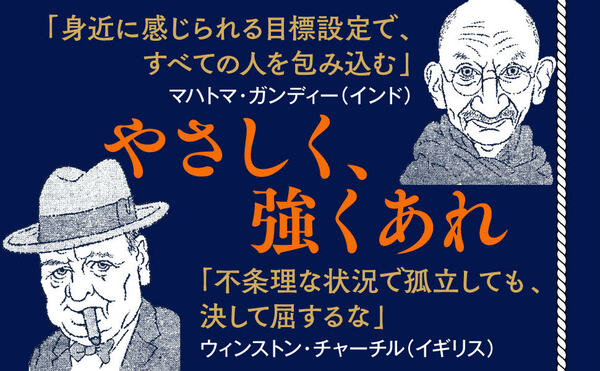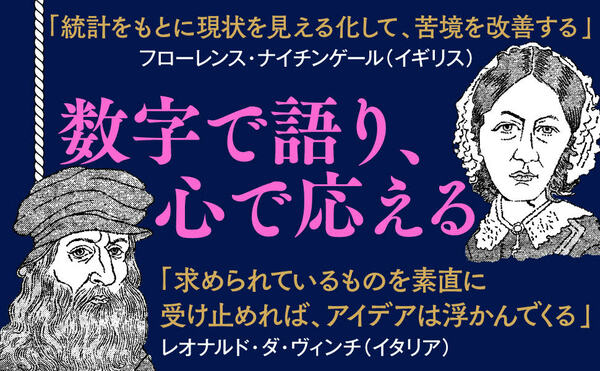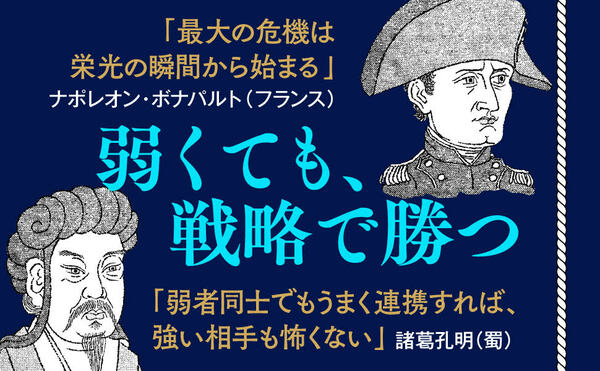➌理想を掲げつつ、現実の「カード」を読み切る
●現実を見失わない判断力――理想だけでは、勝てない戦いがある
サッチャーはフォークランドの奪還に強い信念を持ちつつも、同時に冷徹な現実主義者でもありました。アメリカとの関係がこの戦争の帰趨を握ると見抜き、1956年のスエズ危機の教訓を胸に、支持を得るための外交戦に全力を注いだのです。
そのなかでは、アメリカ・ペルーが提示した調停案に対しても、イギリスの立場を維持しつつ一定の柔軟性を見せる姿勢をとりました(結果としてアルゼンチンがこれを拒否)。この「戦略的な柔軟さ」が、アメリカの事実上の支持を引き出し、イギリスを国際的孤立から守ったのです。
企業経営でも、理想と信念だけでは持続的な成果は得られません。現実を読みとり、適切に折れる柔軟性と、引くべきではない一線を見極める判断力が問われます。
逆境を勝ち抜くための、普遍的なリーダーの姿
サッチャーの戦いは、次の点から現代のリーダーの教科書となります。
●専門家に任せる勇気
●理想と現実のはざまで、最良の選択を探る冷静さ
フォークランド戦争でサッチャーが見せたリーダーの姿は、現代のリーダーにとって逆境における「心の装備」そのものです。
「鉄の女」の教訓を、現代日本でどう活かすか
「鉄の女」と呼ばれたサッチャー元首相。その姿に、自身の理想を重ねるリーダーは少なくありません。日本初の女性首相になる可能性がある自民党総裁の高市早苗氏もまた、サッチャーを信奉する一人として知られています。
では、私たちはこの歴史的なリーダーシップから、具体的に何を学び、明日からの行動に活かせるのでしょうか。
まず「自分の弱さ」の棚卸しから
サッチャーの強さは、軍事の素人であるという「弱さ」を認めることから始まりました。私たちも、リーダーとしてすべてを完璧にこなす必要はありません。
むしろ、自分の不得手な領域を正直に認め、その道のプロフェッショナルに心から敬意を払い、任せる。その「自己認識力」こそが、逆境を乗り越える最強のチームを生み出す第一歩です。
日常に潜む「小さなフォークランド」
国家の存亡をかけた戦争ほどでなくとも、私たちの職場や人生には、決断を迫られる「小さなフォークランド紛争」が常に存在します。
それは、不採算事業からの撤退かもしれませんし、困難な人事評価かもしれません。その一つひとつから逃げず、恐怖を感じながらも向き合う姿勢が、リーダーとしての信頼を形作ります。
信念という「心の北極星」を持つ
サッチャーには「フォークランドは英国領土である」という揺るぎない信念がありました。しかし彼女は、その理想のためだけに戦ったのではありません。アメリカとの関係性という現実的な力学を冷静に分析し、外交というカードを巧みに使いました。
私たちも、自らの組織やチームが目指すべき理想=「心の北極星」を掲げつつ、目の前の現実、使えるリソース、人間関係といった「手持ちのカード」を冷静に見極める必要があります。この両輪があって初めて、リーダーシップは困難な状況を切り拓く力となるのです。
サッチャーが示したリーダーの「心の装備」は、時代や立場を超え、すべてのビジネスパーソンにとっての羅針盤となり得るでしょう。
※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。