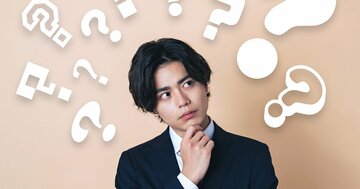そう言うのは入社3年目のD君。すっかりザイオンス効果にはまっていますね。
「ザイオンス効果」とは、ある刺激に触れれば触れるほど共感度が上がり、それを好きになっていくという、「単純接触効果」と言われる研究です。何度も見ていると、その車がカッコイイような気がしてくる。何度も見るタレントさんに親しみが湧き、好感を持つ。CMなどはそれを狙って創られているのですね。
「転職」についても同様で、あまりに頻繁に目にするようになると、「転職は普通のことだ」「転職してしかるべき」という考えが知らぬ間に頭の中に浸透してきて、もはや常識という感覚になってくるかもしれません。
もちろん、コロナ禍以前から、「転職」の広告は電車の中吊り広告にも、テレビCMにもありました。しかし、コロナ禍になりパソコンやネットに向かうオンラインの時間がより長くなり、多くの人がD君のように「転職」というワードに接する機会が何倍にも増えている気がします。
若者が影響を受けるのは見ている時間が長い媒体、つまりオンラインの広告であり、ネットの情報です。
そんな「転職は普通のこと」という日常の上に、仕事上の不満のタネがポトンと落ちたら。土壌はできており、転職への気持ちというタネは序々に芽吹いていくかもしれません。
ミドル世代にとって
転職は「悪」だった
ところが、かたや昭和生まれ平成組のミドル世代にとって、転職とはかなり勇気のいるものでした。というより、むしろ転職は悪、敗北者というイメージすらあったのです。一生、1つの会社で勤め上げ、階段を上るように昇進していくのが順調な人生と思われていました。それが唯一の収入アップ、またはアップしないまでも安定維持できる生き方だというのが社会通念でした。
ではいつから転職に関する意識が変化したのか?
少し振り返ってみましょう。
私は、このキャリアコンサルタントの仕事を1993年にスタートしました。当時まだ誰も「キャリアコンサルタント」と名乗っている人はおらず、「日本初のキャリアコンサルタント」として、10年勤めた会社を同僚と2人で脱サラして起業しました(脱サラ…すでに死語ですね)。