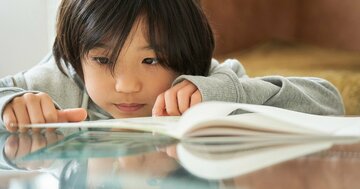提供:日本将棋連盟
提供:日本将棋連盟
将棋のプロ、藤井聡太七冠の“師匠”としても知られる杉本昌隆八段。数多くの子どもたちと接する中で、才能をつぶさないために「絶対に言わないこと」があるという。逆にここ一番の勝負時、力を発揮できるように送る「声がけ」とは?ジャーナリストの笹井恵里子さんが聞いた。(ジャーナリスト・ノンフィクション作家 笹井恵里子)
才能をつぶさないためには
「否定をしない」こと
現在、弟子は全部で10人います。プロとしては藤井聡太七冠、齊藤裕也四段、室田伊緒女流三段、中澤沙耶女流二段、今井絢女流初段の5人、そして奨励会(日本将棋連盟の棋士養成機関)で修行中の5人。
一時期は同時に15人ほどの弟子がいましたね。また以前は将棋教室を開催していたので、その生徒さんも含めると100人近くの子どもたちと接してきたと思います。
「弟子」というと厳しい上下関係があるように感じるかもしれませんが、そんなことはなく、広い意味で“仲間”です。直属の「部下」といってもいいでしょう。
そういう中で彼らと向き合う時、才能をつぶさないために気をつけていることは「否定をしない」ことです。
「ここでは自分ならこうするかな」と
否定ではない表現で指導する
どうしてもこちらのほうが対局の経験や、将棋を指す技術が上ですから、弟子の将棋を見た時に「この場面ではこうしたほうがいいんじゃないか」と言いたくなってしまうんですよね。
もちろん勝つためにその意見が正しい自信はあるのですが、将棋の指し方は弟子の人生観にも関わるところがあります。だからある場面を否定せず、一局(一回の対戦)を通して見る。そして必ずそこで一手や二手は“いい手”がありますから、まずそこを褒める。
「これはいい手だったね」「僕も気づかなかったよ」という具合です。指摘したくなる場面については褒めた後に、「ここでは自分ならこうするかな」と否定ではない表現で指導するようにしています。