シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
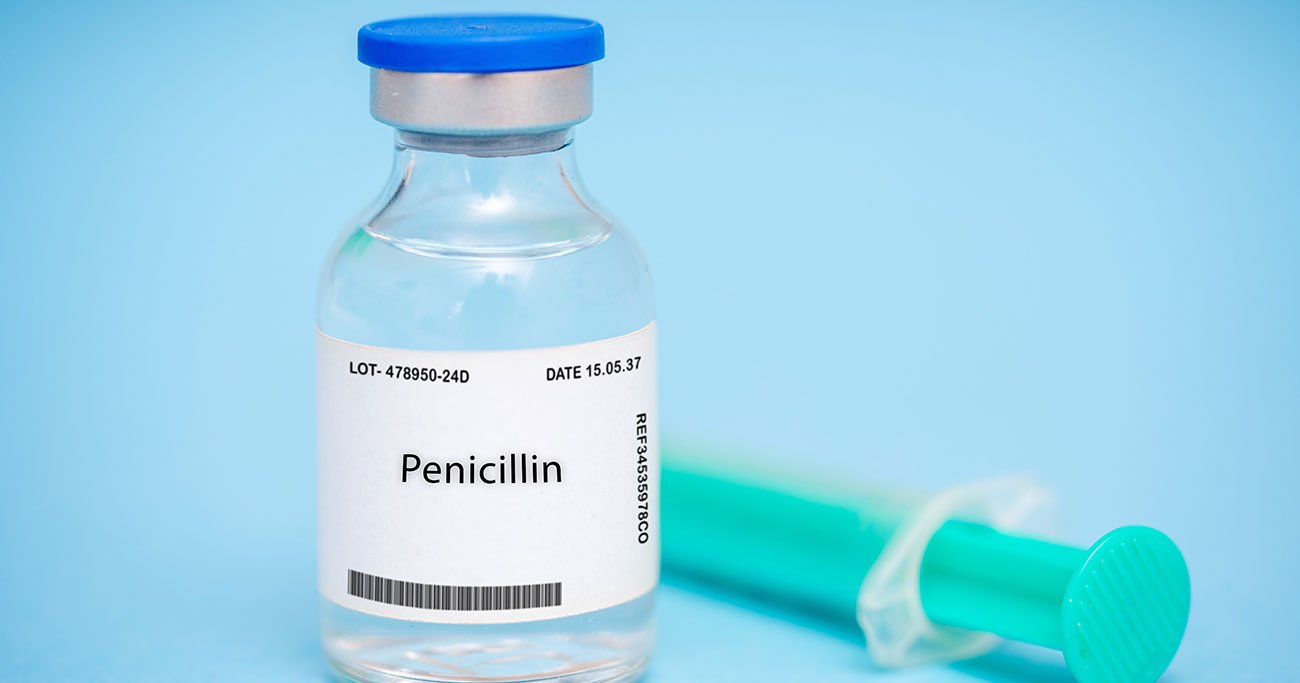 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ペニシリンもトランジスタも
電子レンジも、偶然の発見から生まれた
歴史を学ぶと、多くの重要な発明は、偶然の発見やミスから生まれていることがわかる。以下に、その具体例を挙げてみよう。
ペニシリン:
ペニシリンが、まったく偶然のミスから発見されたことは有名だ。1928年のことだ。イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングは、黄色ブドウ球菌の培養を行っていた際、培養皿(ペトリ皿)を片付けずに放置。その後、皿にアオカビ(ペニシリウム属)が生えていることに気づき、このカビの周囲では細菌の発育阻止が生じていたことを発見。カビが細菌の増殖を抑える物質を生成していることを突き止めた。
この物質をフレミングは「ペニシリン」と名付けたが、実用化には至らず、12年後にフローリーとチェインらの研究チームが大量生産技術を確立した。この発見は、感染症治療に革命をもたらし、多くの命を救うことにつながった。
トランジスタ:
トランジスタも偶然の産物だ。1947年、アメリカのベル研究所でジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテンが高純度のゲルマニウム単結晶を使った実験中に、特定の条件下で電流が増幅される現象を発見。
この現象は、2本の針を近づけて立て、片方に電流を流すと、もう片方に大きな電流が流れるというものだった。この発見を受けて、ウィリアム・ショックレーが、その原理を応用し「トランジスタ」を開発した。
電子レンジ:
電子レンジもたまたまによる発明だ。1945年にアメリカの兵器開発会社レイセオンで働いていた技術者パーシー・スペンサーは、軍事用レーダー装置の実験中、マグネトロン(マイクロ波を発生させる装置)の近くにいた際、ポケットに入れていたチョコレートバーが溶けていることに気づいた。
これによりマイクロ波が食品の加熱に利用できることを発見。これをきっかけに、レイセオンが電子レンジを製品化した。
ペースメーカー:
ペースメーカーの発明も、偶然の発見がきっかけとなった。1950年にカナダの技術者ジョン・ホップスが低体温症を治療するための実験を行っていた際、偶然にも心臓が人工的な電気刺激によって再び動き始めることを発見。この発見がペースメーカーの開発につながり、後に心臓疾患の治療に革命をもたらす装置として発展した。
ポスト・イット:
ポスト・イットは3M社の研究者スペンサー・シルバーが強力な接着剤を作ろうとして失敗し、偶然にも、弱い接着剤を発明したことがきっかけだ。
このように、人類の画期的な発明の多くは計画的な研究の成果ではなく、偶然の観察から始まったものだ。
つまり、今後は画期的な発明の多くは、AIがロジカルな実験をやって実現していくと言われるが、それだけでは人類の発展に十分ではないだろう。
ミスを犯さないAI(人工知能)は、ミスをミスとして認めず、そこに有意性を見出せない。
つまり、AIでは、上記のようなミスが生み出した画期的な発明は生まれない。このあたりは十分、人間の出番があるのではないだろうか。
(本稿は『君はなぜ学ばないのか?』の一部を抜粋・編集したものです)
シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授(2022~2026年)。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院(MBA)、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM&A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官(経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権)を務めた。
2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者(29名)を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース(事例)の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。
2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。
CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。



