
田村耕太郎
日米開戦を避ける選択肢は、あったのか?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

思考力を鍛えるためにおススメしたい、最高の頭のトレーニングとは
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

【大物政治家から学んだ凄いワザ】優れた講演者が常に心掛けている、たった1つのこと
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

なぜ欧米の大学入試では、自分の歴史を書かせるのか?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

「グランメゾン東京」より「ササミフライ一本」が強い! ――メニューを絞り込んだ飲食店の強み
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

頭でっかちのエリートではなく、不遇や苦労を経験する人が評価される時代
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

「年収」ではなく「資産」が大事なワケ
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

日本とアメリカの関係は、これからどうなる?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

ほとんどの人が賛同しない真実を見つけよ――狭き門より入れ
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
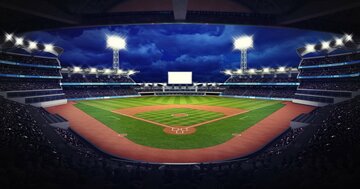
投資は美人コンテストと言われるが、スタートアップへの投資ではどうするか?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

【投資で成功するカギ】みにくいアヒルの子を見つけられるか?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

【投資で成功するカギ】本質を見抜く5つの条件とは?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

2万倍のリターンを得た、世界一成功した投資家とは?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

「人生のすべては投資である」の深い意味とは?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

世の中にイノベーションを起こす起爆剤となる、意外な人たちとは?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

人生の道を踏み外さないために実践したい、2つの習慣
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

成功するために欠かせない、難易度が高い2つのチャレンジとは?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

忙し自慢の政治家、時間貧乏の経営者が日本を貧しくする
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

資本主義の社会でやるべき、本当の仕事とは何か?
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。

シンガポールの暇人が教えてくれた資本主義の真実
シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
